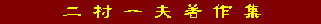足尾暴動
二村 一夫
はじめに
日露戦争後の高揚
日比谷焼打ち事件、電車焼打ち事件、足尾暴動、幌内炭鉱暴動、別子暴動──いささかブッソウな文字が並んだが、これらはみな日露戦争のあと2年たらずのあいだに起こった出来事である。そのころ、ロシアでも「血の日曜日」をきっかけにツァーリにする民衆の反抗がたかまり、あの「戦艦ポチョムキンの反乱」をはじめ、第一次革命の波が全土をおおっていた。この戦争で、日本は莫大な戦費をまかなうために非常な無理をしたが、そのしわよせはみな民衆の上にかぶさった。増税につぐ増税、公債や献金のわりあて、戦時インフレによる実質賃金の切り下げ等々。しかも働きざかりの男がつぎつぎと兵隊にとられ、牛馬から荷車までかりだされた。1方、民衆のこの血と涙と汗の犠牲の上に将軍や高官は富と栄誉をえ、資本家や地主はふところを肥やした。彼らは人民の血税のなかから、各種の補助金、助成金をうけ、20億円にのぼる軍需によって笑いがとまらぬほどのもうけを得た。だが、戦争中「お国のために」と苦しいこともがまんさせられてきた民衆は、戦いが勝利に終ってもなんの利益もあたえられなかった。それどころか終戦翌年の1906、7年と物価はひきつづき高騰し、生活はいっそう苦しくなるばかりだった。はじめにあげた諸事件はこうしたなかであいついで起こったのである。
とくに1906年暮から翌年前半にかけて、労働者階級の反抗運動はかつてない高まりをしめした。1906年暮の大阪砲兵工廠のスト、翌年2月の足尾暴動をかわきりに、三菱造船、生野鉱山(2回)、幾春別炭鉱、幌内炭鉱、別子銅山、夕張炭鉱、歌志内炭鉱等でストライキや暴動が頻発し1907年1年間で、今わかっているだけでも150件近い争議があった。これは第一次大戦前の最高の記録である。とくに注目されるのは鉱山、炭鉱の争議で、件数で全体の2割近くを占め、参加人員でも、そのたかかい方の激しさでも、きわだっている。足尾・別子の場合などは軍隊が出動してようやくしずめえたほどであった。労働争議に軍隊が出るなどということは、それまでほとんど例のないことであった。
どうして鉱山労働者は、このように激しくたたかったのか。また鉱山労働者が闘争に立ちあがれたのは、なぜであるか。いったい、何を要求し、どのようにたたかったのか。なぜ暴動化したのか。こうした疑問を1907年の足尾暴動をめぐって考えてみたい。なぜ足尾暴動を選ぶかといえば、これが一連の鉱山争議のトップをきって、他の争議の盛りあがりを助けたものであり、しかも、もっとも大規模かつ尖鋭な闘争であったこと、さらに重要なことは、ここでは暴動の3年もまえから労働者出身の社会主義者、永岡鶴蔵、南助松らによって指導された労働運動、労働者組織があったことによる。つまり、足尾暴動は、明治末期の労働運動の代表的かつ先進的存在なのだ。だから、われわれは、足尾暴動を知ることによって、明治末期の労働運動のもっとも進んだ部分がどのようなものであったかも知ることができるわけである。
永岡鶴蔵の出現
鉱山労働者があのように激しい闘争に立ちあがれたのはなぜか、というには、もちろんいくつかの理由がある。が、まず注目されるのは、彼らがごく少数ではあったが「労働者のただ一つの武器は団結である」ことを理解し、労働者の組織化のために献身した先進的な労働者をもっていたことである。では、どうして先進的な労働者が育ちえたのだろうか。結論からいってしまえば、それは、鉱山労働者が、それ以前に、長い、きびしい、たたかいの伝統をもっていたからなのだ。永岡鶴蔵の生涯はまさにそのたたかいの伝統そのものである。永岡は1863(文久3)年の生まれ、片山潜の4つ年下である(1914〔大正3〕年没)。彼は17歳で鉱夫となり、その後、各地の鉱山を転々と渡りあるいていた。若いころは、飲む、打つ、買うの三拍子そろった男で、しかも腕っぷしが強く、大勢を相手にけんかをするのが飯より好きだったという。
ところが、この彼が26歳のとき、それまでの生き方を一変させるようなことが起こった。外人宣教師(単税太郎ことC・E・ガルスト?)にキリスト教の話を聞いたのである。彼は今までのデタラメな生活を悔いあらため、残る生涯を正義と人道のために努力しようと決心したという。こうしてキリスト教徒として活動をはじめた永岡は、仲間のおかれている悲惨な状態を見ては、ただ聖書のことばをくり返して、「信ずる者はみな救われん」などとすましかえっていることはできなかった。「なんとかして自分たち鉱夫の状態を改善しなければ」−こういう気持ちがしだいに強くなっていった。
かくて1891(明治24)年、秋田県荒川鉱山で労働余暇会という勉強会を組織したのを出発点として、彼は一歩一歩、労働運動の指導者としての道をあるきはじめる。その歩みを年表ふうにたどってみよう。
明治25年 院内鉱山で鉱業条例の研究会を組織。
明治26年2月 院内鉱山で鉱業条例の遵守を要求し、3日間のストを指導。要求の七分通り獲得。
明治27年5月 秋田県を相手に鉱夫税反対闘争を指導。県下の各鉱山を遊説し「日本鉱山同盟会」を組織。その代表として知事、県会議員を歴訪。11月撤廃に成功。その後山形県朝倉鉱山において、診療所の設置を要求してスト。要求容れられず全員で下山。
明治30年2月 院内鉱山で賃下げ反対のストを組織。警察や暴力団の弾圧をけってデモを敢行。いったんは要求をかちえたが、1カ月後にふたたび賃下げが強行されたため、5月、同志80人をひきいて北炭夕張炭鉱へ渡った。
大日本労働至誠会の創立 優遇保護は只だ夕張よ黄金魔力の闇の闇 聞いて極楽見て地獄殺人会社と夕天地 優遇保護を宣伝して鉱夫を募集していた夕張炭鉱も、来てみればなんのことはない「いずこも同じ秋の夕暮」で、資本家が横暴をきわめていた。鉱夫は8畳の棟割長屋に8人もおしこめられ、毎日激しい労働に追いまわされていた。しかも保安設備が不完全なために、たえずガス爆発の危険にさらされていた。労働者の多くはこの苦しい境遇にまけてしまい、退廃的・刹那主義的になっていた。このありさまをみて、永岡はどうにもじっとしていられなかった。だが、そうはいっても、彼自身6人の家族をかかえ、からだ中の力を吸いとられるような激しい労働に追われて、しばらくは手も足も出なかった。
こうした時も時、永岡は自分と同じ志をもつ、しかも若くて活動的な運搬夫、南助松(1873〔明治6〕年〜現存)と知り合った。10歳も年の違う2人ではあったが、話し合ううちにたちまち意気投合し、1902年5月、相協力して「大日本労働至誠会」を創立した。至誠会は、はじめはキリスト教的労働者矯風会ともいうべき性格のものだったが、運動のなかでしだいに社会主義的色彩を濃くしてゆく。そして、1903年11月、当時全国各地に遊説して社会主義を宣伝していた片山潜を夕張にむかえて、至誠会ははっきりと社会主義を標榜するにいたった。
かねてから「労働問題の解決は労働者自らの力によらねばならぬ」と主張していた片山は、ここに労働者自身の手で、自主的な労働者組織がつくられているのを知り、非常に喜んだ。しかも至誠会は、あの悪名高い治安警察法のもとでも労働者の組織化が可能であることをしめしていた。演説会のあと、片山・永岡・南の3人は夜を徹して日本の労働運動の前途について語り合った。片山は、労働運動の組織者、指導者としての永岡のすぐれた資質と豊かな経験を知り、彼に全国の鉱山を遊説して、鉱山労働者の全国組織をつくることをすすめた。永岡はこれをうけいれ、一方、南は夕張にのこって、北海道の炭鉱労働者の組織化に専念することに方針がきまった。片山はこの夜のおさえきれぬ喜びをこう記している。「余は過去七年間労働運動を為すも、今夜のごとく愉快なる時を過したることなし。夕張の諸有志家は実に北海労働者の花なり。その労働運動は良果を得る蓋し近きにあるべし。」
そして、はやくもその年の12月7日、永岡は後事を南にたくして全国遊説の旅にのぼった。出発にあたって彼が片山に書きおくった決意は、今なおわれわれの胸を打つものがある。
「拝呈毎々御書面被下有難存候 愈々本月七日当地出発致す考へにて準備中に御座候 何分共同店の事業に長らく困難して又ぞろ失敗を重ねたる身の随分の苦戦に有之、貧困の点だけは、カール・マルクスに近く相成候 小生は一大覚悟を以て日本数万の坑夫の為めに一身一家を犠牲にするも頼りみず候……七名の家族を北海の雪中に投じ一家の諸道具を売飛ばし旅費として出発可致候 主義の為めに己が身命を賭して掛る位は当然の事と承知致し居り候 然し一家の処分に就ては大略左の如く相定め候
一、四歳になる子は養女にやる
二、八歳の子は二歳の児の守をなす
三、十歳の子は学校より戻りて菓子売りをなす
四、十三歳の子は朝夕の御飯焚を引受け通学す
五、十五歳の子は昼は器械場に労働し夜は甘酒を売る
六、妻は昼間停車場に出て荷物運搬をなし夜分は甘酒を売ること
右昨日より実行致し居候 愈々之よりは大いに天下に遊説して主義の為めに殉ずる心組みに御座候」
同志会の結成と衰滅
1903年もおしつまった師走の27日、細尾峠を境に日光に接している、ここ足尾銅山に1人の辻占売りが現われた。物好きな男が買ってみると、「労働者諸君団結せよ」「団結は勢力なり」などという文句が書いてあった。この辻占売りこそ、ほかならぬ永岡鶴蔵であった。彼は、当時東洋一の大鉱山として知られていた足尾を、第一の目的地にえらんだのである。
ひと月ばかり、彼は辻占を売りながら街頭演説をしていた。しかしあまり効果があがらず、また生活にも困ってきたので、予定をかえ、本山坑で採鉱夫として働きながら、じっくり腰をすえて活動することにした。昼は坑内で仕事の合い間に「労働の神聖」「団結の必要」を説き、夜は辻占売りをしながら街頭演説をしたり、幻灯会をひらいて労働者の自覚をうながした。17歳のときから25年間きたえた彼の腕の良さと誠実な人柄はたちまち坑夫仲間の信望をあつめ、その語るところに耳を傾けさせた。熱心な活動は、しだいに鉱夫のあいだに反響をよび、毎晩、ひそかに彼のもとをたずねる者が現われるようになった。そして、ついに3月25日には「大日本労働同志会足尾支部」の結成にまでこぎつけた。同志会は共済活動(月5銭の会費をあつめ、会員が傷病で仕事を休んだときは1日6銭保障する)を軸に会員を組織し、演説会、幻灯会等によって労働者の自覚をたかめることに重点をおいた。同志会が会員の不当解雇を2度も撤回させたことは、会の信望をいちじるしくたかめ、半年もたたぬうちに会員は1000名にも達した。そこで、永岡は坑夫をやめて会の活動に専念できるようになった。機関紙『鉱夫の友』が発行され、週刊『平民新聞』とともに鉱夫のあいだにひろがっていった。平民社の西川光二郎らをむかえて何回かひらかれた社会主義演説会は、いつも満員の盛況だった。
ここまでは同志会の発展は順調だった。だが、いつまでもそううまいぐあいにはいかない。はじめはなんの対策ももたなかった資本家側も、この同志会の力の増大におそれをなし、「同志会にはいる者はクビだ」とオドシをかけてきた。飯場頭が中心になって御用団体「協和会」がつくられ、同志会を中傷するデマをとばし、はては永岡の暗殺さえくわだてられた。警察もまた資本家の忠犬ぶりを発揮した。残念ながら、同志会はまだこうした会社と職制と官憲の一致した弾圧をはねのけてたたかうほどには強くなかった。しかもそこへ共済活動のゆきづまりがくわわったため、1905年にはいると、会員はしだいに減少し、会は自然消滅の形となった。
しかし、永岡や、彼のもとで育った十数名の若い活動家たち、井守伸午、山本利一郎、林小太郎、武田誠之助らはけっして落胆せず、月2回の社会主義研究会にあつまって着実に力をたくわえる努力をつづけた。永岡はふたたび辻占や氷水の行商をはじめなければならなかった。だが彼は、こうした困難にあってもけっしてヤケにならず、かえって条件に応じた創意的な活動のスタイルを生みだした。「足尾銅山ラッパ節」「稼ぎ人目ざまし数え歌」といった、鉱夫のみじめな生活を歌い、資本家の横暴に鋭い批判をあびせた歌を自らつくり、また投書箱を設けて鉱夫の声をあつめ、それをもとに雑誌や歌集をつくって、歌いながら売りあるき、しらずしらずのうちに鉱夫の意識をたかめていった。
金銀銅鉄石炭を もしも掘るひと世になくば 文明社会は闇になる 坑夫の値打は此にある
これ程尊い労働者を 豚の住む様な家に入れ 南京米でコキ使い 果ては解雇かあほらしい
ドベラが落ちて(落盤で)惨死して 妻と子供で四人連れ 二五円の涙金 人の命は安いもの
古河さんは御主人か イエイエあいつは違います 弱き我等をふみ倒す 義理も情も知らぬ鬼(足尾銅山労働歌)
具体的要求の実現へ
1906(明治39)年1月、永岡はなんとか運動をもりかえそうとして同志会を改組し、「日本鉱山労働会」を結成した。労働会はゆきづまっていた共済活動をやめ、鉱業法の完全実施、失業者の就職あっせん、資本家の不法行為のばくろ等を目的として運動を再開した。しかしこれにたいしても圧迫は激しく、活動は遅々として進まなかった。そこで永岡は、組織を根本的に立てなおすため、南助松を夕張からまねいた。
同年10月、南の足尾入山を機として、運動はふたたび息をふきかえした。彼らはさっそく「大日本労働至誠会足尾支部」を設立し、演説会を中心に猛烈な運動を開始した。かくて、わずか2カ月余のあいだに、至誠会は会員600名に達する発展をみせる。ひとたび衰運におちいり、永岡らの必死の活動にもかかわらずついに挽回できなかった運動が、なぜこのような短期間に立ちなおれたのであろうか。もちろん理由はいろいろある。五尺六寸のガッシリした体躯から、火をはくような熱弁をふるう南に、鉱夫らが非常なたのもしさを感じたこともあろうし、彼の若く美しい妻、操のかいがいしい働きもあずかって力があったであろう。が、いちばん根本の理由は、至誠会の方針が同志会のそれから一歩前進していたことにある。では、両者の違いはどこにあったか。
12月5日、至誠会の開設式にのぞんだ南は500人の聴衆をまえにして、至誠会の方針をつぎのように説明した。「労働者ガ一致団結シテ、一千人ノ至誠会員ヲ得タル暁ニオイテハ、吾々代表者トナリ賃金値上ゲ、南京米改良ヲ鉱業所ニ要求スル。」当時、賃上げはなににもまして、すべての鉱夫の一致した切実な要求だった。物価は戦争中からひきつづき値上がりをつづけているのに、賃金は12年間も釘づけになったきりであった。そのため、10人のうち6、7人は飯場頭に借金しているしまつだった。また、南京米(外米)はくさくてボロボロで、まるっきり砂をかむようなしろものだった。しかも会社はこのまずい米を一定した価格で.(もちろん、もうけて)供給することによって、なんとか鉱夫の賃上げ要求をおさえるテコとしていたのであり、しかも、欠勤するとその供給量さえ制限されたのである。
「欠番したためお米が出ない、晩のお飯に水を飲む。」
「足腰立つうちゃコキ使い 病気や怪我をした時は 南京米が二升五合(5日間について家族数に関係なく)御主人呼ばわりシャラくさい。」(足尾銅山ラッパ節)
至誠会が同志会と違っていたのは、まさにつぎの点であった。すなわち、労働者のもっとも切実な要求をはっきりしめし、さらにこの要求を実現するための具体的な方針をしめして訴えたこと。ここに、それまでの鉄工組合以来の伝統的な共済活動を中心にした方針からの一歩前進がみられる。
ところで、その「要求実現のための具体的方針」とは何か。できれば彼らは、同盟罷工を呼びかけたかったにちがいない。しかし、当時労働運動圧殺に猛威をふるっていた治安警察法はこれを禁じていた。が、彼らは屈服しなかった。南は言った。「モシ請願シテ容レラレズンバ、手ヲ携エテ比ノ銅山ヲ立去ル覚悟ヲ要ス。」のちに公判で裁判長がこのことばを問題にし「自由廃業モ同盟罷工ト似タモノデハナイカ」と言ったのにたいし、南は堂々とこれを論破している。「人ノ権利トシテ自由廃業ハ勝手デアル。醜業婦デサヘ自由廃業ガ出来ル。況ンヤ労働者ニ於テオヤ。」こうした働く者の見事な論理によって、彼らはこの反動的な法律とたたかったのである。
しかし、彼らはこのときまだ、ストライキや一斉退山をくわだてていたわけではない。それは、あくまでも「労働者の覚悟」として、請願を力強いものとするうらづけと考えていたにすきない。まして、彼らは暴動を教唆扇動するものではけっしてなかった。
暴動の勃発とその結果 こうした力強い方針を得て、南とともに同志会以来の若い活動家達は積極的な行動を開始した。演説会はわずか2カ月ほどのあいだに11回ひらかれ、回を追うにしたがって反響をよんでいった。なかでも、南助松が、鉱業所長南挺三(有名な足尾鉱毒事件当時の東京鉱山監督署長)に公開状を発して立会演説を要求した1月26日のごときは、じつに1150名余の聴衆をあつめ、しかも会場の外にははいりきれない人たちがひしめいていた。ここに、南のアジテーターとしての才能はいかんなく発揮された。彼は、資本家がいかに労働者の生血を吸っているかを説き、職員の不正を糾弾した。鉱夫らはこれを拍手喝采してむかえ、「ヤッツケロー」「打チコロセー」「ヤレヤレ!」と場内は騒然となった。これまで押しつぶされていた不満はあちこちでセキを切ったようにあふれ出し、坑内では公然と同盟罷工が話題にされはじめた。この動きに会社側はまったく狼狽し、急に保安設備を改善したり、これまでは「役員米」とよばれていた白米を鉱夫にも給与すると発表して、なんとか盛りあがりをおさえようとした。が、これは逆に、鉱夫らに団結の力の強さを教えただけだった。
公然たる反抗がはじまった。まっさきにやられたのは、日ごろ鉱夫たちにワイロを強要していた現場職員だった。通洞坑で、製煉で、鉱夫はストライキによって現場職員の排斥に成功した。
鉱夫らの反抗は飯場頭にも向けられた。こんなことは、昔だったら思いもおよばなかったことだった。だが数年前、採鉱法が近代化されたことから、飯場頭は作業請負ができなくなり、それと同時に配下の鉱夫にたいする統制力が弱まっていたのだった。それまでは、鉱夫の賃金も、クビにすることも、飯場頭の自由だったのが、今ではそうもいかなくなっていたからである。鉱夫は飯場頭を昔ほど恐れなくなっていた。
1月27日、ついに通洞坑で飯場頭と鉱夫の正面衝突が起こった。鉱夫側はこれまで不当に奪われていた友子組合(伝統的な鉱夫の共済団体)の交際金の出納権−いわゆる「箱」−の取り戻しを決議し、大挙して飯場頭のところへ押しかけた。飯場頭はやむなく、2月5日を期してこれを鉱夫にもどすことを約束した。だが「箱」は飯場頭の中間搾取の一つの手段だったので、これを失うことは飯場頭にとって大きな痛手であった。
「箱」取り戻しに成功して鉱夫らの気勢はあがった。彼らは、友子組合の坑夫総代(鉱夫の互選により各飯場から2名ずつ出て、友子組合の運営にあたった)を中心として、さらに積極的に闘争に立ちあがった。2月1日、足尾全山の坑夫総代の集まりは、6割の賃上げ、最低賃金80銭、賃金決定に労働者を立ちあわせること、規則制定のさいは事前に労働者の承認を得ること等、24ヵ条の要求を出すことをきめた。こうした鉱夫の活動を、至誠会は井守伸午、大西佐市らの坑夫総代中の有力者を通じて指導していた。しかし、下部の大衆のエネルギーが爆発的にたかまっていくにつれて、自らの下部組織をもたず、友子組合の組織におぶさっていた至誠会には、これを充分に統制し指導することが不可能になっていた。ここに至誠会の致命的な欠陥があった。
一方、「箱」の引き渡しを約束させられた飯場頭は、それに伴う経済的打撃が非常に大きかったので、なんとかこれを巻き返そうと必死の工作をつづけていた。坑夫総代の一人が内密に頭に呼ばれ、300円で「若い者をおだてて役員に乱暴してくれ」とたのまれた。むろん、彼らのねらいは至誠会の一掃にあった。圧制者は危機に追いこまれればどんな卑劣なことをもあえてする、という一つの例がここにもある。
2月4日−「箱」引き渡しの前日−ついに通洞坑内の見張所に石が投げこまれた。これをきっかけに、おさえにおさえられてきた鉱夫たちの不満は、飯場頭の意図をはるかにこえて、全山に爆発した。翌5日には本山坑、簣子橋坑で見張所が襲撃され、役員がたたきだされた。この間、ただちに事態の重大なことをさとった南、永岡は、さっそく現場にかけつけ、必死に暴動の不利を説いて鎮撫に奔走したため、騒ぎは大したこともなくおさまるかにみえた。ところがどうだ。6日朝、警察はまるで予定の行動のように、彼らを暴動の主謀者として拘引してしまったのだ。これを知った鉱夫たちは憤激した。有木坑で、小滝選鉱所で、本山事務所で、ダイナマイトが炸烈し、火がはなたれ、役員がふくろだたきにされた。昼近くには鉱夫の数は5〜600名にも達した。彼らは、指導者を奪われ、しかも酒気を帯びたため、しだいに統制を失い、完全に暴徒と化した。彼らは、うらみかさなる役員をさがしもとめ、本山の職員社宅を打ちこわしてまわった。
所長南挺三は、床下にかくれているところを見つけられ、頭を乱打されて一時は死を伝えられた。すねに傷もつ役員は、洋服をぬぎ、自慢のひげをそりおとし、鉱夫姿に身をやつしてホウホウのていで逃げのびた。夜にはいると、ついに本山の倉庫に火がはなたれ、だれも消す者がないままに、火はつぎつぎと附近の建物をなめ、炎は一晩中天をこがした。
翌7日、一晩たつと、鉱夫らは一応平静をとりもどした。前日の活動の疲労にくわえ、出兵の知らせが彼らの勢いをくじいていた。午後一時、前古河鉱業副社長、時の内相原敬の要請で派遣された帝国陸軍3コ中隊が到着。ただちに戒厳令がしかれ、銃剣にまもられて大検挙がはじまった。かくて、さしも荒れくるった暴動も、わすか3日にして鎮圧されてしまった。暴動全体の参加人員は約2〜3000名と推定され、その大半は採鉱夫であった。
裁判の結果、永岡、南らの無罪は確定した。だが、彼らが営々として築きあげた至誠会の組織は、暴動によって完全に壊滅してしまった。中心的な活動家は鉱山を追われ、「特別要視察人」としてどこへいくにも尾行がついた。
労働運動の敗北と社会主義
このように明治末期の労働運動はそのもっとも進んだところにおいてさえ反抗エネルギーの暴発におわり、組織的活動として持続しえなかった。明治40年1年だけで150件近い争議があったが、いずれもその場かぎりのストライキや暴動におわり、あとには一つの労働組合ものこらなかった。明治期の労働運動がこうした結果におわってしまったのはいったいなぜであろうか。このことを最後に考えておこう。
第一にあげられなければならないのは、天皇制国家権力によるようしゃない弾圧である。治安警察法をはじめとする弾圧法によって労働者の自主的な組織化への動きはつねにその芽ばえのうちにつみとられた。また、官憲をバックとする資本家の干渉も猛烈をきわめた。こうした条件のもとでは労働者の組織的活動はきわめて困難であった。だが、いつの時代にも労働運動に弾圧はつきものである。たんに弾圧の激しさだけでは問題の十分な答えにはならない。当然第二の要因が考えられねばならない。それは、一言でいえば労働者階級の未成熟である。当時の労働者のほとんどは、すぐに成果があがるかどうかもわからぬ組合活動の必要を理解するには、あまりも貧しく、またあまりにも惨めな労働条件におしつぶされていた。彼らは、日ごろは仲間のけんかや、酒・バクチ・女にうさをはらし、またいったん行動に立ちあがったときでも盲目的な反抗によって圧制者にたいする憤激・憎悪を個人的に発散させる方にはしりがちであった。とくにここで主にみてきた鉱山労働者の場合には、貧しさの点でも、労働条件の悪いことでも、他産業とは比較にならないものがあったから、こうした傾向は強かった。このように見てくれば、この時点で労働運動が挫折したことは、いわば「歴史的必然」であったと考えられる。
だが、もしこのとき日本社会党に結集していた社会主義者が労働運動にたいする正しい方針をもち、それによってねばりづよく労働者の組織化に努力していたならば、この事態はあるいは多少の変化をみせていたかもしれない。残念ながら事実はそうではなかった。前項でみたとおり、幸徳に代表される人々は「志士仁人」が政治・言論活動を通じて社会主義的変革を遂行するのだと考え、労働者階級の歴史的役割を理解しえなかった。したがって、そこでは労働者の組織化ははじめから問題にはならなかった。また片山に代表される人々は、労働者階級の歴史的役割を認め、その組織化の必要をも認めていた。しかし彼らは、労働者の組織化は治安警察法のもとでは不可能であるとし、まず普通選挙権を獲得し、治安警察法を改正することがその不可欠の前提だと考えていた。彼らは鉄工組合の失敗の原因をその方針の誤りには求めずに、その時あらわれた治安警察法にすべての責任をおしつけてしまった。だが事実はさきにみたとおり共済活動を中心とする組織方針こそが鉄工組合失敗の原因であり、その方針の克服によって治安警察法のもとでも労働者の組織化はある程度可能であったと思われる。南が参加して以後の至誠会足尾支部の発展は明らかにその可能性をしめている。もちろんこう言ったからといって普選運動が誤りであったというのではない。両者はむしろ並行して進められるべきであった。だが片山らは、この時点で労働組合運動と普選運動とを二者択一的に考え、現在は政治運動のときであるとしてその活動を普選運動にかぎっていた。ここに問題があった。
かくして社会主義者たちは1906−7年へかけての造船所・軍工廠・鉱山などの基幹産業に続発した労働者の自然発生的な闘争を指導することができなかった。いな、指導しようとさえしなかった。もちろん当時の日本社会党が200名にも満たない弱少の勢力で、しかも激しい弾圧のもとにあったことを考えれば、たとえ彼らがこの労働者のたたかいを指導しようとしたとしてもどれだけ成果をあげえたかはわからないが。
だが、もし彼らが足尾暴動の現実をみつめ、また暴動にさきだつ永岡・南らの運動の成果を正しく受けとめていたならば、少なくとも従来の理論的な誤りを訂正し発展させる可能性はあったであろう。足尾暴動の直後にひらかれた日本社会党第二回大会はまさにその残された可能性を現実性に転化させうる一つの機会であったと思われる。
大会は、前年来「余の思想の変化」を表明して党員に大きなショックをあたえていた幸徳の主張−普選の否定、革命は労働者の直接行動によるほかない−を中心に激しい議論がたたかわされ、「直接行動論」「議会政策論」「折衷論」に分立し、火花を散らして衝突した。
これらの論争は、これまでの伝統的な日本社会主義運動の戦術を反省した最初のものとして意味をもっている。とりわけ、幸徳の「直接行動論」は、日本の社会主義運動がこれまで採用してきた議会主義的合法主義が、天皇制権力のまえにいかに無力であったかを反省したうえに築かれたものであり、ロシア第一革命を先頭とする世界の革命的潮流に鋭敏に呼応しようとしたものであった。幸徳の「直接行動論」の底には天皇制への批判の萌芽がみられたが、この問題は発展させられなかった。幸徳はまた、労働者が革命の主体であるという点をみとめていたが、そこでは議会政策を否定し、労働者の直接行動の威力を説くのみで、直接行動の不可欠の前提としての労働者の組織化、自覚の喚起については何らの方策ももたなかった。労働者階級と遊離した合法主義への反省は、かれの「志士仁人」的な革命的情熱と結びついて急速にアナルコ・コミュニズムに傾倒していく結果となった。堺、山川均らは議会主義、合法主義を批判するあまり、社会主義と無政府主義との区別さえ意識せずに幸徳と結びつき、片山派に「修正主義」のレッテルを貼り、「総同盟罷工」論から「暴動是認」の思想にまで陥っていた。これにたいし、田添鉄二らの、いわゆる「議会政策派」の人々は、労働者教育を有力な手段としての普選の意義を正しくしめした。しかし、彼らもその方針だけではゆきづまっている労働運動を打解しえないことを認識していなかった。かれらは、天皇制の本質を理解できずに帝国憲法を是認し、帝国議会の機能を信頼し、また「工場法」などで資本家の良心を信じた結果、最後まで合法主義の段階を抜けきることはできなかった。そのためにその後のねばり強い、しつような呼びかけにもかかわらす、狂暴な弾圧のまえに労働者階級を組織することができず、万策つきて挫折した。
幸徳らは、国民の自由と権利を圧殺する根源である天皇制に批判をもち、その打倒のために革命的闘争を計画した。しかし、かれらも、天皇制の本質を政治機構として把握していたわけではなかった。したがって、かれらの運動は、階級的大衆闘争を組織する方向にむかわないで、「天皇個人」にたいするテロリズムの方法でその目的をたっしようとする焦った戦術がそのなかの一部の人々によって採用された。1910(明治43)年5月、宮下太吉、管野スガらによる天皇暗殺計画を知った政府は、幸徳をはじめ、この計画にはなんら関係のない数百名の社会主義者、無政府主義者を全国的に検挙し、暗黒裁判で、いわゆる「大逆事件」をでっちあげ、幸徳ら12名を死刑に、12名を無期懲役に処した。
言論、思想、集会、結社の自由は極度に圧迫され、社会主義運動の「冬の時代」が到来した。
初出は『学習の友』第69号(1959年7月号)、その後補正して労働運動史研究会編『日本労働運動の歴史』(三一書房、1960年10月)に再録。
|