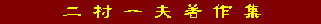鉱山労働運動小史
二村 一夫
はじめに
鉱山業における労働運動あるいは労資関係に関する従来の研究には、歴史的変化を無視、あるいは軽視しているものが少なくないように思われます。ほとんどの通史は、明治期の鉱山労働者の運動を「飯場制の苛酷な支配の下で窮乏化した鉱夫が自然発生的に起こした暴動」と規定しています。また飯場制度についても、大山敷太郎氏のように、あらゆる時期、いたる所にその強固な存続を主張する見解が少なくありません。
しかしこのような非歴史的方法では、問題を正しく把握することはできないでしょう。必要なことは、日本資本主義の資本蓄積の運動法則と日本労働運動の歴史的な変化との内的な相互連関を明らかにすることであると考えます。それには生産諸力の発展にともなう生産諸関係の変化を具体的に把握しなくてはならないでしょう。さし当っては資本蓄積の進行にともなう生産過程、労働組織、労働市場の変化とその特質を明らかにし、これと労働者の主体的な運動との相互連関を明らかにすることから始めなければならない。ここでは明治初年から大正期に限って問題を具体的に検討してみたいと思います。
鉱山労働運動の歴史的展開
そこでまず、この間に展開した金属鉱山における労働運動を概観しておきましょう。それは決して一様ではなく、次に見るように明らかに質の異った運動が存在しています。
(1)明治初年の鉱山騒擾
周知の鉱山官収、つまり官営鉱山の発足時におきた騒擾です。具体的には生野、佐渡、院内などの鉱山で起きたものですが、史料が限られており、その実態はまだ不明な点が少なくありません。村串仁三郎氏は、これらを機械打ちこわしのラダイト的闘争としてとらえています(法政短大『商経論集』第7号)。しかし、実際に機械の打ちこわしを行った例はほとんどないように思われます。今後さらに検討が必要でしょう。
ところで、しばしばこうした官営鉱山における騒擾と同一視されてきた高島炭坑における一連の暴動については、林基氏、村串仁三郎氏らの一連の研究によって明らかにされつつありますが、多くは賃上げストが暴動化したもので、生野などの騒擾とは本質的に異なったものでした。
(2)明治20〜30年前半のストライキ
明治20年代から30年前半にかけて、各地の金属鉱山でストライキが起きています。断片的な記録か二次史料によるものが多いのでさらなる検討が必要ですが、永岡鶴蔵「坑夫の生涯」、『木村長七自伝』、隅谷三喜男『日本賃労働史論』などに、太良、草倉、朝日、院内などにおけるストについての記述があります。また『日本鉱業会誌』63号・76号には、鉱山経営者の一人が、坑夫がしばしば同盟罷業を起こしている事実を指摘し、これに対する方策を論議しています。また、永岡鶴蔵の「坑夫の生涯」には、秋田県を相手にした鉱夫税撤廃闘争など質的に高い運動が展開されている事実も知られています。このように見てくると、この時期の鉱山労働者のストライキはかなり組織的で、また予想以上に数多く発生しているのではないでしょうか。また、同じ永岡の自伝で、明治26年の院内銀山のストでは、請負人がスト中の糧食を供給している点が注目されます。つまり飯場頭が労働者の側に立って経営者と対抗しているのです。
(3)明治40年の一連の鉱山暴動
周知の足尾暴動、別子暴動などです。これについての詳細は今回は省略します。
(4)友愛会支部の結成
大正元(1912)年には友愛会が結成され、大正4(1915)年には各地の鉱山に支部が結成されています。金属鉱山では秋田の各鉱山、日立、足尾などに、また炭坑でも常磐や九州の香焼炭坑などに支部が組織されています。とくに常磐炭田では友愛会最初の連合会が結成されるなど一時的にはかなりの発展を見せています。
(5)1919年、労働組合の続出
足尾銅山では大日本鉱山労働同盟会が最大勢力でしたが、全国坑夫組合および友愛会も支部を結成しています。大日本鉱山労働同盟会は釜石にも支部を組織し、幹部をのりこえて争議を展開しています。また全国坑夫組合は東大の新人会の会員が中心になり、友子同盟を組織基盤として全国各地に組織をひろげました。友愛会も常磐をはじめ各地の鉱山に支部を組織し、友愛会鉱山部をつくりました。その中心になったのも、これまた新人会の麻生久らでた。以上の三組合が合同して、翌1920(大正9)年には全日本鉱夫総連合会が結成されました。
(6)1920(大正9)年以降の御用組合結成
一方この時期には、足尾、日立、北炭など自主的労働組合運動の主要基盤だった鉱山で、相次いで御用組合が結成されます。足尾銅山では、1907年の暴動後に飯場制度を改変して組織された「鉱夫飯場組合」が「鉱職夫組合」へと再編されました。この組合は名目だけでしたが「労働条件の維持改善」を規約にうたい、ILO労働代表の選出権をもつ労働組合の形をとったもので、他鉱山の会社組合とは若干異なっていました。その他での財閥系の鉱山でも、1920年代の終わりまでには、「会社組合」が労働者を組織し、自主的な労働組合運動は企業内から追放されてしまいます。これ以降、自主的労働組合は恒常的な組織を企業内に維持することは出来なくなります。労働者の自主的組織としては、名前は労働組合でも、実態は活動家だけの争議応援団的存在となっています。
運動の歴史的変化の背景
以上のような鉱山労働運動の歴史的変化は、鉱山業の発展にともなう技術の進歩、労働組織の編制替えや労働市場の動向と密接に関連しています。
山師制
飯場制度の原型は、近世の鉱山業における「山師制」にあると思われます。幕藩体制のもとでは鉱山はすべて領主の支配下にありました。領主が奉行や代官をおいて直接鉱山を経営する「直山」と、一定の運上を納める条件で商人らに操業を請け負わせる「請山」にわかれていました。ただどちらの場合でも、代官や請け主が直接生産に関与することはなく、実際に生産面を掌握していたのは「山師」でした。かれら山師は、1ヵ所から2、3ヵ所の間歩の操業を請負い、自ら必要な生産手段を所有し、坑夫、手子、製煉夫などを雇い、採鉱から製錬までの全過程を自己の採算と責任において経営していたのです。この形は明治初年まで続きましたが、開国後に欧米から新技術が導入され、排水や運搬の機械化がすすむにつれて飯場制度に再編されて行きました。
飯場制度
飯場制度の機能
統一的開坑、排水、運搬の機械化など洋式技術を導入した鉱山では、もはや山師制度は存在しえず、これを再編した「飯場制度」が生まれました。飯場制度は、次の2つの機能をもっていました。
(1)作業請負の機能
(2)労働力確保の機能
この二つの機能により、飯場頭は外見的、あるいは当事者の主観の上では「坑夫の事実上の雇い主」で、坑夫に対し強力な支配力を有していたのです。飯場頭がこのような権限をもつっていたのは、採鉱作業がツチとノミを使う手工的熟練に依存する「抜掘法」だったことにあります。「抜掘法」では、搬出される粗鉱は即精鉱でしたから、選鉱や運搬の設備投資が少くてすみました。抜掘によって得られた利益を鉱業資本は主として選鉱、製錬部門に投入し、機械化・近代化をすすめました。機械化の困難な採鉱部門は、専業の採鉱夫中の熟練者に請け負わせたのです。これが前期の飯場制度です。この段階では、資本と飯場頭の間ではたえず請負代価をめぐる対立がありました。明治20年代から30年代にかけて鉱山で多発したストライキの背景には、こうした請負代価をめぐる対立があったものと思われます。
このように労働力集約型の採鉱作業をもつ鉱山業では、生産を拡大するには、労働力の確保がきわめて重要でした。これを具体的な数字で見ると、明治33年現在、日本全国で1,000人以上の労働者を擁する事業所63箇所のうち、鉱山は実に28箇所を占めていたことからも分かります。1909(明治42)年の10人以上規模の男子労働者52万人のうち、36%は鉱山・炭鉱にいたのです。もともと地下労働で危険率も高い鉱山に、このように多数の労働力を確保することは容易ではありませんでした。飯場制による労働力の確保が必要とされたのはこのためでした。飯場頭はさまざまな縁故を通じて労働者を募集し、自己の経営する飯場に泊め、前貸金や物品の供給、入坑督励などにあたったのです。つまり飯場制度は、日本の資本主義が生み出した制度で、その維持のために前近代的関係が利用されたに過ぎないのです。
飯場制度の変質
「抜掘り」採鉱法は、本質的に精鉱掘であり、運搬、選鉱、製錬の投資がすくなくてすむ反面、a)堀り跡がせまく、不規則となり、採鉱・運搬能率が逓減する、b)計画採掘でなく鉱山の寿命を縮める、c)機械化が不可能となる──などの欠陥がありました。こうした問題を解決するため、鉱業資本はある程度経営が安定すると長期的、計画的な経営方針を確立する必要にせまられます。その一環として、明治30年代後半以降、全国的に「抜き掘」から「階段掘り」への移行が進みました。
この変化により、飯場頭は作業請負的機能を奪われ、生産過程から排除されます。坑夫は資本と直接雇用関係をむすび、これまで飯場頭が作業請負で得た中間利潤を資本に吸収する形となったのです。これを補うために、飯場頭は賄料の値上げなど流通面での収奪を強化しました。明治40年の足尾争議で、坑夫側が友子の箱の権利を飯場頭から取戻したことは、弱小飯場が経営的にたちゆかなくなると言われたほど、飯場頭は弱体化していたのです。これに代るべき資本の労務政策はまだ確立せず、経営近代化に伴う規則づくめの一方的な圧制が加わり、坑夫と資本との対立となる。特に間代をめぐる下級職制の収賄の問題からはげしい対立関係が生じる。ここに明治40年の一連の鉱山争議の基盤があったと思います。
友子同盟
明治20年代、および40年の鉱山争議に、友子同盟が大きな役割を果していました。かつて風早八十二、山田盛太郎、平野義太郎氏ら講座派の論客は、友子同盟を飯場制度とほとんど同一視していました。おそらく、これは昭和期における友子同盟の実態をそのまま過去にさかのぼらせたものでしょう。これについても、問題を歴史的に見る必要があります。友子同盟の基礎は採鉱がツチとノミによる手工的作業で、熟練を要することから、技術習得のため親分子分関係を結んだことにあると思われます。これが坑内作業にともなう労働災害やよろけなどの職業病に対する相互扶助の必要から共済機能をそなえるにいたったものでしょう。その点ではヨーロッパの職人ギルドと共通した側面をもっていましたが、職人ギルドが労働条件を自律的に規制したのに対し、友子同盟はそうした機能をほとんど持たなかったようです。また、鑿岩機の導入などの機械化に対しても、日本の鉱夫が抵抗らしい抵抗を示していないことも、この点とかかわりがあると考えます。
とはいえ鉱山労働者が早くから事実上の賃労働者として専業化し、友子同盟という自主的な組織をもつにいたっていたことは、鉱山業における労働運動の発展にとって積極的な意味あいがあったと思われます。たとえば、明治20年代の秋田県を相手とした鉱夫税反対闘争で、県下の坑夫が団結して反対運動を展開したことは、友子同盟の存在抜きには考えられません。永岡鶴蔵が足尾銅山で3年間も活動を続けることが出来たのも、友子の一宿一飯の慣行が存在したからでしょう。友子の伝統が弱かった筑豊では、活動家が鉱業所の用地内に入ることさえ容易でなかったことと対比して考えれば、その積極的な側面が分かると思います。
後期飯場制の確立
明治40年の一連の暴動は、賃金の一括代理受取の禁止や中間搾取の制限などにより、飯場頭の独自性を弱め、その鉱業資本への従属性を強めました。また労働者の運動も、反抗エネルギーの暴発に終わり、組織的、持続的な運動となり得なかったため、飯場制度や友子同盟再編の主導権は完全に資本の手に握られてしまいまいた。ここで、労働力確保を主な機能とする「後期飯場制」が確立します。ところで、この時期の採鉱部門の近代化は、粗鉱運搬、排水、竪坑運搬などでは機械化が進みましたが、採掘作業は階段掘の導入や、ダイナマイト・火薬使用の増大にもかかわらず、機械化せず依然として手掘り作業にとどまっていました。このため、第一次大戦時の急激な生産拡大にともない、採鉱部門における労働力需要は急速に増大しました。これを具体的に鉱山労働者の数でみると、1907(明治40)年に約7万7000人にであったものが、1917(大正6)年には実に16万5000人に達しているのです。
労働運動の新たな基盤
この急激な拡大期に、採鉱技術の機械化は急速に進みました。開坑、探鉱作業では鑿岩機の使用が主力となっています。1914(大正3)年には足尾と別子で小型鑿岩機が完成し、採鉱作業にも鑿岩機が使用されるようになります。これと並行して運搬系統の機械化もすすみ、選鉱部門においても比重選鉱・浮遊選鉱などが採用されました。早くから機械化が進んでいた製銅部門は独立して工場化します。こうした変化にともなって、鉱山における機械部門も大幅に拡大しています。
つぎの表でご覧いただけるように、足尾では坑内運搬夫・雑夫の比率が低下し、機械夫・工作夫が急激に上昇しています。1917(大正6)年になると工作夫469人、機械夫533人、計1002人にも達しています。鉱山業は、巨大な機械工場を付属させるにいたったのです。友愛会は機械工を中心に組織を拡げていましたが、鉱山でも機械夫、工作夫を核にして組織化をすすめています。また運動の目標も、社会的地位の向上をめざすものとなります。友愛会の活動を担ったのは、下層社会から離脱しつつあったこれらの人びとが中心だったと思われます。従来の労働運動の通史は窮乏化論を軸として叙述されていますが、極貧層が立上ったというよりこれら新しい時代を担う層が立上ったのだと思います。もちろん彼らは豊だったわけではありませんが、その窮乏の質は以前とは異なっていたと思います。こうした点を十分に考える必要があるのではないでしょうか。
足尾の1919年の争議でも、大日本鉱山労働同盟会の幹部である飯場頭出身の松葉、インテリの綱島らが経営側に買収されて運動から離脱したあと、指導者になったのは機械工出身の高梨二男、石山寅吉、高橋長太郎らでした。彼らはいずれも、1920(大正9)年10月に、三組合が合同して結成された全日本鉱夫総連合会で活躍します。鉱夫総連合会は総同盟に加入し、機関誌『鉱山労働者』を発行し、最高時には7,000人の組合員を擁して、各地の鉱山争議に関与しています。
このような運動の高揚に直面した鉱業資本は、飯場頭を労務管理補助者たる世話役にかえ、同時に従来の紹介手当、入坑手数料などを廃止して月給制とします。つまり、組合の要求である「飯場制度の廃止」を形の上では承認し、同時に世話役を中心にして御用組合を結成させました。この御用組合は、1919(大正8)年10月には鉱夫飯場組合、翌20年3月には鉱職夫組合となり、同1925年1月には鉱職夫組合連合会を組織します。こうした事態に適応出来なかった旧飯場頭の世話役は整理され、代って工手教習所の終了者などが世話役に任命さています。
鉱業資本による労働者支配の貫徹
全日本鉱夫総連合会は、きびしい状況の中で生まれましたが、組織の根を十分に下すことができませんでした。このことは、単なる資本の労務管理政策の変化や、労働運動に対する国家権力によるはげしい弾圧のためとばかりとは言えないと思います。大正末から昭和初年にかけて労働組合が鉱山から閉め出されるにいたった大きな要因は、労働市場における力関係が変化したことにあります。すなわち、1917(大正6)年には16万5000人を数えた金属山の労働者は、1919年には10万人、20年には7万9000人、22年には4万人と、わずか5年間に4分の1に減少してしまい、買手優位の労働市場となったのです。その背景には、当時チリ、コンゴなどで新たな銅鉱床が発見されたり、アメリカの鉱山業の機械化がすすんだことがあります。日本はそれまでの世界有数の産銅国から、輸入国に転落してしまったのです。こうした状況のもとで日本の鉱山業そのものが大打撃を受けました。当然のことながら、日本の鉱山労働者の労働組合運動もきわめて困難な状況に追い込まれたのです。かりに労働組合運動が強固な力をもっていたとしても、こうした状況に対応することは容易ではなかったでしょう。実際には、日本の鉱山労働者は、ようやく全国的な組織を結成した直後のことでした。全国の主要鉱山から自主的な労働組合が閉め出されたのも当然といえば当然の状況だったのです。
1975年10月4日に金属鉱山研究会での報告を、村上安正氏が文章化されたもの。初出は「鉱山業における労資関係の歴史的概観」のタイトルで『金属鉱山研究会会報』第9号(1975年10月)に掲載。2000年11月、著作集への掲載にあたり文章表現を主に若干の訂正をおこなった。
|