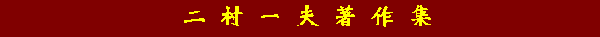s]t
º¡@釗 wú{ɨ¯éJÖWÌWJx
]ÒFñº@êv
P@uåÍà_vÌÏJÆ{̬§j
@º¡釗ªwoÏw_WxÈÇÉ\³ê½_¶ðåÉâ³µAV½È_eàÁ¦ÄAwú{ɨ¯éJÖWÌWJxÆè·éêðÜÆßçê½B±êÜÅu_¼àvâuv¢Â«vÍÈÈ¢ªAÀؤ̼Él·éà̪ÙÆñÇÈ©Á½±ÌªìÅALxÈj¿É ïçê½{ÍAгµÔèÉA¸ÁµèƵ½è²½¦ð´¶³¹Äê½Bº¡ÆÙÆñǯÉAÙÚ¯lÈâèÓ¯ðàÁÄú{Jâè¤Ì¹ÉüÁ½ÉÆÁÄA±ÌåÌdÝÍÐÆ«íÅ éB
@º¡ÆªÙÚ¯lÈâèÓ¯Åoµ½Æ¢¤ÌÍA{Ìq͵ª«rÅmÁ½±ÆÅ éB±±Åº¡Í©ç̤̫Çèð½ÇÁĨçêéªA»Ì`ªÅA¬Ìæ¤Éq×ĨçêéÌÅ éB
@uàÆàÆAª±Ìæ¤Èðj¤É«ð¥Ýüêé±ÆÆÈÁ½ÌÍA¼ÚIÉÍAêãÜÜN Aú{ÌJ^®ªêãÜZNOãÉ×Á½êµÌÈ©©çEµ¦È¢Å¢éðjIóµÌÈ©ÅAåwwÌKɨ¢ÄAw±³öÅ çê½åÍàêj³ö©ç¤©ªÁ½qoÒ^_rɧr·éú{ÌJ^®É¢ÄÌ¢íÎh½IÈðɽðo¦½ÌÉ[ðµÄ¨èA»ÌãíXÈîÉæèåw@Éiñ½Æ«A»Ì´oI½ððjÌWJð½Çé±ÆðʶÄæèm©ÈàÌƵÄ©ñÄ¢±¤Æµ½Æ«È̱ÆÄ éBv
@àÙÚ¯¶±ëAjwÈÌw¶ÆµÄú{J^®j¤ÌkíãðͶ߽ΩèÅ Á½Bµ©µAÌjwÈÉÍAJ^®jͨë©AßãjðêU·é³öÍêlàÈAµ½ªÁÄkíÆ¢ÁÄàîbIÈPû𳸯Äêéqeûr̢Ȣqkí¶rÅ Á½B»±ÅA©ªÅèÉIñ½q¼zeûrªåÍàêjÅ Á½BâgVÌwêt¾úÌú{J^®xª§s³ê½Ìª1952NÅ èA53NtÌÐïôwïÌåïe[}ªuÀJɨ¯é§vÅ Á½±Æɦ³êéæ¤ÉAÍqoÒ^_rÌ¢¤ÈêÎÅ·úÄ Á½B
@µ©µA±ÌkíͯÁµÄqeûrÌÓ©É]ÅÍÈ©Á½BÞµë_IÉÍA·Åɢ©\³êÄ¢½qoÒ^_rá»É¯´·é_ª½©Á½B½¾AÌá»Ì½ªAqoÒ^_rÌ_ÌgàÅÌá»C³ÉÆÇÜé©A³àȯêÎA±êð«íßÄêÊIÈö®ÉæÁÄ¥IÉá»·éÉIÁÄ¢½±ÆÉÍsÅ Á½Bàܽº¡Æ¯¶AqoÒ^_rá»ðuðjÌWJð½Çé±ÆðʵÄæèm©ÈàÌƵÄ©ñÄ¢±¤Æµ½vÌÅ éB
@ƱëÅAº¡Í»ÌÅÌá»ðA1958NéÉuú{ɨ¯éJsêÌWJvÆè·éCm_¶ÉÜÆßçê½B{ÉæêÎA»ÌàeͬÌæ¤ÈàÌÅ Á½Æ¢¤B
@u±±ÅÍAú´í©çêãOZNãO¼É¢½édHÆÌJsêÌWJßöðåèƵA»êð¡fIJsê©çcfIKwIJsêÖÌ]Æ»ÌAƵÄÌåéÆɨ¯éα´ðî²Æ·éqN÷Ir̬§ÆµÄc¬µ½ÌÅ éªA»Ì]ÍA{Ì~ÏÉÆàȤ¶YZpÌWÆJgÖWÌ®hÖÌÎƵĻíêÄ«½ÆèåéÆÌ·ÄÇ¿ÈJÍðmÛµæ¤Æ·éJ±ô(¾¡úÈ~ÌéÆà{¬{ÝEéÆà{Ý̱üðî²Æ·éàÌ)ªAܳɻÌ{~ÏßöÄ»íêÄéiCzÂÌ`ÔϻƻêÉÆàȤJÍÌùÖWÌ\¢IÏ»É}î³êè
µÄ¢ßöƵÄÆç¦çêé±ÆÉÈÁ½vB
@½ÌA±Ìæ¤É¢\_¶Ì_|ðÐî·é©Æ¢¦ÎAÐÆÂÉÍA±êª¢Â©Ì_ÅC³ðÁ¦çêA¸§»³êÄÍ¢éªAËRƵÄ{ÌSIȽèðȵĢéÆvíêé©çÅ èAæñÉÍA±Ì_¶ÆA1959NÉ\³ê½VqåÍà_rÆ»ÌiªµÄ¢é©çÅ éB
@æêÌ_ÍãÅÓêé±ÆɵÄA±±ÅÍæñ_É¢ÄÝĨ±¤B
ümÌæ¤ÉAåÍàÌqoÒ^_rÍÀJÌú{^Å éqoÒ^r±»ª¾¡©çæñåíãÉ¢½éÜÅÌêØÌú{ÌJâè̪êÉ èA»êðî{Iɧñ·éàÌÅ éÆ¢¤_Å Á½B»±ÅÍA¾¡©ç»ÝÉ¢½éÜÅú{ÌJâèÍî{IÉͯ¿ÌàÌÆÝȳêÄ¢½B
@ƱëªA1959Nð«ÉåÍàÌ_Íå«È]·ðÆ°é±ÆÉÈéB»ÌÅÌ_¶ªA¯N4Awú{J¦ïGxn§Ìªªð©´Á½_¶uú{IJgÖWÌÁ¿Æ»ÌÏJvÅ Á½B±Ì輪¦·æ¤ÉAåÍàÍú{ÌJgÖWªðjIÉÏ»µ½±ÆðFßéÉ¢½Á½ÌÅ éB
@Ï»ÌæúÍAå³ú©çºaúÅ èA±êð«É¡fIÈJsêÍuåéÆðSÆ·éÂÊIɽ³ê½ñöJIÈàÌÆA¬éÆðSƷ鬮IÅ¡fIÈ»êÆÌAãºÌñKwɪðµ½Bv
@ܽAu¡fIɬ®«Ì éJsêÆÑ¢½íOÌJgÍAµÄ¡úÌæ¤ÈqéÆÊrgDÅÈAÞµë¡fIgÅ Á½vBêûAíãɨ¢ÄuéÆÊgÌݪ¬³êA»êÌݪôÅ«½ÌÍAJsêªÂÊéƲÆɽ³êÄ¢½AÆ¢¤î{IÈÀÉæÁÄÌÝླêé׫±ÆÅ éBv
@åÍàÍAÈãÌæ¤ÉAqoÒ^_rÆ;ç©ÉÙÈÁ½_\¢ðàÂV_ðu éÓ¡ÅÍÌqv¢Â«rÅ èÜ·©çA³mÈhL
gÉàÆâıêðÀØ·éÆ¢¤óÔÉÜÅÍܾ©½ÜÁĨèܹñv(wJ^®j¤xæ15)Æq×ĨçêéB
@±êÍA©¯lȵɻÌÊèÅ éB½¾AâèÍ»Ìqv¢Â«rð¶ñ¾wiÅ éBâ¶ÈªçAåÍà©gͽç»Ì_É¢ÄÓêéªÈ¢B»±Å~Þð¾¸AåÍàÉãÁÄA±ÌÔÌÀÉ¢Äá±ÌRgðÁ¦Ä¨±¤B
@æPÍAqoÒ^_rÉàÆÃéÆÊg_ÉεÄü¯çê½ÅÌá»ÌÐÆÂÍAuú{ÌJgÌgD`ÔªAíOÆíãÅ¢¿¶éµ¿ª¤ÌÍAǤµÄÈÌ©ð[¾Ì¢æ¤Éð±ÆàÅ«È¢vÆ¢¤_É Á½±ÆÅ é(wêIJ^®ÌW]xAJ@¥{ñÐA1952N§ûAåFv_¶)B
@æQÍAú{ÌJsꪡfIÈàÌ©çAcfIÈJsêÉÏ»µ½Æ¢¤ÀðÅÉwEµ½Ìͺ¡Ä Á½Æ¢¤±ÆÅ éBOf̺¡ÌCm_¶ª©ê½ÌÍ1958N12Å èAåÍàªV½È_WJðæOÒÉÅÉ\¾µ½ÌÍA1959N3ÌJ^®j¤ïÌáïɨ¢ÄÅ èA_¶ÆµÄ\³ê½ÌÍA»Ì̱ÆÅ Á½B
@³çɯÁ¦êÎAº¡_¶ðNæèàæÉÇñ¾ÌÍAw±³öƵÄ_¶ÌR¸ÉÁ½åÍà»ÌlÅ Á½BO̽ßÉ¢¦ÎAÍåÍ઺¡_¶ðÞµ½ÈÇÆæw¢éÂàèÍÈ¢Bº¡_¶ÆVqåÍà_r͵įêÅÍÈ¢B»êÍAº¡ª©çÌ_¶ð½ÈµÄuJÒ^®ÌªÍð¢½ðjÖÌAv[`vÆq×Ä¢éÌÉεAVqåÍà_rÍéÆÊgðKèµ½qÏIðððjIÉÇ·é±ÆÉü¯çêÄ¢é±Æ©çà¾ç©Å éB½¾AVqåÍà_rÍA»ÌiðÈ·JsêÌðjIϻɢÄÌjÀF¯ðº¡_¶ÉÁÄ¢éÌÅÍÈ¢©Æ¢¤qv¢Â«rð·Äï¢ÌÅ éB»êÍÆà êAÌÀ¾¯ÍmFµÄ¨Kvª éB
@{Ìî{½è̢©ÉAVqåÍà_rÆ̤ʫð´¶çêA{ÌÓ`ðVqåÍà_rðÀØIÉWJµ½àÌÆ·é]¿à¶ÜêéÌÅÍÈ¢©Æl¦éBµ©µA»êÍëèÄ éB{Ìî{½èÍAº¡ÉæÁÄ·ÅÉ1958NÉAÆ©É©o³êÄ¢½ÌÅ éB
@¢ÅÉ¢¦ÎAVqåÍà_rªqoÒ^_rÆ_IÉS®µÄ¢È¢±Æ;ç©Å éÉà©©íç¸AåÍàªqoÒ^_rÉηé©Èá»Ê«Å±Ì_]·ð¨±Èíê½±ÆÍAÌ¡àÁÄ[¾µ¦È¢Æ±ëÅ éBµ©àÅßÉÈÁÄåÍàÍAqoÒ^_rͼàÅ Á½©Ì²ÆÉ¢íêA¬Ìæ¤É壳êÄ¢éB
@u^_Íqh½_rÅ éÆ¢ÁÄàA»êÍ ÜÅ»Àð©ܦéc[ÅAq^_rIÈè@à±êðêÂ̼àÆl¦êÎA½à»¤CÉ·é±ÆÍȢŵå¤B éöxÜÅA»Àð©ÞÌÉ»êªLøÅA»Àðª»êÅißÎA»êÅ¢¢ÌÅA»Àð©ÞÌÉsÖÅ Á½èðɧ½È¢Æ¢¤ÌÅ êÎA»Ì^Ì`¬Èè¼à»ÌàÌÉëèª Á½ÌÅÍ èܹñ©B»¤ÈêλÌiKÅ»Ì^ð½ÈµÌÄÄࢢv(wÐïôl\Nx343y[W)B
@µ©µAVqåÍà_r͵ÄqoÒ^_rÌëèðFßA»êÉηé½ÈƵÄñ¦³ê½ÌÅÍÈ©Á½B»ÉA©gªåÍàÉuqoÒ^_rÍ·ÅÉC³³ê½Æl¦Äæ¢Åµå¤©vÆ¿âµ½ÌÉεAÍu»¤ÅÍ èܹñvƾ¾³êÄ¢é(wJ^®j¤xæ25A13y[W)B
@àµAª»ÝÅàqoÒ^_rÍëÁĢȢÆ壳êéÌÅ êÎA»êªVqåÍà_rƵµÈ¢±Æð_Iɾç©É·×«Å ë¤BܽAqoÒ^_rÌëèðFßçêéÌÅ êÎA»ÌëÁ½_ðïÌIɦµÄ©Èỳêé׫ÅÍȩ뤩B
@Æà êAqoÒ^_rá»ðÓ}µÄðj¤É
èµA»ÌÅÌ_¶ª¢\̤¿ÉAÌåÍàªA»Ìá»_ÌS½èð©ÈÌV½È_ÌÈ©Égݱñ¾qv¢Â«rð½\³ê½±ÆÍAº¡ÉÆÁÄå«ÈVbNÅ Á½É¿ª¢È¢B±±Åº¡ÍAÓ½½ÑqVåÍà_rÉηé¢ðçêé±ÆÉÈÁ½ÌÅ éB
@qVåÍà_rÉη麡Ìá»ÍA³µÁÄÍA¼Ú»Ìû@ðâèÆ·éÌÅÈAjÀÌF¯ÉεÄü¯çê½B·Èí¿AåÍàçªuú´íãÉ»íêÄ«½SHgEÅHgEúS¸³ïÈÇð»Ì^®vzÌÝÈ縻ÀÔƵÄ༢ÌNtgEjIÉÞµ½àÌÆ·é©ðvðñ¦µ½ÌÉεAº¡Íú´íãÌú{ɨ¢ÄÍACMXÉ©çê½æ¤Èkí§xÍm§µ¦¸Aµ½ªÁÄJgªüEK§ÉæÁÄJÍ̧Àð¨±È¢¤éqÏIÈðÍÈ©Á½AÆ壵½ÌÅ éB
@±Ì½èðÅÉ_ص½ÌªA¢\Ì_¶uYÆ{iKɨ¯éíªnûJÍÌĶY\¢v(1961N10)Å Á½B
@µ©µAá»ÍÀF¯ÉÆÇÜç¸AæÉû@Éü¯çêÄ¢Á½BuJâè¤ÆåÌ«_v(wÐïôwÌî{âèxA1965NALãt§Aû)Auú{{å`ÆJgÖWv(wú{ÌJgÖWxA1967NAú{]_ЧAû)ÌQ_¶ÍAܳÉåÍà_Ìû@Iá»ðåèÆ·éàÌÅ Á½B»±ÅÌSIÈ__ÍAåÍà_É ÁÄÍAuJÒåÌ̬§_@vð³µÊuïĢȢƢ¤É Á½B
@ƱëÅA±Ìæ¤ÈåÍà_Éηéû@IÈá»ÍAKRIɺ¡©gÌû@ÉηéÄ¢ðéàÌÅ Á½B{Ìu͵ª«vð©êÎA»ê;ç©Å éBâè̪𲫫µÄ¨±¤B
@PD@Cm_¶É¢ÄB@@u»Ì]èÉàVF}eBbV
Èc¬ÆA³çÉÍðjßöÉoê·éåÌAÆèí¯æÌ_¶É¦µÄ¢¦ÎAJ±ôÌÎÉðȷ͸ÌJÒ^®ÌªÍð¢½ðjÖÌAv[`ÌpÌÀE«v
@QD@uYÆ{iKɨ¯éíªnûJÍÌĶY\¢vÉεÄB@@u»ÌîêÒ³IÈpÌÀEBccåÌIÈJÎRÌÔlª¢íÎqÌIÈJÍæøÌ\¢ÉæÁÄK§³êé¤ÊÉå½éÖS(ð¨)ìÌ·³ccX^eBbNÈ\¢ªÍÆ¢¤`ðÆÁÄ¢½ã³v
@ÈãÌæ¤È½ÈÌãɧÁÄÜÆßçê½ÌªuæêåíãÌJÖWv(woÏw_Wxæ30ªæ4Aæ31ªæ1A1965N)Å èAuYÆ{iKɨ¯énûJÍÌĶY\¢vÌêðüeµ½uSHg̬§Æ»Ìöóv(woÏw_Wxæ31ªæ4Aæ32ªæ2A3)Å Á½B
@ÈãAu͵ª«vð誩èÉA{̬§É¢½éº¡Ì¤Ì ÆðHÁÄ«½BȺÅÍA{Ì\¬ÆàeðÐîµAá±Ì¢ð±±ëݽ¢B
@Q@{Ì\¬Æàe
{Ì\¬ÍÌƨèÅ éB
@Í@@åèÆû@
@æPÍ@ÔÚÇ̧̬§Æ»ÌÏe
@æQÍ@¼ÚIÇ̧ÖÌ]·ÆéÆà{ÝÌWJ
@æRÍ@¼ÚIÇ̧̻ÆHêÏõï§x̬§
@ÍÌæRßÍARc·¾YAåÍàêjA÷JOìjÌOÌJÖWÌc¬Éηéá»ð¨±ÈÁ½uú{{å`ÆJgÖWv(Of)ðÙÚ»ÌÜÜû^µ½àÌBæPÍÍOfÌuSHg̬§ÆöóvðAæRÍÍA¯¶uæêåíãÌJÖWvðAÆàÉ\¬ðgÝ©¦AåÉÁMÌãûß½àÌÅ éBÍÌPAQßA¨æÑæQÍÍVeÅ éB
@ܸAÍÌæPßÍuÎÛIðÆ»ÌÓ¡vÆèµÄA{ª»ÌªÍÌÎÛðudHÆåocÌJÖWA»êàÙÚêªãZN©çêãOZNÉ¢½élZNÔÌðjIWJÌßövÉÀèµ½±ÆÌÓ¡ªÌ×çêÄ¢éB
æQßÍuåèÆû@vÅA±±Éº¡Ì»_ɨ¯éâèÓ¯ªWñIÉÌ×çêÄ¢éBÆèí¯A¬Ìê¶Å éB
@uíêíêªA{å`Ì»ÀIðjßö̤¿ÉWJ·éJÖW̪Íɧ¿ü©¤Æ·êÎA{å`ªJÍ̤i»ðîbƵÄlÔÌÚIÓ¯IȮƵÄÌJßöð{̶YßöƵÄïÛ·éàÌÅ èȪçàA»êðoÏIÉ͵ª½¢_@ðàï·é±ÆÉεÄA»êÍAðjIèÝ»ê©ÌɦµÄA±ÌðjßöÌå®Í½é{ÆÌs®Æ»êðx¦éO¨æÑ»êÉKè³êÂÂÎRIÈåÌƵĻêéJÒÌs®ÆA»êðx¦éOɦµÄ¼ÒÌðjIÔlð¾ç©É·é±ÆAµ©àA±Ì¼ÒÌÎRÖWªA{Ì^®ÉæÁÄK§³êȪçàA¯É»êÉæÁÄ͵ª½¢àÌƵÄAÆÌôIîüð}îƵÂÂðjIÉ]·élð¾ç©É·éàÌÅȯêÎÈçȢŠë¤v(ºüøpÒ)B
@¢ÅAEÌâèӯɦµÄ{ÌÛèªÌæ¤Éñ¦³êéB
uÙÚêªãN©çêãONÉ¢½édHÆåocÌWJßöðÎÛƵÄA{ÌS¢èªHê§xÌBÉεÂÂÇÌæ¤È¶Yßöɨ¯éxzÌÌnð¶ÝoµÄé©A»ÌxzÌÌnÌÈ©©çÇÌæ¤ÈJÒÌÎRª¶Ýo³êÄé©A±Ì_ɦµÄ¼ÒÌÎRÌðjIÔlð¾ç©É·é±ÆA»µÄA±Ì¼ÒÌÎRÖWªA{Ì^®Aí¯ÄàJÖWðïÛ·éJsêÌ^®ÉæÁÄÇÌæ¤ÉK§³êé©A³çÉÍA±ÌK§ÉæÁÄ൪½¢µªAÆÌôIîüð}îƵÂÂAÇÌæ¤ÉA¢©Èéӡųê½Ì©AÙÚ±Ìæ¤È_©ç»ÌJÖWÌWJÌlð¾·é±ÆÉ év
@v·éÉAº¡ÍJÖWÌðjIWJðc¬·éÌÉA(1)¶Yßöɨ¯éxzÌÌnA(2)JÒÌÎRA(3)ÎRðK§·é{Ì^®AÆèí¯JsêÌ^®A(4)ÆÌôIîüAÈãSÂ̤ÊÉ¢ÄAv[`·éû@ðÆë¤Æ¢¤ÌÅ éB½¾µA{ÅÍ(4)É¢ÄÍA«íßÄÀçê½ÇÊÉ¢ÄÌÝÓêçêé±ÆªA¬Ìæ¤ÉfçêÄ¢éB
@u{ÍJÖWªÆÌJô̤¿É³êéßö»ê©ÌðªÍÌÎÛÆ·éàÌÅÍÈ¢ccccA{ɨ¢ÄÆÌJôɾy·éêÉàA»êÍAdHÆåocÌJÖWÌWJªÆÌôIîüðÄÑN·ÇÌæ¤È_@ðàïµÄ¢é©A»µÄܽ»ÌÆÌôIîüÉæÁÄdHÆåocÌJgÖWªtÉ¢©ÈéK§ðó¯é©AÆ¢¤ÇÊɾ¯Àè³êÄ¢év
@±±ÅA æPÍȺÌÀؤÉ¢ĩæ¤BÀçê½Å»ÌLxÈàeðÐî·é±ÆÍeÕÅÍÈ¢ÌÅAÊÉf°é\¬\ÉæÁÄ{ÌSÌð©ñÅ¢½¾«½¢BæªApêÈÇÅ«éÀèÒÌp@ð¸dµ½ÂàèÅÍ éªAÁLÌTdȯÛðµ½\»ðèÉ®µ½àÌàÈÈ¢B±Ì\É¢ÄÌÓCÍARAÉ éBȨ±Ì\ɦµ¦È©Á½±Æª¢Â© éB»ÌæPÍAJÖWÌWJÌ®öÅ éBÏ»ðKèµ½åÈvöÍAeúÆà{~ÏÌisÅ éªAJÍÌ¿ðAµ½ªÁÄZ\{¬§xðA³çÉÇ@\âÀà\¢Ée¿ðyڵĢÖWª¾É ÆïçêÄ¢éB¼ûAJ^®ÌWJàIÈ®öƵÄÊuïçêÄ¢éBúIíãÌåcð_@ÉéÆà{ݪ±ü³êA é¢ÍæêåíãÌJg^®ÌgÖÌÎƵÄHêÏõ離±ü³êé±ÆÈǪ»êÅ éB
@±Ì\¬\ɵĢéæQÌ_ÍAocÌJ±ô̤¿AEêÇEÀàÇÈOÌàÌÅ éB½Æ¦ÎAJsêÎôƵÄÌèúEH§âtÁtÈÇA³çÉÍuå]ÌîbvÆocÆ°å`ÈÇocÌOÉ©©íéàÌÅ éBæê_ÌêÍAì\ÌZpãÌ¢ïÉæéƱëªå«¢ªAæñ_É¢ÄÍAº¡Ì¤ãÌÉæéƱëàÈ¢ÆÍ¢¦È¢B½Æ¦ÎAeúɨ¯éocOÌÏ»( é¢Íp³)ÍK¸µà¾ç©ÅÍÈ¢B
@ȨAúæªÉ¢Äàá±Ìâèª éB·Èí¿AæSúÌu¼ÚIÇ̧̻ÆHêÏõï§Ì¬§vúÍA¨»ç1920NOãÅñªµ½ûªº¡Ì_|Éàv·éÌŠ뤪A»Ì_{ÅÍK¸µà¾ÄÅÈ¢ÌÅA\ÅÍ{Ì;ÄÉ]Á½B
@Æà êA±Ìæ¤ÉeÚÉ¢ÄÌÚ×ÈàeðàÂ\¬\Ì쬪Â\Å éƱëÉ{Ìbgª é±Æͽµ©Å éBÆèí¯A¶YßöÌÏ»ÉÆàȤJÍÌ¿IÈÏ»AZ\{¬§xAÀà\¢AÇ@\ÈÇ̪ÍÍ]̤
ðÍé©É±¦Ä¢éBZ\{¬§xÌÚAéÆà{ÝÌÀÔÆ»ÌÁ¿AÀà\¢ÌÏ»ÈÇA{ÉæÁÄͶßľç©É³ê½à̪ÈÈ¢B
R@ñAOÌâè_
@ÅãÉAÈPÉñAOÌâè_É¢ÄÌ×Äݽ¢B
@»ÌæêÍAúæªÆ¢¤æèAeúÌKèÉ©©íéâèÅ éBeÍÌW誦·æ¤ÉAº¡ÍÔÚIÇ̧ƼÚIÇ̧Ƣ¤KèÉæÁÄeiKðÁ¥Ã¯Ä¨çêéB¨»çA±êͺ¡ª¶Yßöɨ¯éxz`ÔÌÏ»ðd³ê½½ßÄ ë¤ªAÉÍA±ÌKèÍKØÆÍv¦È¢B½ÌÈçu¼ÚIÇ̧vÍ1930NÅIéÌÅÍÈA»ÌãàA»ÝÉ¢½éÜÅKpÂ\ÈTOŠ뤩çBܽA±ÌKèðp¢é±ÆÍAÔÚIÇ̧©ç¼ÚIÇ̧É]»µ½ú´íÆúIíÌÔÉÌÝA±Ì40NÔɨ¯éåæúª éÆÌóÛðð¯ï¢©çB
@æñÌâèÍA{ÌuåèÆû@vÆÀØIÈðjªÍÆÌsêvÅ éBuåèÆû@vŲ³êéÌÍAu{å`Ìðjßöð¤i`ÔÉæéK§ð¤¯ÂÂWJ·éåÌÆqÌÌðÝìpÌ_Bi~NXƵÄc¬µæ¤Æ·év§êÅ éB½µ©ÉqoÒ^_rÈÇÆÍ¿ªÁÄA±±ÅÍåÌÆqÌÍÝÉìp·éàÌƵÄ`©êÄ¢éBµ©µA»ÌÖWÍ^®ÌƵÄÌ_Ci~NXð¢Ä¢éæ¤ÉvíêéB
@»êÍAº¡ªJÖWÌWJðc¬·éÌÉAåƵĶYßöɨ¯éxz`ÔÌϻ̤ʩçAv[`µAJ^®É¢ÄAÆ©ÌǪ[ªÅÈ¢±ÆÉæéàÌÆvíêéB·Èí¿A¾¡úÉ¢Ģ¦Îukí§xªm§µÈ©Á½íªÅÍAJgªüEK§ÉæéJÍ̧Àð¨±È¤ðÍÈ©Á½vÆ¢¤VF[}Åíè«Á½´ª¢B»êÅàAܾ¾¡úÉ¢ÄÍAº¡ÌªÍÍJ^®ÌWJðÙÚJo[µÄ¢éB
@SHgÉ¢Ä̤ÍAº¡Éηé«Ñµ¢á»ÒÅ ércM̤(wú{@BHg¬§j_x1970NAú{]_Ч)ÆÈçñÅ]̤ðå«Oi³¹½àÌÅ éB
@µ©µAæêåíÈãÉÈéÆAº¡ÌJ^®Ìc¬ÍA©ÈèêÊIÅ éB·Èí¿1910NãÌ^®ÍåƵÄF¤ïÌEÆÊgå`©çYÆÊgå`ÖÌûü]·ÆµÄc¬³êA»±©ç¼¿ÉA1921NÌcÌð l¾^®ÖÆÚ±³êÄ¢éB¾ªµ©µAdHÆåocɨ¯éJÖWÌWJðc¬·éÆ¢¤{ÌÛè©ç·êÎA±±É͢©ÌdvȪ éæ¤ÉvíêéB
½Æ¦Î1919Nðs[NÆ·éJgÌ®¬Å èAg¬Æ§ÚÉÑ¢½åc̱ŠéB¢¸êàACºH±AÎì¢DAåãSHAìè¢DAóì¢DAª¦»SÈÇÌdHÆåocÉWµÄ¢éBJ^®Ì¤Ê©çÝêÎA¾ç©ÉV½ÈiKðæ·éàÌÅ Á½B
@±ÌÍôRÅÍÈ¢æ¤ÉvíêéB±±ÅàAº¡ÍêèÌVF[}ÉæÁÄ^®ðc¬³êÄ¢é©çÅ éB
»ÌVF[}ÍA¾¡úÌ»êÆ_IɯêÅ éB·Èí¿Aú{ÅÍAàÆàÆgªüEK§ÉæÁÄJððK§·éðð¢Ä¢½ãÉAocª¶Yßöð¼ÚÉÇ·ȩ́𻵽½ßAJÒWcª©¥IÉJððK§·é±ÆªXÉ¢ïÅ Á½Bu±¤µ½óµÌàÆÅÍAJgƵÄJðÌK§ÉÖ^µæ¤Æ·êÎAEêÇÒÌ@\ðcÌðÂðʶÄK§·éÈOÉÍ»Ìû@Í è¦È¢vÆ¢¤ÌÅ éB
@©Äº¡ÍAcÌð l¾^®ÉæêåíÈãÌ^®Ì·×ÄðûÊ·é±ÆÉÈéB»µÄAcÌð l¾^®ÌskãAJgÍåoc©çÍSÁ¸µÄµÜÁ½©Ì@Å éB
@¾ªA±êàAÀɽ·éBêáð °êÎ]cïÖn]ÌåÍÍÎì¢DÉ Á½BPÈéHêÏõï§xÅÍÈAãÌYñ^®ÌæìÆÈéuú{å`J^®vªÎì©®gðSÉWJ³ê½ÌàAܳÉA»êÉæ¾ÁÄÎìɶJgª¶ÝµÄ¢½ÀÆ©©íÁÄ¢½B
@±ÌÙ©Aܾá±Ì^âà èAsà éBµ©µA»Ì½ÍA·ÅÉÒ©gA[ª©o³êÄ¢éæ¤ÉvíêéBu_ª[ªÉ¬nµÄ¢È¢Æ¢¤©ov©ç{ðuÜÆßé±ÆðfOµæ¤©Æ¢¤UfÉÆè©êÄ«½vÆÌq͵ª«rÅÌÉA»êͤ©ª¦éB¨»çÍA{Ì__̢©ÍA¡ã̤ÌÈ©ÅÄ¢³êAù³³êé±ÆÉÈéÅ ë¤Bµ©µA{ª1960Nãɨ¯éú{Jâè¤ÌB_ð¦·ã\IÈìiÅ èA¡ãAú{ÌJâè¤ðu·ÒÉÆÁÄKÇ̶£ÆµÄA·¢¶½ðÛŠ뤱ÆÍ^¢È¢B
º¡@釗 wú{ɨ¯éJÖWÌWJx
åwoÅïA1971N2§sA479Å
ko@ÍuêãZZNãɨ¯éú{Jâè¤ÌB_º¡釗wú{ɨ¯éJÖWÌWJxÉñ¹ÄvÌ´èÅAwG§J@xæ80A1971N6ÉfÚl
|