高野房太郎とその時代(二三)
ニューヨーク号の船旅
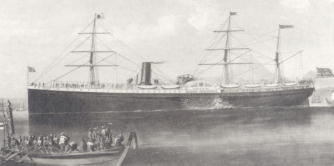
明治一九(一八八六)年一二月二日午前一〇時、あと一ヵ月で満一八歳になる高野房太郎を乗せたザ・シティ・オブ・ニューヨークは、晴天の横浜港を出航しました。母や弟、講学会の友人ら多数が見送るなかでの門出でした。ただ、当時の横浜港には大型船が接岸できる岸壁はなく、乗客は
ちなみに、房太郎が横浜を出航したこの日は、アメリカ労働総同盟が組合員一五万人で発足したまさにその日です。後年、彼はこの組織の代表として日本で活動することになるのですが、もちろんこの時は、その存在を知る由もありませんでした。
ニューヨーク号は、アメリカの太平洋郵便汽船会社(the Pacific Mail Steamship Company)の客船で、香港始発、横浜を経由してサンフランシスコに向かう定期便でした。とうぜん香港からの先客がありました。アメリカへ出稼ぎに向かう中国人労働者が乗り込んでいたのです。一八八二年に中国人排斥法が成立していたので、最盛期のように中国人労働者がすし詰め状態といったことはなくなっていましたが、それでも在米家族が呼び寄せる形をとったり、香港で英国籍を取得するなどの抜け道をつかって、どの便にも数百の中国人が乗っていたといいます*1。もっとも、この日の便は、年末が近かったこともあってか、中国人乗客は七五人だけでした。
この日、房太郎といっしょにニューヨーク号に乗り込んだ日本人乗客は彼をふくめ一〇人、そのなかに房太郎とほぼ同年の
明治一九年一二月二日午前一〇時、平野、水島、松本、山口、青木、瀬戸、岡、深沢の諸兄と姉上と別れを告げました。白帆が東風を受けて、船は矢のごとく走り、観音崎は寸時に過ぎ去り、はるかに緑の房総の山々が、私の洋行を喜んでくれているかのようでした。同船の日本人は九人でした。第一日はみな甲板を歩き回り、東を見たり西を眺めるなどして過ぎ去りました。二日目は晴でしたが、午后三時頃から西北の風が烈しく吹きつけ船体は大きく揺れました。三日目も晴天でしたが、風の勢いは前日と変わらず、このため同船の日本人の半ば以上が船酔いにかかりました。私もめまいがしたので、高幡老獅坐からいただいた感応丸を飲み、そのおかげで無事に過ごすことができました。同船者にも分けてあげ、みな気分がよくなったようです。
三週間近く、来る日も来る日も見えるものは波ばかりという船旅が、ほとんど耐え難いほど退屈なものであることは、永井荷風が『あめりか物語』の冒頭の「
出帆した日、故国の山影に別れたなら、もうそれが最後、船客は彼岸の大陸に達するその日までは、半月あまりの間、決して一ツの島、一ツの山をも見る事は出来ない。昨日も海、今日も海──いつ見ても変らぬ太平洋の眺望というのは、ただ茫漠として、大きな波浪の起伏する辺に、翼の長い、くちばしの曲った信天翁 の飛び廻っているばかりである。その上にも天気は次第に北の方へと進むに連れて、心地よく晴れ渡る事は稀になり、まず毎日のように空は暗澹たる鼠色の雲に覆い尽さるるのみか、ややもすれば雨か霧になってしまうのだ。
もっとも、永井荷風が描いているのはシアトル航路でしたから、房太郎の乗ったサンフランシスコ便は、天気の面ではいくらか恵まれていたようです。
もう一度、石坂の手紙に戻りましょう。
四日目になると風の勢も衰えました。五日目は晴で、同船者のなかには、自分の経歴などを話す者もおりました。彼らの多くが横浜に住んでいたこともあって、おおかたの話は横浜の人物についての評判で、誰それの貧富、誰それの美醜といったものでした。私が持参した食品はこの五日目ですべてなくなってしまいました。蜜柑一箱は二日間で食べ尽くし、コンデンスミルク一缶は一時間でなくなってしまいました。同船の人びとは、お互がもってきた食料を分け合って食べました。
六日目は南風が吹き荒れ、今度の航海中ではもっとも激しかったのですが、私は何ともなく一日中甲板を歩き回りました。七日目は寒気が甚しく、一日中部屋に閉じ籠もって横になっていました。私たちの部屋は定員が九人でした。中国人の部屋は船の最下層にあり、通風がよくありません。この船には中国人七五人が乗っていました。私たちの部屋は船の中層にありました。これは船の客室係に一人五ドルずつの賄賂を出したからだとのことでした。日本人室はヨーロッパ人の下等室の隣にあります。上等室も同じように船の中層にありました。上等の船客は三人だとのことです。この船の船長ハ「サアー」いう名で、二五〇ドルの月給をとっているそうです。水夫のなかで最も下等の者の月給は一五ドルで、乗組員は総員一〇六人です。
船室についての、この公歴の手紙にはちょっと説明が必要です。パシフィック・メールの定期船は、帆と蒸気機関で走る機帆船で、船体は四層からなっていました。最上層には一等船室と船長など高級船員の部屋、第二層は二等船室と一般船員の部屋、第三層に三等船室があり、最下層は荷物室でした。ここでは便宜上、一等、二等、三等としましたが、実際に使われていた言葉は、二等は〈ヨーロッパ人普通船室〉(European steerage)、三等は〈中国人普通船室〉(Chinese steerage)でした。三等船室は大部屋で、竹で編んだ幅六〇センチ長さ二メートル七〇センチの
日本人客の多くは二五〇ドルもする一等はもちろん、八五ドルの二等も買えませんでしたから、ほとんどが三等船客でした。しかし彼らが、実際に入れられたのは第三層の大部屋ではなく、第二層の二等船室でした。客室係に五ドルの割り増しを払うとグレードアップしてくれたのです。というより、一般に日本人乗客は最初から中等船室に入れ、割り増しを払わなければ下等船室に移れというやり方がとられていたようです。二等の正規運賃は払えなくても、五ドルの割り増しで二等船室に入れるならと、ほとんどの日本人客はこちらを選んだようです。船会社は少しでも多くの収入を得ようと、こうした運賃政策をとったのでしょう*5。
また、石坂の手紙に戻りましょう。
八日目晴天。此日は東西半球の変わり目を通るので、明日もまた一二月九日になるとのことでした。親切な水夫がわざわざ来て、今午后一〇時三〇分(日本時間で午前八時)がその切り替え時だと教えてくれました。私にはなぜそうなるか分からず、同船の人びとはくちぐちに自分の推測を述べていました。此日、船医が来て種痘をしました。同船の日本人のなかには医者がいて、これは昔のオランダ式の種痘だと言っていました。そのやり方はメスで皮膚を切り、ゴムの中へ種が入っている象牙の小片でその切り口をこするものでした。
九日目、曇り後雨。一〇日目、同船の日本人が互いにその名を手帳に書き記しました。銀行の役員二人(横浜茂木銀行の社長)、医学生二人、うち一人は都築郡川井村の足立良弼といい、横浜の近藤医師に学んだとのこと。もう一人は紀州有田郡の人で、田舎で医者を開業していた人。川越町ノ書生一人、北埼玉持田村石久保ト云フ書生一人、横浜の職人一人、横浜講学会の発起人である書生一人〔これが高野房太郎──引用者注〕、東京紙屋の小僧一人、それに私をふくめ一〇人です。おたがいに将来の希望を語り、過去の楽しかった体験を話すのを聞いて、驚きました。「東洋航海ノ客窃花人又避漢人」という詩をつくりました。
一一日目、昨夜は雹 が降りました。その大きさは豆ほどもありました。夜にもまた降りましたが五分ほどで止みました。この夜、たわむれに同船した人びとの未来を予想し、皆で笑いあいました。ある人にその未来を訊ねると、数万金を得た後はナイヤガラの滝のかたわらに別荘をつくるつもりだと答えたので、以後この人は〈ナイヤガラ〉とあだ名されました。あるいは〈藪医のてんぷら〉といったあだ名をつけられた人もいます。話すことがなくなると、毎晩昔のかってきままな楽しみは良かったなどという話になります。ずいぶんきわどい話にもなりますが、そばに日本語が分かる人がいないので、皆安心して喋っている様子でした。
一二日目はきびしい寒さでした。この夜からトランプで遊びを始め、負けた者は罰として一〇銭だすことになりました。到着の前夜まで、毎晩トランプ会を開き、私も仲間に入って五〇銭の罰金を払いました。多い人で八〇銭、少い人でも三〇銭は出したでしょう。この頃までには皆が持参してきた食品はなくなっていましたので、この罰金でコーヒーやビーフテキを買い、争って食べました。私は、前々から銀行の役員がこれを試みていることを聞き、それを真似て中国人のコックに一〇銭を払うと、コーヒーとパンが手にはいるので、毎日これを試み、航海中、食べ物で困ることは少しもありませんでした。初めのうちは、乗客にでる定食を食べる者は一人もいませんでしたが、最後には食べるようになりました。
一三日目、朝雹が降りましたが寒くはありませんでした。一四日目は晴、一五日目は曇、一六日目は快晴でした。一七日目の朝は雨でしたが昼には晴れ、夜は曇りました。この航海中で、こうした日が普通でした。此日、水夫等は船を綺麗に掃除しました。一八日目はいよいよ到着の日で、皆上陸の準備をしました。同日午后四時二〇分、ゴールデンゲートを通過し、夕方サンフランシスコに到着しました。目に見える景色すべてが限りない喜びを感じさせてくれました。
一八八六(明治一九)年一二月一九日夕方、ザ・シティ・オブ・ニューヨークは一九日間の船旅を終え、サンフランシスコ港に入りました。港は、周囲を陸地に囲まれ、ほとんど湖のようなサンフランシスコ湾内にありました。太平洋から湾への出入りに通る狭い水路が有名なゴールデン・ゲイト、黄金の門でした。いかにもゴールドラッシュで急激な発展をとげた町・サンフランシスコへの入り口にふさわしい名というべきでしょう。横浜乗船の際には艀で沖に停泊している船まで運ばれましたが、ここサンフランシスコ港では大きな汽船も埠頭に横付けされ、乗客は直接新大陸の大地へ第一歩を踏み出すことができたのでした。房太郎はもちろん、乗客のほとんどにとっても、これが生まれて初めて見る外国の土地でした。
【注】
*1 パシフィック・メール会社の太平洋横断の船旅の状況は、米国桑港寓周遊散人原著・東京石田隈治郎編輯『来たれ日本人──別名桑港旅案内』、東京開新堂、明治一九年一二月刊)に詳しい。なお、ここでは『日系移民資料集』北米編、第五巻〈渡米案内〉(一)(日本図書センター、一九九一年一二月刊)によった。なお、同書の筆者〈周遊散人〉は『中央学術雑誌』一九号の「記事欄」に掲載された「茨木宗太郎君書翰」の筆者である可能性が高い。茨木は東京専門学校の卒業生で、書簡は一八八五(明治一八)年一〇月四日に横浜を出航したリオデジャネイロ号で渡米した際の体験を記したものである。この書簡の内容と前掲書の記述は、細部にわたって共通するところが多い。
*2 石坂公歴は渡米後半世紀たってからも、高野房太郎と同船してアメリカに渡ったことを記憶しており、一九三九年に「在米日本人事績保存会」のアンケートのなかで、その事実を記している(色川大吉編『三多摩自由民権史料集』下巻、大和書房、一九七九年、九七九ページ)。同船した日本人の数を五人とするなど、本文で引用した手紙の内容とくらべると不正確なところがある。それだけに、同船者として高野房太郎の名を記憶し、その実弟が高野岩三郎であることまで知っていたことは、高野房太郎が在米日本人の間でも注目される存在であったことをうかがわせる。石坂公歴については、色川大吉『新版 明治精神史』(中央公論社、一九七三年)、とくに第一部三「自由民権の地下水を汲むもの」、同六「放浪のナショナリズム──石坂公歴」を参照。
*3 ここに現代語訳した書簡の原文は、鶴巻孝雄研究室にある北村透谷研究 ――参考 石阪昌孝・公歴父子研究に、石坂公歴のアメリカ便りの最初に収められている。
*4 永井荷風『あめりか物語』(岩波文庫、二〇〇二年)一一ページ。
*5 米国桑港寓周遊散人原著・東京石田隈治郎編輯『来たれ日本人──別名桑港旅案内』、東京開新堂、明治一九年一二月刊)五九〜六一ページ参照。