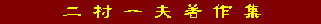二 村 一 夫
明治40年の足尾暴動について
はじめに
ただいま村上安正さんから永岡鶴蔵や南助松らの活動について詳しいお話しがありましたが、私はこの暴動の基盤といいますか、なぜこの時期にあのように鉱山において運動が高揚したのかについて問題にしたいと思います。はじめに問題の手がかりを得るために、これまでの研究が足尾暴動をはじめとする一連の鉱山暴動をどのように規定しているかをみておきます。
まず大河内一男先生ですが『黎明期の日本労働運動』のなかで次のように述べられています*1。
「〔足尾暴動の〕特徴は苛烈な原生的労働関係と奴隷制的飯場制度の強度な支配とは、労働組合の力をもってしてはコントロールできない暴動を惹き起こすという点」にある。さらに「各種の炭坑のほかとくに銅山におけるストが際立ってて多く大規模であるのは、激しい軍事的需要と鉱山における封建的圧制との二重の桎梏に対する労働者の反発の結果であろう。」
また岸本英太郎氏はつぎのように主張されています*2。
「明治四十年には戦後恐慌が勃発し、多くの失業者を出し、労働者階級の窮乏が著しく、労働者は激しい弾圧のもとに相踵いで自然発生的なストライキに立上がったのである。」
「三十年代末から四十年、四十一年に亙るストライキの頻発は、原生的労働関係に対する労働者の自然発生的抗争であり、自覚し組織化された労働者のストライキでは決してなかったのである。」
以上の規定のうち、「軍事的需要」や「戦後恐慌」との関連を主張されているところは明らかな誤りだと思いますが、時間も限られていますので、ここではふれずにおきます*3。
私が主として問題にしたいのは、大河内・岸本両氏に共通しており、現在ではほぼ通説化している見解、すなわち暴動やストライキの主たる原因は苛烈な原生的労働関係と奴隷制的飯場制度の強度な支配にある、とされていることについてです。たしかに飯場制度は労働者を非常に悲惨な状態に陥れていましたし、それが反抗の大きな原因であったことは事実です。しかしここで考えなければならないのは、飯場制度は本来、労働者の反抗を規制し抑圧することをその主たる機能のひとつとしている組織であることです。もしこれが言われるごとく〈強度な支配力〉を有していたなら、労働者の状態がいかにも窮迫していても、彼らは反抗には立ち上がれなかったのではないでしょうか。少なくとも暴動とか公然たる反抗という形をとる可能性はあまりないと思われます。
だとすれば、暴動は大河内氏らの言われるごとく「飯場制度の強度な支配」によるものではなく、むしろ逆に「飯場制度の弱化」によるものと仮定しうるのではないでしょうか。足尾暴動の経過をみると、この推論はいちおう当たっているようです。いわゆる足尾暴動そのものは
、ひごろ賃金決定の不公正などで労働者のうらみを買っていた現場係員をはじめ鉱業所長にいたるまでの職員に対する復讐的制裁であり、まったくの本能的反抗でした*4。しかし注目すべきことは、その前に、永岡鶴蔵、南助松らの指導のもとに友子同盟*5の幹部=山中委員を中心として、公然と飯場頭の中間搾取を制限しようとした組織的な運動があり、暴動直前にはいちおうこれに成功していたことです。暴動そのものは、この敗北によってピンチに追い込まれた飯場頭が至誠会をつぶすために挑発した疑いが濃厚です。このように一般の坑夫が飯場頭に対して集団的に公然と反抗することが出来て、しかも一時的にせよそれに成功していたことは、この時期における飯場頭の支配力が決して強固なものでなかったことを示しています。したがってこの問題を解くためには、これまでのように飯場制度イコール「身分的圧制」とか「原生的労働関係」と規定するだけでは不十分で、飯場制度そのものの変化が歴史的に追究されなければなりません。こうした作業を通して、それぞれの時期の運動の歴史的な質の相違を明らかにすることも可能になると考えます
飯場制度の史的変化
飯場制度の原型というか、その前段階の労働組織は「山師制」とも言うべきものです。いうまでもなく明治維新前において鉱山はすべて封建領主の領有するところであり、直山の場合には代官がおかれ、請山の場合には銅商等の商業資本が請け主としてに経営にあたりました。しかしいずれの場合でも代官や請け主が直接生産に関与することはほとんどなく、実際に生産面を握っていたのは、いわゆる「山師」でした。彼らは各々1カ所から数カ所の坑についてその操業を請け負い、自らそれに必要な生産手段を所有し、坑夫、手子、製煉夫などを雇い、採鉱から製煉にいたるまですべての作業をまったく自己の採算と責任において行いました。
このような形態は、何よりも当時の生産力の低さに規定されたものでした。当時の採鉱法はすでに水平坑道による「坑道掘進法」をとっていましたが、排水、通風の困難から深部採鉱は不可能で、地表近くの富鉱部を採掘し得ただけでした。ですから、ひとつの鉱脈を採掘する場合でも、地表の各所から多数の坑口を切りあけて進むほかはなく、一鉱山といっても実際は多数の相互に独立した坑の集合体にしか過ぎませんでした。したがって、代官にせよ請主にせよ、自ら生産過程を掌握して統一的な経営を行うことは困難でした。そこでいきおい彼らは山を各坑ごとに分割して「山師」に請け負わせ、産出物を流通面において掌握する方向をとったわけです。
しかし、地表近くの富鉱部はごく僅かなものですから、この「山師制」による小規模分散経営ではすぐに限界に突き当たらざるをえませんでした。17世紀の中期以降、日本の金銀山が一般的に衰退して行ったのは明らかにこのことを示しています。このような状態は徳川時代を通じて、一部の大鉱山を除き基本的には変化せず、その克服は明治にはいってからの西欧近代技術の導入をまたねばなりませんでした。
明治10年に古河が経営を握った当時の足尾銅山もまさにこの「山師制」の段階にありました。このことは『古河市兵衛翁伝』(五日会編発行、1926年)のつぎのような記述からみて明らかです。
「引継当時の採鉱箇所は如何なる状況であつたかと云ふに、鉱脈露頭より掘込んだ坑口貳百五十余を算したが、現に採掘しつゝあった稼ぎ場所は七十四ヶ所であって、それが三十八人の下稼人によつて個々別々に操業されて居た。」(同書108ページ)
「当時の足尾は下稼人の足尾であつて、坑主は唯彼等に米噌を給し出銅を買上ぐる金主たるに過ぎなかった。」(同書119ページ)
ところで、このような「山師制」による小規模分散経営では、長年にわたって衰退の原因となっていた排水問題を解決して、生産の拡大を行うことは不可能でした。この状態を根本的に解決するには、何よりまず通洞、竪坑を開鑿し、排水・運搬を機械化することが必要でした。そのための技術的条件は、すでに官営鉱山を中心に西欧の近代技術を移植することで準備されていました。しかし、この鉱業技術の近代化を遂行するはためには、下稼人=「山師」の坑に対する稼行権というか実質的な所有権を奪って、鉱業主が直接生産過程をも掌握し、全山を統一的開坑計画のもとに組み入れることが先決問題でした。この山師の稼行権の剥奪は、官営鉱山では国家権力の強権によって強行されきわめて短期間になしとげられたところでした*6。
しかし一般の民営鉱山ではこのようなことは不可能で、足尾においても直轄坑の開削、山師の「所有」坑の買収などによってじょじょに行われ、明治14、15年頃にようやく一応の完了をみました。こうして、ひとたびこの経営統一に成功するや、明治19年〜29年の大通洞の開鑿、明治22年の我が国最初の水力発電所などを初めとして排水、運搬、製銅の各部門において目覚ましい近代技術の採用が行われていったのです。
そこで次にとうぜん問題になるのは、これによって「山師制」がどのように変化したかということです。これを解明できるだけの史料が現存していないので、はっきりしない点はありますが、少なくとも下稼人は完全に追放されたわけではなく、一時的、局部的には作業を請け負うものとして古河資本に包摂されたことは明らかです。ここでは、下稼人はもはや生産手段の所有者ではなく、資本家と労働者の間に介在する中間搾取者に過ぎません。しかし彼らは依然として自ら労働者を募集し、請け負った作業を配下の鉱夫に割り当ててその監督をおこない、賃金を一括して受け取り、これを配分しました。これがまさに典型的な飯場制度です。ところでこの場合、本質的に労働者の雇い主であるのは、すでに主要な生産手段を所有し操業全体を基本的に管理していた鉱業主、つまり古河家でした。しかし当事者の意識の上では、中間搾取者である飯場頭が労働者の雇用主であるかのごとく現象したことが注目さるべきです。というのは、飯場
頭の支配力の基礎は、通常考えられているようなリンチなどの直接的暴力のみにによるものではなく、むしろ基本的には飯場頭が雇用、解雇、賃金決定、賃金支払いなどの実権を握り、現象的には労働者の雇用主として存在したことにあると考えられるからです。
飯場制度存続の根拠
さて、ここで当然つぎのようなことが問題にされなければなりません。それは、近代的資本制産業の内部に、なぜこのような前近代的な労働組織が存続したのかということです。
ご承知のように大河内一男先生は、これを1)出稼型労働者の前近代的エートス、2)統一的労働市場欠如による縁故募集の存続、によって説明されています。この説明はたしかに飯場制度の一面、すなわちその労働力募集、確保の機能の根拠をいちおう解明しているようです。しかしながら、飯場制度が作業請負制として生産過程の内部に介入していることの必然性はこれだけでは十分に理解し得ません。
私は、この飯場制度存続の根拠は基本的には鉱山業の生産過程の特質に求められるべきであると考えています。この主張を理解していただくために、もう一度、先ほど申し述べた技術の近代化の過程を振り返ってみましょう。そこですぐ気がつくことは、近代技術が採用されたのは、主として主要坑道、排水、竪坑運搬などに限られ、鉱山業の基本作業たる採鉱部面および切羽運搬においては、従来とほとんど変わりのない手工業的段階にあったことです。
もちろん採鉱過程でもまったく進歩がなかったわけではありません。鎚やタガネはいくぶん改良されていましたし、何より火薬の使用は開坑・採鉱作業の能率をいちじるしく高めました。しかしこれによって採鉱作業の手工的性格が変わったわけではありません。また採鉱法が鉱脈中の富鉱部のみを掘りとるいわゆる「抜き掘法」──「狸掘り」とも言いますが──であったことは、この場合とくに重要な意味をもっています。これについてはまた後でふれたいと思います。
ところで、このように作業がまったく手工業的である場合、作業能率を増進させるためにはつぎの2つの手段しかありません。そのひとつは出来高賃金制、もうひとつは直接的な監督の強化です。
まず第1の出来高賃金制ですが、これが「労働者による労働者の搾取」を伴いやすいものであることはご承知の通りです。しかも採鉱作業の場合には、基準賃金が一般の個数賃金の場合とちがって、各切羽ごとに、したがって集団的なものとして決定せざるをえないので、とくに「労働者による労働者の搾取」が生まれやすいのです。
つぎに直接的監督の問題ですが、一般に採鉱業においては、作業現場である切羽は、鉱脈の状態に応じて広い地域の各所に散在することになります。それも平面的でなく立体的に散らばっています。たとえば明治19年の足尾では切羽の総数は151箇所にものぼりました。これらの切羽は坑道や竪坑で連絡しているとはいっても、各作業場の独立性、分散性は一般の工場とは比較にならぬほど大きなものがあります。その上、坑内は暗黒であり、坑道も狭く険しいといった条件も加わるので、採鉱作業を資本が直接的に監督することは著しく困難です。このような諸点こそ、作業請負制としての飯場制度が存続せざるをえなかった主要な根拠です。
では、なぜ鉱山業の基本作業である採鉱過程の技術的な進歩が、ほかの部門にくらべ立ち後れたのでしょうか。これがつぎの問題です。この問いに対してはほとんど定説的といってもよい答があります。それは日本の低賃金が原因であるとする見解です。たとえば星野芳郎氏はマルクスを引用しつつ、つぎのように言われています。
「日本の鉱山や炭坑、各種の建設事業における機械化の極度のおくれは、根本的には労働者の低賃金労働に起因している。」(『現代日本技術史概説』)
私ももちろんこの指摘は誤りではないと思いますが、しかし明治20年代の足尾銅山において採鉱作業の近代化が進まなかった原因としては、これだけでは十分な説明にはならないだろうと考えています。これには、さらにつぎの2つの要因があわせて考えられなければならないでしょう。ひとつは鑿岩機の技術的な未発達の問題であり、もうひとつは資本蓄積がまだ低位な段階にあったことです。
まず第1の点についてみます。鑿岩機の技術的な未発達といっても、鑿岩機そのものが日本に知られていなかった訳ではありません。しかし当時の鑿岩機はいわゆる「ピストン式」のもので、形も重量の大きいので、一般には大規模坑道の掘鑿に用いられただけでした。採鉱の機械化が技術的に可能になったのは、ようやく1899(明治32)年のハンマー式鑿岩機の出現以後のことです。これで、なぜ採鉱作業が機械化されなかったかは一応はっきりしましたが、それだけでは採鉱法が旧来の抜き掘りにとどまり、近代的な採鉱法である階段掘り等が採用されなかった理由が不明です。というのは、採鉱作業を機械化するにはその前提として規則正しい近代的な採鉱法の採用が必須の条件ですが、これ自体はべつに鑿岩機を使用しなくても可能なことであるからです。そこで第2の要因を考えざるをえません。
それは、いわゆる「抜き掘法」は後でお話ししますようにいろいろな欠陥があるのですが、ただ鉱脈のなかの富鉱部だけを採掘するため、採掘量にくらべて採鉱量は多く、しかも品位が高いのです。したがって運搬量は少なくてすみ、選鉱も容易であるという利点をもっています。ですから運搬、選鉱などにさほど大きな固定資本を投下しなくても、比較的高い生産をあげられるわけです。このことが、なによりも、資本蓄積が低位にあった創業時には魅力だったのです。
採鉱法の変化と飯場制度の弱化
しかし「抜き掘法」には採鉱・切羽運搬の機械化の不能という問題を別にしても、早晩克服されなければならない欠点がいくつかありました。それは、つぎの3点のようなことです。
1)採掘跡が不規則になるため、掘り進めば掘り進むほどその後の採掘・運搬が困難になり、しかも通風も悪くなる。
2)母岩が固いなど採掘困難な箇所、あるいは低品位鉱は掘らずに残してしまう「乱掘」になり、長期的にはその鉱山の寿命を短くする。
3)採掘しないまま残された低品位鉱は鉱毒の原因となる。
このような欠陥は、足尾銅山でも明治20年代の後半にははやくも問題となります。そのひとつは産銅量の停滞として、第2には鉱毒事件の発生として顕在化しはじめ、解決を要する問題として意識されはじめます。そのためには、いうまでもなく採鉱法の転換が必要でした。その詳しい経過については省きますが、足尾においてはこの「抜き掘法」から「階段掘法」への移行は明治20年代の後半に始まり、36、37年頃にいたってようやく一応の完了をみます。このような採鉱法の転換は、全国的にも明治36、37年頃を境に進展します。
ところで、この階段掘法の採用は必然的に飯場制度の変質をもたらします。なぜなら、これまでの「抜き掘法」の場合には作業は経験的に習得された技能だけで可能だったのですが、「階段掘法」となると、作業の監督にはどうしても単なる熟練では得られない「科学的技術」が要求されるようになったからです。もはや作業監督は旧来の経験のみに頼る飯場頭の手には負えなくなったわけです。そして彼らに代わって現場の指揮監督は技術者=現場係員の手に移らざるを得ませんでした。しかも、階段掘法の採用にともない、ある程度切羽が集約整理されたので、それまでに比べると資本の直接的・統一的な監督が容易になったのです。
飯場制度の作業請負の機能が失われた背景にはこうした技術的な変化がありました。そして飯場頭の職務は労働者の募集、雇用の際の身元保証、鉱夫入坑の督励、日常生活の管理に限定されるようになります。それとともに、鉱夫の賃金決定、作業箇所の配分などはまったく資本の手に握られるにいたり、鉱夫は飯場頭に雇われるのではなく、資本と直接に雇用関係をむすぶことになります。これこそが、従来の飯場頭の「雇用主」的ヴェールをはぎとり、その鉱夫統括力を弱化させた原因です。
もっとも飯場頭は募集の際の前貸し、物品の貸し売り等の債権によって鉱夫をしばり、さらに鉱夫賃金の一括代理受け取りを依然としておこなっていましたから、配下鉱夫の賃金決定に無関係ではありませんでした。これらにより、以前と比べると弱体化したとはいえ、その鉱夫支配力は存続していたことも事実です。しかし、作業請負をおこなわなくなった現在では、賃金の代理受け取りはその合理性をまったく失い、その中間搾取者的性格を露骨に示すことになります。
ここにいたると、鉱夫らが飯場頭によるピンハネをピンハネとして意識し飯場頭が彼らの労働に寄生する不当な存在であることを認識するのは比較的容易になります。暴動前に坑夫らが「坑夫ヨリ飯場頭ニ渡シオク委任状ヲ取戻シ坑場ヨリ直接ニ金銭ノ授受ヲ為スコトニ決議」したことは、これを明瞭に示しています。
その上、作業請負を奪われ、これを一定の手数料収入にかえられた飯場頭は、日露戦後のインフレにより実質的に減収となります。彼らはこれを補うために、各種の賦課金の徴収、あるいは賄い料や供給品の値上げなど、流通面における収奪を強化しました。これによって飯場頭と坑夫の間の矛盾はいっそう激化し、飯場頭が中間搾取者たることの認識はさらに容易になったと思われます。
ここにこそ、坑夫らが公然と飯場頭に反抗することが出来、あるいはその制止を振り切ってストライキや暴動に立ち上がり得た根拠があると考えます。
*1 大河内一男『黎明期の日本労働運動』(岩波新書、1952年)207-208ページ、214ページ。
*2 岸本英太郎『日本労働運動史』(弘文堂、1950年)97ページ、101ページ。
*3 この点については、二村一夫「足尾暴動の基礎過程──出稼型論に対する一批判」の「問題の所在」で論じた。
*4 「まったくの本能的反抗」という主張は誤りであった。これについては、拙著『足尾暴動の史的分析──鉱山労働者の社会史』第1章、とりわけ75ページを参照ねがいたい。
*5 従来、友子同盟は飯場制度とまったく同一視されるか、あるいは親分子分制によって飯場制度を補完するものと理解されている。後者はたしかに友子の一面を把握している。しかし友子同盟が労働者の自治的
共済団体である限り、逆にストライキ等の闘争の母胎となる可能性を残していたことも無視し得ない。実際、この足尾の場合をはじめ、友子が闘争の組織となった事例は予想外に多い。鉱山労働者が永岡鶴蔵のような労働者出身の指導者を生み出し得たことは、友子同盟の存在と切り離しては理解し得ないように思われる。
*6 明治初年の生野、佐渡、院内等における鉱山騒擾は、まさにこの過程に対応して起こったものであり、これまで言われてきたように「奴隷労働的な苦役をめぐる騒擾」ではない。闘争を主導したのも、おそらく一般の鉱夫ではなく山師らであったと思われる。
なお、ついでながら明治10年代から20年代にかけて、各地の鉱山でかなり多くのストライキがあったことが記録されている(永岡鶴蔵「鉱夫の生涯」、隅谷三喜男『日本賃労働史論』など)。これらは賃上げを主とし、かなり統制のとれたストライキであって、明治初年の騒擾とも40年代の暴動とも質的に異なっている。これはおそらく、資本と、飯場頭の主導する坑夫との間で請負代価をめぐって争われたものであろう。
初出は『労働運動史研究』No.12 1958年11月29日。なお、オンライン版掲載にあたり、文意を変えない範囲で文章にいくらか手を加え、注の(1)〜(4)を追加した。
|