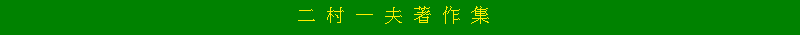終章 総括と展望(2)
──展望:労働史研究の現地点の確認のために──
(3) 今後の課題
最後に,本書で明らかにし得たと考える論点のうち,より一般的な問題にかかわるところを敷衍し,同時に今後の研究課題を確認しておきたい。ただ正直のところ,いま得られている結論,というより中間的な到達点は,とうてい一般的な理論を展望するようなものではなく,すでに多くの人が指摘していることを,別の角度から論じ,これまで広く受け入れられてきた理論の限界,問題点を示しているに過ぎない。ただ私としては,日本の労資関係の特質を歴史的に解明するために,研究史に学び,先人の理解を自分で掘り起こした史実とつきあわせ,納得できない説明に対しては,史実に整合的な解釈を発見すべく努力を重ねたつもりである。その際,いかに権威ある理論であろうと疑い,ひとつの疑問を解く過程で生じた別の疑問を大事にし,その答えを追い求めることを繰り返した。その意味では,ここに述べる中間的な結論と同時に,こうした結論を出すに至った道筋とその過程でのささやかな発見についても,読みとっていただければ幸いである。
労働運動の経済主義的理解への疑問
本書の各章を通じて明かになった論点の1つは,これまでの日本労働運動史,日本近代史,日本資本主義発達史などの研究に見られる労資関係,労働運動,とりわけ労働争議についての理解が,著しく経済主義的であったことである。その意味は二重である。
第1は,労資関係をとりまく歴史的,社会的,文化的要因の軽視である。とりわけ労働運動を理解する上で決定的に重要な,労働者の主体的要因の分析についての軽視である。現代の労働運動論においては,労働者階級の窮乏化の進行から直接的に運動の発展や変革主体の形成を説き得ないことは広く承認されているが,日本労働運動史をはじめとする日本近代史研究においては,この観点が欠如している。少なくとも,日本労働運動史研究においては,こうした視点から労働運動を具体的に把握した成果は多いとはいえない。一方現代労働運動論としての主体形成論では,歴史的な把握を含む場合でも外国,それも欧米先進国の事例が中心で,日本の労働者階級の歴史をふまえた検討が不十分であるように思われる。もちろん,これは主として日本労働史研究のたちおくれに起因するものであろうが。
第2は,これも主体的要因を無視あるいは軽視しているからであるが,日本における労働者状態についての理解,とりわけ第二次世界大戦前の労働者状態についての理解が,一般にきわめて経済主義的で,〈窮乏〉そのものについての把握も単純に過ぎることである。このため,いつでも,いかなる産業・職業でも,低賃金・長時間労働を自明のこととし,ともすれば,〈奴隷的〉,〈信じられないほど悲惨な〉,〈苛烈な〉,〈極度に劣悪な〉といった形容で労働条件を規定し,労働者状態についての現実に即した分析,全面的な把握を怠ることになっている。
これらのことが,争議や暴動を,つねに経済的窮乏に対する〈自然発生的抵抗〉として,描くに終わらせているのではないか? もちろん〈原子化された労働者説〉は,こうした経済主義的理解とは異なっている。しかし,その論理の背後に,あるいはその前提として,こうした単純な経済主義的認識を秘めていることは,第1章の冒頭に引用した一節を再読されれば明らかとなろう。
もとより争議や暴動は〈胃の腑の問題〉という側面をもっている。足尾暴動をはじめとする1907年の一連の労働争議の主原因が,インフレによる生活困難にあったことは明瞭である。だが,〈信じられないほど悲惨〉な労働条件の下にあれば,人々は必ず運動に立ち上がるというものではない。いかに飢えても,何らの運動も起こさなかった事例は少なくないのである。おそらく,人類史を通じてみれば,死に至るような飢餓であろうと大衆的抗議行動を生み出した事例の方が少ないのではないか? いずれにせよ,経済的要因だけで暴動や争議の発生を理解するのは無理である。
足尾暴動の検討によって確かめられたのは,賃上げ運動の担い手が,労働者の中ではもっとも高給をとっていた坑夫であったことである。もちろん彼らも窮乏していた。しかし,その〈窮乏〉は食うや食わずといったものではなく,それ以前に,他職種の労働者に比べ,また他産業の労働者に比べて,相対的に〈豊か〉な暮しを経験した時期があったことを抜きには考えられないものであった。そうした相対的な豊かさが失われた時,あるいは失われようとした時,何かのきっかけで,彼らは運動に加わったのである。
その〈きっかけ〉は,〈役員〉の侮蔑に怒った労働者が職制を殴るといった偶然的なことであったかも知れない。しかし,より一般的には,南や永岡のような労働運動家の呼びかけ,あるいは他山での暴動の知らせといった,広い意味での外部の働きかけであることが多かった。だが,それと同時に,そうした外部からの刺激を受けとめ,運動として展開するには,ある種の組織を必要としたのである。第一次大戦前の労働運動において鉱山労働者が大きな比重を占めたのは,鉱山業に多数の男子労働者が集まっていたこと,また1つの経営の規模が大きかったことにもよるが,友子同盟の存在を抜きには考えられないのである。全員集会か,飯場代表による集会かは鉱山の規模によって異なったが,坑夫が日常的に会合し,意見を交換し,代表者を選出する慣行をもっていたこと,しかも決定されたことが坑夫の総意として,全構成員を拘束することなどは,大衆行動を展開しやすくする重要な要件であった。この問題については,すでに何度か述べたので,いままた繰り返す必要はないであろう。
ところで,一般に運動の先頭に立ったのは,もっとも窮乏した最低辺の労働者ではなく,相対的には〈豊か〉な労働者であった。これは何も足尾に限らず,急速な拡張期をもった大鉱山・大炭鉱にも当てはまるように見える。たとえば,1907年には足尾のほかにも,別子,夕張,幌内などで争議や暴動がおきているが,これらの鉱山は,暴動時でも,他山に比べ相対的に〈高賃金〉であった。このように,相対的に好条件の鉱山や炭鉱で暴動や争議が集中して起きたのは何故であろうか? それぞれの鉱山によって独自の原因があるに違いないから,足尾だけの検討結果で安易な一般化はつつしむべきだが,そこに何か共通する要因があると考えるのは当然であろう。足尾暴動について検討し終えたところで,予想される理由は次の通りである。
これらの鉱山は,いずれも暴動に先立つかなり以前に,富鉱脈や優良炭層を発見するなどして,急速に生産規模を拡大した時期があった。そうした際には,地元や周辺地域だけでは急増する労働力需要をまかないきれず,他の鉱山と比べ相対的に高い賃金を支払い,必要な労働力を確保せざるを得なかった。また,それらの鉱山の優良な鉱体や炭層は,そうした相対的〈高賃金〉の支払いを可能にした。しかし,こうした山でも,必要な労働力が一定程度確保された後は,賃金の上昇は抑えられていった。とくに,金属鉱山の場合は,製品が国際商品で価格の変動が激しかったから,相場の低落時には賃金引き下げを招きやすかった。しかし,労働者はいったん高い水準で形成された生活・消費構造をすぐには切り下げ得ず,また飯場頭による中間搾取等そうした高水準を前提として形成されていた収奪構造も,実質賃金が下がったからといって直ちに解消するものではなかった。このため,物価騰貴ともなると,家計に赤字が生ずるか,生活水準を切下げるか,おそらくその双方が避け難く,運動参加への誘因となったのである。しかも,こうした多数の労働者を擁する大企業では,経営側が労働者を直接掌握することは困難で,その不満を的確に把握し,解決する仕組みもまだ整っていなかったばかりか,さまざまな罰則をともなう規則を制定し,労働者の不満を増大させがちであった。
同様の事例は,鉱山や炭鉱だけでなく,ほかの大経営にも見られた。その典型的な事例は,日本労働運動史上で最も著名なストライキの1つ,1898年の日本鉄道会社の機関方争議である。ストライキを起こした機関方の賃金水準は他の職業と比べれば著しい高賃金であった。にもかかわらず彼らが賃金増額を要求したのは,「明治20年代初頭以降,ことに日清戦争後の激しい物価騰貴のもとで,一般の労賃は名目上かなり上昇したのであるが,それとくらべて機関車乗務員ことに機関方のそれは著しく停滞的であった」(20)からである。また,1906年8月の呉海軍工廠の争議も,「其原因は〔日露〕戦時残業徹夜等のため多額の収入ありたるに反し,戦後は事業の緩急を計り,残業徹夜を廃したるため,各職工の給金は一時に少額となり,物価騰貴の今日,到底生活をなす能はずと苦情を唱ふるものある折柄,今回の昇級について職工長,組長等の専横より偏頗の処置ありたりとて,一般職工を激昂せしめたるものヽ如し」(21)という。両者とも,〈窮乏〉は争議の重要な動因の1つであるが,それは従来よく主張されたような〈奴隷的な〉労働条件のもとでの窮乏ではなかったことは明瞭である。個々の事例をあげることはしないが,第一次世界大戦後の労働争議の中にも同様な性格をもつものは,いくつも見いだすことが出来る。
労働者意識
〈はじめに〉で述べたように,1971年に労働争議研究の積極的意義を主張したとき,第1に強調したのは,「文書による記録を残すことがまれな活動家や一般組合員,あるいは組合にも参加しない労働者の意識,思想」を,人々の「行動そのもの」を手がかりに探ることが可能である点であった。争議という〈非日常〉を通して,労働者の〈日常〉を探りあてること,これが争議研究の重要な課題であると指摘したのである。この提唱は,最近の社会史ブームの中で注目されている〈マンタリテ〉(心性)の重要性とその把握の具体的方法を提示していたもので,西欧での民衆史や社会史の研究動向といささか共通する問題を,ほぼ同時に意識していたと言えるのではないか。
では,足尾暴動の分析を通じて何が明らかになったのか?
その第1は,坑夫らの間に〈差別に対する怒り〉が根強く存在したことである。至誠会が提唱した「南京米ノ改良」についての要求が大きな反響を呼んだのは,職員には内地米を販売しながら,労働者には外米しか売らないという差別的な処遇に対する怒りからであった。さらにこの怒りを明瞭に示しているのは〈暴動〉そのものである。端的に言って,足尾暴動とは,坑夫の職員に対する報復・制裁行動であった。その特徴は同じ職員の中でも,大学出より,まず労働者出身の下級職制が〈暴行〉の対象となった点にある。これは,現場員らが労働者と直接,日常的に接触する機会が多かったから,また賃金査定などを種に賄賂を強要したからであろう。だが,それと同時に,採鉱方や見張方は,本来は自分たちと同じ階層に属していたのに,〈役員〉となった途端に威張りくさって労働者を見下す態度をとったからであった。このような〈身分的差別〉によって日常的に欝積した憤懣,怒りが彼らを衝き動かし,暴動に駆り立てたのである。日本の労資関係の特質とその歴史的変化を解明するためには,この問題に示されたような現場労働者と職員の関係,およびその後の両者の関係の変化に注目する必要がある。
ところで,従来の研究では,こうした職制排撃に見られる労働者の怒りは,感情的な問題であり,意識的でないものとして軽視され,見過ごされてきた。その一方,争議を直ちに労働者階級の階級意識の高揚と結びつけて理解する傾向も根強い。だが,このどちらも日本の労働者を理解する上での重要な問題を見落とすことになっているのではないか。というのは,この〈差別に対する怒り〉は,何も初期の労働争議や暴動を特徴づけるだけのものではなく,戦前あるいは第二次大戦直後の激化した労働争議の多くに,程度の差はあれ広く認められるものだからである。一方,争議に示された労働者の〈怒り〉を〈階級意識の高揚〉と規定するだけでは,日本の労働者の〈心性〉の特徴を見失ってしまうことになるであろう。
〈差別に対する怒り〉が労働争議の動因となった好例は,今あげたばかりの日鉄機関方争議である。日本鉄道の機関方は,彼らの身分を「書記同等」とすること,また職名も〈馬方〉を連想させるような〈機関方〉でなく,〈機関手〉と改めることなどを要求したのである。機関方は,自分たちは労働者ではなく技術者であり,職員として処遇されるべきであるとし,それにふさわしい高賃金を要求したのであった。とくに,彼等は,機関方から駅長などへの昇格が認められていないことに,強い不満を抱いていた。もちろん,日鉄の機関方も,呉の労働者も,賃金に無関心であったわけではない。当然のことながら,賃上げにも強い関心を抱いていた。ただその場合,賃金の高さは単なる経済問題にとどまらず,その社会的地位の反映であり,人間としての優劣の尺度としての側面をもっていると考えられたのである。その意味で,日鉄の機関方が,その要求を〈待遇問題〉であるとして,運動のための組織を〈待遇期成大同盟会〉と呼んだのは象徴的である。言うまでもなく〈待遇〉には2通りの意味がある。1つは賃金をはじめとする労働条件一般であり,もう1つは〈課長待遇〉といった言葉が示すように,身分的処遇である。
このように,労働者と職員,とりわけ労働者出身の職制との関係が問題となるのは,何も日本だけのことではないが,この国ではとりわけ大きな意味をもっていた。それは何故かといえば,やはり明治維新の改革の特質と関わっていると思われる。明治維新によって封建的な身分秩序は崩壊した。四民平等は単なる建前でなく,一定の実質をともなっていた(22)。しかし,維新後の社会は文字通りの平等を実現したわけではなく,職業等による社会的地位の差は歴然としていた。新たな職業である工場・鉱山などでの労働は,人々が経済的窮迫からやむを得ず従事するものであったから,一般社会は彼等を〈下層社会〉として蔑視しがちであった。工場労働は,すでに歴史的に形成され社会内にしかるべき位置を占めていた職人より,一段低く見られたのである。工場労働者が〈職工〉と呼ばれるのを嫌い,〈職人〉と自称したことも,こうした社会的評価を反映している。
労働者は一般社会において差別されただけでなく,経営内においても差別された。工場・鉱山内には,生産過程そのものが要求する分業の体系,職務の編成があるが,封建社会での生活体験しかない人々にとって,こうした職務の体系を職務序列として,身分的な関係において受けとめるのはしごく当然のことであった。労働者は,そうした職場内における〈身分〉関係そのものを否定したわけではない。しかし,彼等の多くは自分たちが下層社会の一員とされ,あるいは現場労働者として企業内で底辺に位置づけられていることを当然とか,やむを得ないこととは考えなかった。イギリスの労働者が,労働者の子供は労働者であることを当然とし,労働者階級の一員であることに誇りを抱くといった気持ちは,日本の労働者には無縁であった。日本の工場労働者,鉱山労働者の間には,できれば労働者であることをやめたいと思っている人々が少なくなかった。彼等は,〈身分〉の上昇,社会的地位の向上に大きな意味を見いだしていた。一般労働者から一歩抜け出して〈役員〉となった者が,労働者を見下したのは,その意味ではきわめて自然であり,当然であった。これと反対に,一般労働者の間では,〈役員〉に対する憤懣が欝積していったのである。
もっとも,日本の労働者は〈差別〉に敏感で,〈人並み〉に処遇されることを強く要求する感情を抱いてはいたが,差別一般を否定していたわけではない。能力がすぐれているなら,〈上の身分〉であっても差し支えない。能力が劣っているのに,自分より身分が上であることに不満をもったのである。企業内での身分を決めたのは,主として学歴であり,ついで個人的な縁故であった。学歴は一定の〈能力〉の反映ではあるが,戦前の日本では親の経済状態に左右されるところが大きかった。日本の小学校は,イギリスなどとは違い,原則的には親の出身階層を問題にせず,地主の子も小作人の子も机を並べて勉強し,そこでは成績や腕力がものをいった。ところが,義務教育終了とともに親の経済状態が子供の進路を左右するようになるのである。1950年代頃までの日本の労働運動者の中には,成績優等であったのに家庭の事情から上級学校に行けず,自分より出来ない者が大学まで行きエリートとなっていることへの〈悔しさ〉をバネに運動に入った者が少なくない。労働運動の担い手が,最低辺の労働者であるよりも,むしろ相対的には〈高賃金〉を得ていた者であったもう1つの理由は,その層がこうした差別をより強く意識させられる状況に置かれていたからであった。
このように,個人の能力による差別を当然と考えるところでは,欧米の労働組合,とりわけクラフト・ユニオンの基本原理である,労働者相互間の競争の排除という考えは容易に受け容れられない。たとえば,日本の労働組合運動において出来高賃金制そのものに対する反対運動はほとんど問題にされたことがない。現に足尾銅山で賄賂があれほど横行した主な原因は出来高賃金制度にあったのに,これに反対する声はまったく出ていないのである。今日の日本の労働運動においても,建前としてはともかく,本音の部分ではこの傾向は根強く存続しているのではないか? 〈能力〉による差別よりを不当と感ずるより,労働組合員の間においても,能力を無視した処遇をこそ不当とする傾向が強いのではないか?
ところで,こうした問題を検討するためには,国際比較研究が有効であり,不可欠である(23)。本書をまとめ終えたいま感じているのは,この研究では,こうした国際比較の観点が十分でなかったことである。たとえば,第2章で作業請負制の根拠を問題にしたとき,作業監督が困難な坑内労働の場合,賃金が出来高制となるのは当然,と言うよりほとんど必然と考えていた。しかし,その後外国の鉱山業の歴史を調べているうちに,坑内労働の場合には確かにtutworkとかtribute system, butty systemといった請負制や,出来高賃金制をとる事例が多いが,アメリカ西部の鉱山では,採鉱夫でも日給制が主流であり,なかには,西部鉱夫連盟(Western Federation of Miners)のように,坑内労働者は熟練に関係なく一定の賃金を要求することを原則とする組合が存在したことを知り得た(24)。要するに,監督困難な坑内労働の場合,資本の論理としては出来高賃金制は必然であるが,それが現実になるか否かは,労働者側の対応と両者の力関係によるのである。それでは,なぜ日本の労働者は出来高制に反対せず,欧米の労働者はこれに反対したのか? 私自身は,おそらく次に述べるクラフト・ユニオン,クラフト・ギルドの伝統と関連があるのではないかと予想しているが,その追究は今後の課題である。
前近代社会の遺産
これまで著しく軽視されてきたが,労働者の主体的要因を考える上での重要な論点として,前近代社会の伝統の問題がある。再三強調したように,足尾暴動をはじめ20世紀初頭の鉱山争議では,徳川時代にその組織的起源をもつ友子同盟が大きな役割を果していた。近代日本の鉱山労働者の運動を考える時,この組織の存在を,したがって徳川時代からの仲間組織の慣行などを無視することは出来ないのである。たとえば,友子同盟の執行部とも言うべき大当番が複数制で,回り持ちの月番であったことや,意志決定にあたって全員一致をきわめて重視したことなどは,単に友子同盟だけではなく,おそらく近世日本の組織全体に関わる特徴を示しているように思われる。友子同盟だけでなく,足尾暴動では工業化前の社会における日本の民衆運動と共通する行動様式や価値観が随所に見られた。たとえば,南挺三所長の社宅を襲った〈暴徒〉のリーダーが,「飲み食いは自由だ,充分破壊せよ,しかし盗むな」と指示したところには,百姓一揆の行動規範と共通するものがある。あるいは,一般に労働争議などの際,日本の労働者は,経済的要求と同時に,経営者や職制に人間としての〈誠意〉を要求する傾向が強い。〈身分〉が上の者は能力だけでなく,道徳的にも,人間としても優れていることが建前として存在する社会では,誠意を欠き,人情を解さないことは,支配者としての資格を問われることになる。また,労資双方の対立点を明確にして妥協点・解決点を求めるより,各自がその個別の事情を訴え,情緒的な和解を生み出すことで対立を緩和させようとする傾向も強い。足尾暴動の後でも,操業を再開する前に,労資の代表が揃って山神社に参詣し,「暴動ノ為メ汚シタル山ヲ清メタ」ことなども,〈日本的〉な紛争収拾の特徴を示しているのではないか。こうした点は,日本独特であるか否かは別にして,欧米の労働運動ではあまり見られないところである。
さらに,暴動に先立つ演説会で永岡鶴蔵が鉱業法や鉱業警察規則,さらには治安警察法第17条さえ自己の運動を正当化し,足尾鉱業所を批判する根拠として用いたことに示されるように,自己の正当性を実定法に求めたことも注目される。これは永岡だけでなく,第一次大戦後においても日本の労働運動で一般的に見られた傾向である。労働者が自己の主張の正当性を,労働者も富国強兵の担い手であり,大日本帝国の一員であることに求めたのである。日清戦争、日露戦争を経て、労働者の間にも大日本帝国の構成員であるとする意識は強まっていた。そうしたなかで,労働運動に対する警察の厳しい取り締まりを受けながら運動を展開した彼らは,国体イデオロギーに依拠し,近代天皇制の一君万民論を逆手にとったのである。ところで,こうした傾向の反面には,日本では自己の生存を人間としての権利や自然権とする考え方がほとんど見られず,また根付かなかったことがある(25)。
では何故そうなったのか? かねてから問われてきたこの問題を解くにも,これまでのようなブルジョア革命の不徹底による日本の国家と社会の前近代的性格によるといった従来の説明だけでは理解しがたいことは明瞭で,やはり日本の近世にその根拠を求めざるを得ないのである(26)。
だが,これまでの日本近代史研究は,こうした前近代社会との関連にそれほど強い関心を寄せてこなかった。とりわけ日本労働運動史研究には,そうした傾向が強い。日本労働運動史の通史のほとんどは,明治維新以後,それも日清戦争からその筆を起こしているものが多い。工業化前の社会における労働慣行や労働組織,民衆の価値観などが,工業化後の組織や運動に及ぼした影響の検討など問題にされたことがない。わずかに取り上げられた場合でも,〈出稼型〉論のように,〈半封建的〉とか〈前近代的〉な〈遅れ〉の問題としてのみであった。友子同盟の評価もこうした傾向に妨げられて,長い間,否定的な側面だけが強調されてきたのである。だが,はたしてそうした捉え方でよいのか? 工業化の過程で,熟練労働者の中核を形成したのは職人層であった。江戸時代の職人組織と幕藩権力との関係,職人の価値観,労働慣行などと,工業化以降の労働者階級の組織,価値観等のかかわりは,無視し得ない重要な研究課題であろう。また,近代化後に,工場労働者の主要な給源となった農村社会での慣行,組織,価値観などが,企業社会にどのような影響を及ぼしたかなどについても,〈出稼型〉論とは違った角度から検討の余地があるのではないか。
ここ十数年来の欧米の労働史研究が明らかにし,強調してきたのは,西欧の労働運動の初期においては,運動の主な担い手は工場労働者よりも職人であった事実である(27)。これに対し日本では,労働運動といえば当然のように主として工場労働者の問題であると考えられて来た。これは何故であろうか? 大工や石工,左官など西欧のクラフト・ユニオンの運動を担ったった職人が,日本では初期労働運動の担い手にならなかったからであろう。では,それはいったい何故なのか? 私は,そこには,おそらく近世の日本における西欧のギルド的慣行の欠如していたからではないかと考えている。周知のように,西欧の職人ギルドの場合は,徒弟制度を通じた入職規制や,構成員の労働時間や能率を自律的に規制することによって労働力の供給量を制限し,労働条件を維持しようとする慣行が根強く存在した。これに対し,日本の労働者集団では,入職規制の慣行はきわめて弱い。それどころか,幕末の大坂の大工組などのように,個々人の役負担を軽減するために,鑑札をもたずに大工稼業を営んでいる者に,一人前の鑑札を持たせるよう,組を統括している大工年寄が指示している例が知られている(28)。また,友子同盟の3年3月10日という徒弟期間は一種の入職規制としての意味をもつものであったと思われる。しかし,実際にはこの期間を満たすことなく移動する者があってもそれを罰することもなく,入職規制として十分な効果をあげたとはいい難い。知る限りでは,友子同盟の存在が熟練坑夫の供給量の増加を妨げているといった不満が,鉱業主や技術者の間から出たことはないのである(29)。もちろん日本の職人組織でも賃金や労働時間を協定しようとした事実がないわけではない。しかし,そうした慣行を労働者自身がきびしく守ろうとはせず,まして幕藩権力をはじめ社会全体がこれを是認することはなかった。
さらに,機械化,合理化に対する抵抗,いわゆる制限的慣行の根強さは,欧米の労働組合運動の特色として周知のところである。しかし,近代化,鉱業化の過程で,日本の労働者が近代技術の導入に抵抗を示した事例は,汽車の導入に対する人力車夫の反対運動のほか,ほとんど例を見ない。鉱山労働でも,アメリカ西部の鉱山で,ダイナマイト使用に反対する運動が展開されたことがある(30)が,そうした問題は,日本では起きたことがない。吹大工にとって洋式熔鉱炉の導入は死活問題であるのに,その実験段階はもちろん,実用化に入っても反対運動が起きた兆しもないのである。
では,なぜ欧米のクラフト・ユニオンは,こうした組合政策を採用し,またある程度それに成功したのであろうか? その答えは,どうしても工業化前のギルド慣行と深くかかわっているとしか考えられない。よく知られているように,労働時間や作業量,賃金などの労働条件について,互いの競争を制限することこそがクラフト・ギルドの基本であった。しかもこうした慣行を,生産者だけでなく,社会全体が承認していたのである。直接資料にあたって調べているわけではないので確かなことは言えないが,徳川時代の日本では,こうした生産制限的な慣行が社会的に認められることはなかったのではないか? 先に指摘したように,日本の労働者は高い能力をもつものは高い地位,高い報酬を得て当然であるとする能力主義志向が強いのであるが,これも,前近代の日本におけるギルド的慣行の欠如と深く関わっているのではないか? 西欧の労働者が結果の平等を求めてきたのに対し,日本の労働者はチャンスの平等を求めてきたと言えるのではないか? このようなクラフト・ギルドの伝統の欠如は,決して過去の問題ではなく,特定企業の正規従業員だけを構成員とする工職混合の企業別組合を主流とする,今日の日本の労働組合の性格にも濃い影を落とすことになった。しかし,こうした問題は本書の範囲を超えており,まさに今後の検討課題である(31)。
【 注 】
(20) 青木正久「日鉄機関方争議の研究」,『黎明期日本労働運動の再検討』
(1979年,労働旬報社)16ページ。
(21) 労働運動史料委員会編『日本労働運動史料』第2巻,90〜91ページ。
(22) 鈴木正幸『近代天皇制の支配秩序』(校倉書房,1986年)参照。
(23) 国際比較研究の利点は,それによって国による違いだけでなく,共通性を解明できることにある。たとえば,生産過程の共通性は労資関係,労働運動にも類似した影響を及ぼすことがあると思われる。第1章で熱烈な労働運動家を生み出す契機として労働災害や安全衛生問題が大きな意味をもっていることを指摘した。永岡鶴蔵や山本利一が運動に加わった動機のひとつは資本家が利益追求のため安全設備をないがしろにし,労働者の生命身体を危険にさらしていたことであった。おそらくこれは日本だけのことではなく,一般に危険な坑内労働に従事する労働者組織が強靱な闘争力を発揮する基礎にあるひとつの要因であろう。こうした点を追究するためにも国際比較研究の必要があろう。
(24) John Rowe, The Hard-Rock Men , New York, 1974.
Richard E. Lingenfelter, The Hardrock Miners, Berkeley , 1974 .
(25) 鈴木正幸『近代天皇制の支配秩序』(校倉書房,1986年)および水林彪「近世の法と国制研究序説」(『国家学会雑誌』第90巻1・2合併号〜第95巻1・2合併号,1977〜1982)。
(26) 水林彪「近世の法と国制研究序説」(1)〜(6)(『国家学会雑誌』第90巻第1・2合併号〜第95巻1・2合併号,1977年〜1982年。
(27) Willam H. Sewell Jr. , Work and Revolution in France, Cambridge,1980.
E.P.Thompson, The Making of the English Working Class, London,1963.
Herbert Gutman, Work,Culture and Society in Industrializing America, New York, 1976.
(28) 西和夫「近世大工とその組織」(永原慶二,山口啓二編『講座・日本技術の社会史7 建築』,日本評論社 1983年)。
(29) 鉱山主や経営者の間で,友子同盟に対する批判がなかったわけではない。1891(明治24)年6月の『日本鉱業会誌』には,在黒森・直居駒吉「敢テ鉱業家ノ一顧ヲ煩ハサン」と題する小文が掲載されているが,その内容は,「鉱業家ガ使役スル多類ノ労働者中其ノ尤モ甚ダシク軽々同盟罷工ヲ企テ易キモノハ坑夫ニ如クナキニ似タリ」として,親分・子分,兄弟分の絆に結ばれた坑夫は,「常ニ容易ニ一致シ易ク,又団結セザルヲ得ザル仲間ノ義務アリ」として,ブラックリストの締結を呼びかけている。つまり彼らが友子同盟を問題視したのは、暴動や争議をおこす組織基盤となる点だったのである。
(30) Richard E. Lingenfelter The Hardrock Miners, Berkeley, 1974, pp.83〜84.
(31) おおよその見通しは,拙稿「日本労使関係の歴史的特質」(社会政策学会年報第31集『日本の労使関係の特質』,御茶の水書房,1987年)で述べた。また,〈差別に対する憤懣〉が日本労働運動の歴史においてもった意義については,拙稿「企業別組合の歴史的背景」,法政大学大原社会問題研究所『研究資料月報』第305号(1984年3月)で論じたことがある。
[初版は東京大学出版会から1988年5月10日刊行]
[本著作集掲載 2004年9月7日]
【最終更新:
|