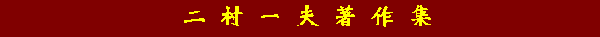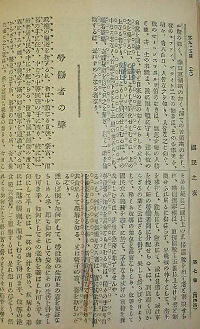高野房太郎とその時代【追補1】
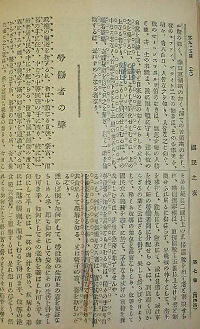
大田英昭氏に答える
─ 〈労働者の声〉の筆者は誰か・再論(1) ─
はじめに
今から128年もの昔、民友社の『国民之友』に掲載された「労働者の声」*1は、日本で最初に労働組合運動の意義を説いた論稿として知られています。ただ活字で発表された無署名論文ですから、その筆者が誰であるかは、今なお確定していません。ただ私は、かつて本著作集に連載した『高野房太郎とその時代』で、高野房太郎執筆の可能性が高いことを論じました。それが第38回「〈労働者の声〉の筆者は誰か」です。また、オンライン本を改稿し、岩波書店から刊行した『労働は神聖なり、結合は勢力なり ─ 高野房太郎とその時代』(2008年刊)でも、第6章「アメリカからの通信 ─ 日本最初の労働組合論」に「〈労働者の声〉の筆者は誰か」の一項を設け、同様の主張を展開しています。
この私の主張に対し、大田英昭氏は、その著書『日本社会民主主義の形成 ─ 片山潜とその時代』で、批判を加えられました*2。批判点のひとつは、私が「これまでこの論文の筆者を探索した人はいません」と書いたことに対する誤認の指摘でした。すでに『日本歴史』1952(昭和27)年12月号に、家永三郎氏が「〈労働者の声〉の筆者」*3と題する小論を寄稿されていたのです。家永氏は、たまたま同年夏、『国民之友』の主筆だった徳富蘇峰に面会し、その証言を得て、これを紹介されたのでした。他にも、佐々木敏二氏が「民友社の社会主義・社会問題論 ─ 『国民之友』を中心に」*4と題する論稿で、この家永氏による蘇峰証言をもとに「労働者の声」の筆者について論及されていました。
さらに大田英昭氏は、この蘇峰証言を主たる根拠として、「労働者の声」の筆者は竹越三叉である蓋然性が非常に高いと主張されました。大田氏はご著書のなかで、この「二村批判=竹越三叉説」を、長文の注の形で論じただけでなく、ご自身のブログ《長春便り》にも「労働者の声」の筆者についてと題する一項を設け、この注の全文を再録されています。ブログに転載されたのは4年も前のことのようですが、私が気づいたのはごく最近です。どうやら大田氏は、この「二村批判」によほどの自信と執着がおありのようです。最初に本でこの批判を読んだ時は、他の仕事で忙しかったこともあり、こちらの主張を読んでいただければ分かることだと、反論しませんでした。しかし、ブログに独立項目として転載されたことで、ネット社会では、放置しておくと批判を認めているに違いないと、批判者にも一般の読者にも誤解される恐れがあると考え、遅ればせながらリプライすることにしました。
私が、家永三郎氏や佐々木敏二氏の先行研究の存在を見落としたまま、「〈労働者の声〉の筆者は誰か」を論じたことは、研究者として初歩的な誤りで、大田氏の批判と教示に感謝する次第です。
しかしながら大田英昭氏が、「竹越三叉は早くから社会問題への関心が高く、民友社の幹部でもある竹越が〈労働者の声〉を執筆した蓋然性は非常に高いと考えられよう」との結論を出していることには、疑問を感じました。「蘇峰証言」を用いる際に必要不可欠な史料批判が、全くなされていないからです。そこで本稿では、この問題を検討するため、最初に家永三郎氏による徳富蘇峰証言の内容を紹介し、次に「労働者の声」の筆者が三叉・竹越与三郎であり得るか否かを、仔細に吟味したいと考えます。
1. 家永三郎氏による徳富蘇峰からの聞き取り
かつて古代・中世佛教史研究を専門としていた家永三郎氏は、第二次大戦中から近代思想史にも研究テーマを広げておられました。とりわけ、戦後間もなく『国民之友』全372冊のうち約200冊ほどを入手されたこともあって、同誌の研究に手を染められたとのことです。その研究の一環として、1952(昭和27)年8月、家永氏は、徳富蘇峰を熱海の居宅に訪れ、聞き取りをされました。当時「労働者の声」の筆者探しに関心を抱いていた家永氏は、同稿が掲載された『国民之友』を持参して蘇峰に一読を乞い、その筆者について尋ね、その結果を「『労働者の声』の筆者」と題する一文にまとめて、『日本歴史』に寄稿されたのでした。短文ですし、正確を期すため、その全文を引用しておきます。
「労働者の声」の筆者
家 永 三 郎
国民之友」第九十五号(明治二十三年九月二十三日発兌)所載民友社の社説「労働者の声」が、日本の労働運動史上劃期的な文献であることは、周知の通りであるが、その筆者については、これまで疑問とされてゐた。赤松克麿氏は「筆者はわからない」と云ひ(明治文化全集解題)、嘉治隆一氏は「徳富の起筆にかゝると伝へられる」(明治時代の社会問題)と記してゐる。
私はかねてから何人の筆に成るかをつきとめたいと思つてゐたところ、たまたま〔原文は縦書き。「たまたま」の後半は繰り返し記号の「くの字点」……引用者注〕今年八月、徳富蘇峰翁と面会する機会を得たので、同誌を示して、これは誰の書いた文章であるかと尋ねたところ、翁はしばらく雑誌を目にくつつけて劈頭の部分を熟視してゐたが(翁は眼鏡なしで本を読むのである)、これは自分が筆を取つて書いたのではない、竹越か山路であらう、とはつきり答へた。私はこの重要な証言を学界に報告する義務があると思ふので、敢てこの短文を本誌に寄せた次第である。
(東京教育大学教授・文博)
家永氏は、この聞き取りの意義をかなり重視されていたようです。それは、徳富蘇峰宅への訪問から34年余の歳月が過ぎた1986年12月に、「『国民之友』研究の思い出」と題する一文を執筆され、同研究が未完に終わった事実を告白された後で、次のように述べておられることで知りました*5。
ひとつだけ学界にのこすに足りると思っているのは、『日本歴史』第五五号(一九五二年一二月)に載せた「『労働者の声』の筆者」と題する短文である。日本の近代社会思想史上の記念碑的文章とされていた社説「労働者の声」が蘇峰の執筆か、他の同人の筆か、後者ならば誰の筆に成るものかを、蘇峰から直接教えてもらいたいと思い、熱海の蘇峰宅を訪問し、高齢の蘇峰翁が眼鏡も使わずに私の出した当該論文を見て下した回答を報告したもので、おそらくこの文章の筆者についての確認の作業として唯一のものと思う。
『国民之友』の創始者であり編集者でもあった蘇峰に、実際に「労働者の声」を読んでもらった上で得た回答ですから、その証言は重視さるべきでしょう。しかし、一歴史研究者としては、いかに当事者の証言であろうと、その内容を吟味することなく鵜呑みにするわけには行きません。まずは、証言内容を仔細に検討する必要があります。なにしろ、この言葉は、90歳を目前にした高齢者に、62年もの昔に編集刊行した雑誌に掲載した一論稿の筆者について質問し、得た答えなのです。
まず注目すべきは、この蘇峰の回答が、「労働者の声」の筆者を一個人に特定してはいない事実です。家永氏による蘇峰証言の核心は、次の一文です。
これは自分が筆を取つて書いたのではない、竹越か山路であらう、とはつきり答へた。
この蘇峰証言で、確かな事実として認めても良いのは、「自分が筆をとつて書いたのではない」という箇所です。これは本人が、その論文を読んだ上で確言しているのですから、信頼するに足りると考えます。これによって、嘉治隆一が「徳富の起筆にかゝると伝へられる」と記した*6伝聞が誤りであることは確定した、と言って良いでしょう。
しかし、証言の後半部分、「竹越か山路であらう」という箇所は、「あらう」という言葉からも明白なように、蘇峰の推測による判断です。「労働者の声」の筆者を特定しているわけではなく、断定もしていません。竹越三叉か山路愛山の執筆であろうと、その蓋然性を述べているに過ぎません。このとき蘇峰は、「労働者の声」の「劈頭の部分を熟視して」はいますが、他に日記やメモを参照した様子はありません。つまり、89歳の徳富蘇峰が、27歳の時に編集刊行した『国民之友』に掲載した一論文の筆者について、記憶だけを頼りに答えたものです。蘇峰は、『国民之友』の論説記者のうち、こうした分野について書き得た人物は竹越三叉か山路愛山しかいなかったと考え、このように答えたものでしょう。おそらくこの時、蘇峰が、社外執筆者の存在に思い及ぶことは、なかったと思われます。なぜなら、家永三郎氏の質問は、「〈労働者の声〉が蘇峰の執筆か、他の同人の筆か、後者ならば誰の筆に成るものか」だったからです。この問いについては、前掲の「『国民之友』研究の思い出」に記されています。要するに、質問者も回答者も、最初から社外執筆者の存在を考慮していないのです。いずれにせよ、家永三郎氏の問いに対する蘇峰の回答が、さらなる検討を要するものであることは明白です。
なお、家永三郎氏は、この「蘇峰証言」を記録にとどめただけで、そこから先、つまり筆者が竹越三叉か山路愛山か、あるいは他の人物かまで、研究されることはありませんでした。家永氏は、1995年に、単行書未収録の論稿を集めた論集『古代史研究から教科書裁判まで』を出版し、そこに「〈労働者の声〉の筆者」も収録されました。「著者解題」で家永氏は、本文に数倍する長さで同稿の執筆経緯などを説明した後、「蘇峰の答がただしいかどうかは問題であるが、とにかく『国民之友』主筆その人の証言として他に代替性のない史料価値をもつことは否定できまい」*7と記しているのです。
2. 「労働者の声」は、はたして竹越三叉の執筆か?
そこで、ここではまず、大田英昭氏が「労働者の声」の筆者である蓋然性が高いと主張されている、竹越三叉説について検証します。本来なら、蘇峰がもう一人名をあげている「山路愛山説」についても吟味する必要があり、また、大田氏が「高野房太郎説」を否定されている論拠についても検討しなければなりませんが、長くなり過ぎるので、これらは次回以降にまわしたいと思います。
はじめに三叉説に対する検証結果を述べておけば、三叉・竹越与三郎が「労働者の声」を執筆した蓋然性は、限りなくゼロに近いと考えます。
その根拠は、つぎの2点です。
1) すぐに気づくのは文体の違いです。「労働者の声」は、名文家、美文家として知られた竹越三叉の文体とは、大きくかけ離れています。
2) つぎは文章の内容です。竹越三叉の著作の本領は史論や政論にあり、社会問題を論ずる場合でも人類史・文明史的な視角からの立論に終始しています。一方、「労働者の声」は、何より日本の現実を問題とし、解決策を提示したもので、これを三叉作品とみなすのは無理があります。竹越与三郎が執筆した多数の著書、論文を精査すれば、両者の関心事の相違は明瞭です。
以下、この2点について、具体的に見て行きましょう。問題の性質上、百数十年も前の文章を数多く、それも時にはかなり長く引用しています。読んでいてイヤになった場合は読み飛ばし、必要を感じた時に戻って、確かめてください。
2.-1. 文体の違い
三叉の文章を「労働者の声」と比べてみた時、まず感ずるのは、両者の文体、とりわけ朗読した時のリズムが大きく違っていることです。
三叉・竹越与三郎は、早くから、その名文、麗筆で知られていました。語彙が豊富なことや、その「清新玄妙な造語」は、多くの人の認めるところでした。彼は、何か論稿を書き上げると「抑揚の妙を極めた朗読をするのが例であり」その「文章は一種の散文詩とでも謂ふべきもので、如何にも口調が善く、悠揚として高風の雲を吹く様な趣があった」と評されています*8。また、民友社で竹越の同僚として、彼を良く知る山路愛山は、「竹越与三郎論」*9の中で、三叉の文章の特質を次のように論じています。
文章を作つても其通り、誠に正々堂々の陣で、旗も太鼓も多い。実質は勿論無いではないが、実質を裸で出さず、衣裳をつけ、羽毛を飾つて、立派なものにしてからでなくては満足しない。演説でも何でも皆其流儀で、総て荘重典麗。
私が読んでも、竹越三叉の文章は、独特の形容を駆使し、多様な語彙を用いて、特有のリズム感をもっていることに気づかされます。別の面からみれば、愛山がいささかの皮肉を込めて特徴づけたように「荘重典麗」=「おごそかで重々しく、整って美しい」です。そうした特徴を示す文例を3点ほど紹介しましょう。うち2点は、「労働者の声」とほぼ同時代の文章です。
最初は、『新日本史』の「平民主義」に関する説明です*10。
この主義〔平民主義……引用者注〕の一たび現わるるや、天下靡然〔なびきしたがうさま〕としてこれに傾けり。何となればこれ、自由主義、民権論、人権説、個人主義、自由貿易論、最多衆民論、国家独立論、精神的発達論ら、すべての自由進歩的の文字の注入すべき江海〔川と海〕にして、以上の文字は、熔解して新たにこの平民主義となり、新奇なる色沢〔いろつや〕、新奇なる領分を有したるものなればなり。要するにこの文字たる、維新以来、単純なる、法権主義の専制に反対する、すべての分子の総管束を為し殿を為すものなり。
200字に満たないこの短い一節ですら、「江海」と「熔解」のように韻を踏んだり、「新奇なる色沢」「新奇なる領分」といった同じ形容を重ねたり、「総管束」といった造語を使うなど、さまざまな工夫を凝らしていることが見てとれます。
次は「労働者の声」と同じ年1890(明治23)年の5月16日に『国民新聞』に掲載された「近日の文学」*11です。文学論というだけでなく、三叉の文章論とも言うべき論稿です。
人心漸く近日の文学に飽きたるが如し。曰く今日の文学は繊少〔繊はかぼそいの意味、少は小の誤りか〕なり、微細なり、浮華〔外面だけ華やかで実質がない〕なり、卑汚〔卑しく下賎〕なり、曰く博大雄壮〔広く大きく雄々しく元気〕の思想なしと。甚だしきは之を以て六朝亡国の余韻となすものあり。
思うに是れ、最〔尤〕もの次第ならん。如何に大牢〔中国で、天子が社稷をまつるときの供物〕の料理は美味なりとて、三百六十五日朝夜旦暮〔朝に晩に〕、大牢の美味に潰されては、如何なる贅沢家も之に懲りん、況んや大牢の美味ならざるものをや。今の文学は、其初めて発達するや、漢文ともつかず、和文ともつかず味なく趣もなき佶倔聱牙〔文章が堅苦しく難解で、読み難い〕法吏の宣告文の如き文学を承けたるものなれば、その自然の結果として、絢爛華麗人目を眩射するものありき。世人の厭倦〔飽きて嫌になる〕を招くの原已に此にありて存す。彼已に絢爛の文によつて人心の一部を満足せしむ、未だ雄大博大の韻を求むるの心を満足せしむるに足らず。此に於てか天下の非難、今日の文学に集まる。今日の新文学を難ずるの声は、実に昔日の新文学を賞嘆せる声なり。〔後略〕
これなどは、まさに愛山が評した言葉通りの、「旗も太鼓も多く、衣裳をつけ、羽毛を飾つて、立派なものにした、荘重典麗な文」と言うべきでしょう。
第3の文例は、青少年向けに執筆された『人民読本』(明治版)の第26章「国民の経済(下)」の一節です*12。「労働者の声」とも通ずる説明的な文章の例として挙げておきましょう。
然らば如何にして国の富を蓄積せんかと云ふに、其道、多端にして一ならず。第一に人民各自勤勉にして節倹を重むじ、驕奢〔おごり、ぜいたくをする〕の弊風を避けざるべからず。然れども如何に勤勉なりとも、唯だ己の手足を用ゆるのみにては不可なり。譬へば農業を営むにも、耕作力役の外、農学の示す所に従つて、効験ある肥料を用ひ、作物循環の法を実行する等、百方、地力を利用するの道を行はざるべからず。工業にても同じことなり。我国にては労力者の賃銭、欧米に比して安しとの説あれども、我国の労働者は欧米の労働者に比して、機械を取扱ふ事に熟練せず、力役者と云ふべきも、技藝者と云ふ能はざる者多きが故に、富を生産する結果につきて云へば、我労働者の方遙かに少きが故に決して欧米に比して賃銭安しと云ふ能はず。
この文章は、若者に向けて書いているので、あまり難しいことばは避けていますから「荘重」とは言えません。しかし「驕奢の弊風を避けざるべからず。然れども如何に勤勉なりとも、唯だ己の手足を用ゆるのみにては不可なり」といった箇所を読めば、文にリズムがあることは明らかです。
なお、用語面で注目されるのは、「労働者の声」で多用されている「労役者」が使われておらず、代わりに「労力者」や「力役者」を用いている点です。また「労働者の声」では「熟練的の労働者」と呼んでいる人びとを、ここでは「技芸者」を用いています。さらに内容面では、日本の労働者の多くは熟練労働者ではないと論じており、これも「労働者の声」の筆者の立場とは異なっています。
以上、3つの文例に対し、「労働者の声」の文体は「抑揚の妙を極めた散文詩」とか「荘重典麗」と言うには程遠い、理詰めの文章です。それでも冒頭の導入部は、管子を引用するなど、措辞にも気を配っています。しかし、本論に入ると、もっぱら知識・情報の提供に集中し、措辞には無頓着になっています。比較するため、「労働者の声」の核心ともいうべき「同業組合」と「共同会社」、つまり労働組合と協同組合の結成を提唱している箇所を見ておきましょう。
吾人は今茲に、二個の方法を提出し、以て世の慈善心ある義人に愬へんと欲す。
其一は則ち労役者をして、同業組合の制を設けしむる事是なり。同業組合とは何ぞや。大工は大工なり、左官は左官なり、又其他の職人は職人なり、同職者相団結して、以て緩急相互に救ふの業を為す事是なり。此事たるや、欧米諸国にて既に久しく行はれしものにして、今日は其法頗る発達し、独り同職者のみならず、その職業の異なる者をも、皆団結して一体となり、以て緩急相応じて、以て其団結の利益を保護し、併せて之を拡張する所以の法を講ぜり。〔中略〕
斯の如く同業組合は、これを内にしては同業間の親睦を篤ふし、其緩急相助くるの情を養ひ、彼等をして幾分の所得を貯蓄せしめ、又非常の時に際しては、その緩急に応ずるの保険者たらしめ、之を外にしては以て同業者の勢力を団結して、その疾苦を医するの手段を講じ、已むを得ざる時に至りては、罷工同盟をも為しかね間敷の勢を養ふに足る。〔中略〕
第二の考案は、共同会社の制是なり。其制たるや方法一にして足らずと雖、要するに資本家と労役者と、雇主と被雇者との間に在りて、其利害を並行せしむる所以の目的に外ならず。
則ち彼の労役者彼自身が、其少数の資本を出して、以て互に共同して営業を為すもその一なり。例せは大工の如き、別々にて之を為すよりも、其力を合せて之を為す時に於ては、其利甚だ多きは、更に呶々を俟たずして〔どどをまたずして=くどくど言わないでも〕明かなり。吾人は、我邦の人民、共同の精神甚だ少きを嘆ず。若し彼等にして共同の精神あり、少しく意を枉げても、其全局の利益を取り、之を以て己等に分配するの道を講せば、労は半にして功を倍するの結果を見ること疑なしと信ず、則ち佛国に於ては其実例赫然たるものあり。又た資本家と労役者との間に於て、其利害を並行せしめん為に、労役者をも其会社の一員に加へ、其利益の幾部以下は、之を会社の資本に割り、其の幾部以上は、之を会社員たる労役者に分配するの道を講するも可なり。或は又た労役者の勤労久しき時に於ては、其賃金若くは賞金の幾分を差引き、之をして彼等の株金と為し、彼等をして其他日に於ては、一個の株主たらしむるが如き制を設るも可なり。孰れにしても二者の利害を並行せしむるの道を講すれば足れり。
然りと雖以上は、たゞ富の生産上に於ける共同会社の利益にして、尚ほ富の分配上に於ける利益は、下に述ぶる所の者の如し。
即ち欧米諸国にて、其日用品をば社員中には最も廉価に売渡し、以て生活上の便益を図る事あり。此事にして若し其方法宜きを得ば、労役者をして生活の便益を得せしむるに於て、實に浅からぬ恩恵を与ふる者なり。例せば爰に少数の資本金を以て、味噌、醤油、薪、米、干物、濁酒、金巾木綿、石炭油、弁当、すべて是等の物を卸売同様の減価にて、最も薄利に之を販売する時に於ては、その労役者を利する、其効勝て云ふ可からず。而して此資本金や、若し労役者の資本よりして斯の如き会社を成立たしめば、是最も妙の妙なる者と雖、我邦に於て斯の如き事を望む可からずとせば、他の仁人君子たる者が、自ら資本家と為るも可なり。
ここに、「抑揚の妙をきわめた」散文詩ともいうべき口調の良さを感ずることが出来るでしょうか? 「労働者の声」は「実質を裸で出」した文章とは言えても、「荘重典麗」と呼ぶことは出来ないでしょう。別ファイルに「労働者の声」の全文を翻刻しておきました。通読されれば、三叉の文体との違いは、よりはっきり分かると思います。
2.-2. キイワードを比べる
無署名の文章から筆者を探る上で手がかりとなり得るのは、使っている語彙です。無署名文と筆者が明らかな文章とを比較し、両者に共通する語彙の有無、頻度などから、ある程度、両者の異同を推測することが出来ます。そこで、まず「労働者の声」から、キイワードとなる語を選び出し、これと対応する語を『新日本史』から探し出して、比較してみます。
「労働者の声」で、キイワード中のキイワードともいうべきものは、「労役者」と「労働者」です。「労役者」は23回、タイトルにも使われている「労働者」は少年労働者や婦人労働者といった複合語も含め、7回出て来ます。また、「労役者」とほぼ同じカテゴリーの言葉である「職工」も、労働者と同じく7回出現しています。
もう少し範囲を広げて、職業や社会階級・階層、組織などに関連する語彙を選ぶと、以下の通り。順序はアイウエオ順、カッコ内の数字は出現回数です。既出の語も再掲します。
会社(7)、株主(1)、義人(1)、貴族(1)、共同会社(8)、購客(6)、豪富(1)、小売(3)、国民(1)、左官(2)、志士仁人(1)、資本家(4)、資本主(1)、社員(2)、熟練的の労働者(2)、職人(2)、職工(7)、人民(2)、人力車夫(1)、僧侶(1)、大工(3)、中等民族(1)、同業組合(6)、同業者(2)、同職者(1)、同盟罷工(1)、土方(2)、問屋(2)、農夫(1)、罷工同盟(5)、被雇者(1)、普通の労働者(1)、平民(1)、雇主(3)、友愛協会(1)、労役者(23)、労働者(7)。
一方、『新日本史』 の「旧社会の破壊、新社会の結合」の節*13から、上記の語に対応するカテゴリーの語彙を抜き出してみましょう。なお、当然のことながら、三叉本人の執筆ではない引用文は、採録対象から外しています。
階級(13)、学者(1)、華士族(4)、華族(8)、漢学者(1)、官人(1)、官吏(5)、貴族(1)、教育会(3)、基督教会(4)、基督教徒(1)、郡官(1)、県知事(1)、県庁(1)、県令(2)、公衆(3)、郷紳(7)、豪族(2)、工談会(3)*14、講談会(1)、豪農(4)、国民(3)、志士仁人(1)、士人(2)、地主(3)、士農工商(1)、資本(4)、社会党(1)、儒者(1)、上下議事院(1)、娼妓(1)、商社(1)、少年(1)、娼婦(1)、商法会議所(1)、書生(1)、紳士(2)、紳士壮年(1)、人民(13)、政社(3)、青年会(1)、壮士(1)、壮年教師(3)、村内長老(1)、大聖(2)、大名(1)、太政官(1)、地方官(1)、地方官会議(2)、寺子屋師匠(1)、土地(4)、農談会(1)、農民(2)、府県会(4)、府県会議員(1)、婦人会(1)、仏教団体(2)、仏僧(1)、文学会(1)、平民(13)、民会(4)、有司(1)、老大官(2)、労力(4)。
「労働者の声」と『新日本史』とで共通して使われている語は、わずかに「人民」と「国民」「平民」「志士仁人」の4語だけです。なお、部分的に共通する語としては、前者の「資本家」や「資本主」が、後者では「資本」として出て来ます。いずれにせよ問題は、労役者、労働者、職工といった「労働者の声」のキイワード中のキイワードが、『新日本史』では、まったく使われていない事実です。これも「労働者の声」の筆者を竹越三叉とする主張に、強い疑念を抱かせます。
2.-3. 文の内容からみた両者の相違
周知のように竹越与三郎は『新日本史』、『二千五百年史』、『日本経済史』など大部の通史・史論を刊行し、また『国民之友』をはじめ『六合雑誌』『国民新聞』『世界之日本』など数多くの雑誌・新聞に、多数の論稿を執筆しています*15。しかし、これらの著書や論稿のどこを探しても、「労働者の声」の筆者であれば、当然、論ずるであろう、労働問題に関する言及がないのです。
まず、「労働者の声」とほぼ同時期に執筆された『新日本史』について見ましょう。『新日本史』は、上巻が1891(明治24)年7月3日に、中巻が翌1892(明治25)年8月4日に、ともに民友社から刊行されています。なお、下巻はなぜか未刊です。ちなみに、服部之総は「三叉の『新日本史』は、下巻の稿成って、ついに発行を許可されなかったと伝えられている」*16と記していますが、真偽のほどは不明です。また『新日本史』の執筆時期は、1891(明治24)年2月27日から同年6月28日であることが、日記から判明します〔岩波文庫・下巻 pp.374-375、西田毅氏解説〕。つまり『新日本史』は、1890(明治23)年9月に「労働者の声」が発表されてから、半年も経たずに執筆を開始した書物、ほぼ同時期に書かれた本なのです。
『新日本史』のテーマは、幕末から明治23年までの日本の歴史、いうなれば現代史・同時代史です。その中巻「社会・思想の変遷」の中で、三叉は次のように論じています。
故に概していえば、明治十年までは、平民が士族に対して優劣の争を為したる時代にして、即ち武権と富との争なりしなり。然れども富、武権に勝つや、ここに富と富との争となり、直ちに資本と土地労力の争となれり。而して資本は市府に属し商賈〔商は行商する者、賈は店を構えてあきなう者〕に属し、土地労力は地方農民に属したれば、即ちここに地方村落と市府の争を起したるものなれば、いやしくも大局の眼あらん者は、一視同仁、早くも欧米の如き、資本と土地労力の激戦を生ぜざるに、予防の立法を為すべきに、明治政府の政策は比年〔年々〕、中央集権にして殊とに市府の人民に都合能き事のみ多かりしかば、市府は長大の進歩を為したり。これに引換え、農民は二十年間の保護政略の恩光に浴せざりしかば、悉くその資力を近傍都会の市民に吸収せられ、土地と労力とは連合して、資本に対して、激しき戦を挑みたるその結果遂に農民の敗北となれり。(岩波文庫、下巻p.112-113)
この引用箇所は、竹越三叉が「資本」という言葉を使っている数少ない例です。しかしこの文章には、「資本家と労役者」「雇主と被雇者」の対立という「労働者の声」の核心ともいうべき認識が欠如しています。仮に三叉が「労働者の声」の筆者であったならば、同時代史の「社会・思想の変遷」を取り上げる章で、それも「資本」という言葉を使っている箇所で、「労役者」「被雇者」に言及することなく、論を終えるでしょうか? また上の文で、三叉は「労力」という文言を使っています。しかし、この「労力」という言葉が指しているのは「農民」です。労働者は含まれていません。『新日本史』執筆の時点において、三叉に「労役者」「被雇者」に対する考慮はなく、労働問題に対する関心も基礎的な知識もなかった、としか考えられません。
こうした推測は、「社会問題の成行」と題する論文から、さらに明らかとなります。『六合雑誌』第81号(明治20年9月30日)に掲載されたこの論文は、大田英昭氏によって、竹越三叉が社会問題に関心をいだいていた証左として挙げられ、「労働者の声」が三叉執筆であることの有力な証拠とされています。また、文明の進歩が社会問題を発生させたことに関する「先駆的な洞察」だとする、高い評価がくだされている論稿です〔『日本社会民主主義の形成』 pp.175-176、p.189〕。
一方、私がこの論文に注目する理由は「労働疑問」という語が用いられているからです。おそらく「労働疑問」とは「labor question」を直訳した言葉で、今の用語なら「労働問題」でしょう。つまり、この論文は、三叉が労働問題についてふれている、数少ない事例なのです。主要部分を以下に引用します。
アヽ吾人之を知れり。彼の智者や学者や政治家が持て余したる百種の問題、幾千万の生死を以てするも其効なかりし変遷は唯だ社会問題を来さんが為なりしを知る。〔下線部分は、原文では傍点〕
欧米の諸洲に於て識者の眼光は相集まつて社会問題の一点に注ぎ、散じて労働疑問となり、資本論となり、賃銀論となりまた集つて土地疑問に帰入〔もとに戻ること〕するを怪しまんや。蓋し社会問題は其実僅かに郡県論を社会的の眼孔より論じ出せるものに過ぎずして、近代文明の特質に貧窮を養成するの分子を帯ると人を駆りて害悪に陥らしむるの傾向あるとの二者は、実に人権平等論と相合して社会問題を強からしめ、仏国の革命はその暁鐘となり点火となり後に来たるべきものあるを示したりとせば、一たび米国に於て社会問題を実行し之によりて一魚躍つて万波生ずるの態を万邦に現出するの日は遠からざるべきを信ず。蓋し社会問題は上帝を畏れ人を愛するものゝ如何にしても看過し能はざるの問題なればなり。(『竹越三叉集』《民友社思想文学叢書》第4巻、1985年、三一書房、p.208)
何とも論旨のはっきりしない、意味の取りにくい文ですが、この分かり難さの主たる原因は、三叉の「社会問題」についての考えが独特だからでしょう。欧米の有識者の論議が「社会問題」に集中した後、「社会問題」はさらに「労働疑問」「資本論」「賃銀論」に分かれ、ついで「土地疑問」に戻るという認識が示されています。さらに、社会問題は「郡県論を社会的の眼孔より論じ出せるものに過ぎない」とも主張されています。ここまで来ると、この「社会問題の成行」は、三叉が自分の頭で考え、その思索の結果を論述しているのではなく、横文字の種本か「種論文」があって、これを翻訳〔ことによると誤訳?〕・紹介しているのではないかとの疑いが生じます。「労働疑問」や「土地疑問」などという、後にも先にも日本語で使われたことのない言葉が出て来るのも、このように考えれば、納得がゆきます。
ここで注意すべきは、三叉が、ものごとを数千年単位で考える文明史家だったことです。「社会問題」も「労働疑問」も、こうした視点から抽象的に論じられており、日本の社会問題や労働問題の現実を直視し、解決策を見出そうとする姿勢は皆無です。労働問題とともに賃銀問題が挙げられているのも、三叉の労働問題に関する理解の欠如、と言って悪ければ独自性が示されています。このような論文を書いた人物が、「労働者の声」に見られる、日本の労働問題に対する具体的な解決策を構想・提唱したとは、とうてい考えられません。
なお、この論文の前半は、「支那印度波斯日本等の東邦が今日迄演じ来れる所は唯だ是れ拙劣なる戯曲を幾回となく繰り返せしものに過ぎずとの悪口を耳にせしと雖ども世界人類の史記は概ね皆此如きに過ぎざるなり」と述べています。要するに、アジア的停滞論がとりざたされて来たが、これは人類史全般にあてはまることで、改革・変遷はこれまで何回も繰り返されて来たことだと論じています。つまり「歴史は繰り返す」と主張した後で、本項最初の引用文は、これを受けての結びにあたる文章です。「蓋し社会問題は上帝を畏れ人を愛するものゝ如何にしても看過し能はざるの問題なればなり」と結論しているところを見れば、この「社会問題」は我々が現在考える「社会問題」ではなく、当時のキリスト者間の論争に関わって問題にされた言葉ではないかと臆測されますが、いかがなものでしょうか。
ここはやはり、本論文を「〈文明〉の進歩が〈社会問題〉を必然的に発生させたことについての先駆的な洞察といえよう」と高く評価しておられる大田英昭先生に、われわれにも理解できる言葉で、解説していただく他ないでしょう。
もうひとつ例を挙げておきましょう。竹越与三郎が、次代を担う少年少女に向けて執筆し、権利の意味を庶民に啓蒙する目的の「読本」、つまり教科書として執筆した『人民読本』(明治版)の一節です。
『人民読本』(明治版)の第25章、第26章「国民の経済」は、三叉が「労働者の声」の筆者であるならば、労働問題について論じてしかるべき章です。しかし、そこで労働問題に関して述べているのは、以下に引用する箇所だけです。 (慶應義塾福澤研究センター 近代日本研究資料2 『人民読本 (竹越與三郎著)』、1988年、慶應義塾福澤研究センター発行、p.80)。
我国にては労力者の賃銭、欧米に比して安しとの説あれども、我国の労働者は欧米の労働者に比して、機械を取扱ふ事に熟練せず、力役者と云ふべきも、技芸者と云ふ能はざる者多きが故に、富を生産する結果につきて云へば、我労働者の方遙かに少きが故に決して欧米に比して賃銭安しと云ふ能はず。
ここで思い出して欲しいのは、「労働者の声」の筆者の場合は、日本においても、労働者を「活版の職工」のような「熟練的の労働者」と、人力車夫のような「普通の労働者」とに分けて論じている事実です。この一点だけでも、「労働者の声」の筆者を竹越三叉とする説が成り立ち難いことは、明らかではないでしょうか。
また『人民読本』(大正版)の第34章「政治の主義及び政策」*17では、個人主義に対する概念として「衆団主義」をあげ、次のように論じています。
近年欧米各国、民衆の勢力、大に発達するに至りて、衆団主義、稍々勢力を得、延きて我が国にも波及しつつあり。蓋し個人主義は従来、少数なる上級豪族が、政府の権力を握り、此の権力によりて、人民の事業に干渉するを排せんがため、中等人民が発明したる政策にして、此の政策によりて利する所は、中等人民中の強者のみにして、下級の人民より見れば、一の豪族を除きて、他の豪族を迎ふるに等しきが故に、茲に衆団主義を歓迎して、中級の専制を排し、政府の干渉に依りて、幸福の分配に與らんとするものにして、下級人民の勢力を得る処は、即ち衆団主義の勢力の生ずる所なりとす。
もし三叉が「労働者の声」の筆者であったなら、「衆団主義」を論じた箇所では、「同業組合」について触れたのではないでしょうか。しかし、実際に三叉が論じているのは、政治の世界における権力や政策の問題だけなのです。
さらに、1933(昭和8)年、同時代史的文明評論として刊行された、竹越与三郎著『旋風裡の日本』*18も注目されます。同書は、ロシア革命やファシズム台頭後の作品で、資本主義と社会主義の対立が鮮明化し、労働組合や労働争議が日常的な出来事となった時代の作品だけに、竹越三叉の作品としては珍しく、労働問題について触れた箇所があります。以下が、当該箇所のほぼ全文です。
事業に関係して商品を生産するものは、企業家と資本家とサラリーマンと労働者であるが、このカテゴリーは、皆な生産より生ずる利益の分配によりて生活するのである。然るにこの利益の分配の方法が宜しきを得ないからと云ふので、労働争議が起るのであるが、余はそれが単一なる争議である限り、必ずしも労働者の主張が悪いと云へぬ。それは労働者の主張が我欲に過ぐる場合もあるが、企業家の主張が我欲に過ぐる場合もある。その善悪可否はその争議の原因如何にあることであつて、一概に何れを可とし、何れを否とすることは出来ぬ。併しながら近来労働者が団結して、その分配額を増加せんことを要求するがため、世人の耳目は労働者の主張にのみ注がれて、サラリーマンの報酬如何は余り問題にもなつてをらぬが、経済機構の運転より論ずれば、サラリーマンの報酬は、労働者の賃銀の昇るが如く、今日より増加せられねばならぬであらうと思ふ。併しながらその分配の方法如何は、各々その性質を異にする事業によりて、実際に案出せらるべきである。またこれと同時に会社の執務法と工場の経営法とを変更して冗費を淘汰せねばならぬ。同時にサラリーマンや労働者の気分を一変し、能率を増加せねばならぬ。併しながらこれらは会社経営論や賃銀論に於て論ずべき実際問題であつて、余の侵入すべき問題でない。
見られる通り、ここでの竹越の主張は、「労働者の声」の筆者とは、大きくかけ離れています。もちろん「労働者の声」から40年余の歳月が経過していますから、労働運動や労働組合についての評価や主張に変化があっても、不思議ではありません。しかし、労働問題に関する事実認識、理解のレベルが低下することはあり得ないでしょう。しかし『旋風裡の日本』の著者は、労働運動や、後で出て来る消費組合に関する議論でも、「労働者の声」の水準に、遠く達していないのです。
とりあえずの結論
以上、『国民之友』第95号に掲載された無署名論文「労働者の声」の筆者が、三叉・竹越与三郎である蓋然性はきわめて低く、限りなくゼロに近いことを、論証し得たと思います。
次回は、蘇峰が「労働者の声」の筆者でありうる者としてあげた、山路愛山について検討します。また私の「高野房太郎説」を否定する大田英昭氏の主張の論拠についても、具体的に検証します。
【注】
*1 無署名論文「労働者の声」、『国民之友』第95号(1890(明治23)年9月刊)。なお「労働者の声」の全文はjpeg画像で、「高野房太郎とその時代」(38)の末尾に掲載している。ただ画像では、やや鮮明を欠く箇所があるので翻刻、htmlファイル化し、〔高野房太郎とその時代 参考文献 「労働者の声」〕として本著作集に収めている。
*2 大田英昭『日本社会民主主義の形成 ─ 片山潜とその時代』(日本評論社、2013年刊)188~189ページ。
*3 家永三郎「〈労働者の声〉の筆者」『日本歴史』第55号、1952年12月。
ちなみに『日本歴史』は日本歴史学会編集の月刊誌で、現在は吉川弘文館から刊行されている。ただし創刊当時の出版社は日本歴史社、のち霞ヶ関書房、実教教科書と推移し、この時点では実教出版が刊行していた。
なお、本文でこの家永三郎「〈労働者の声〉の筆者」を全文引用しているが、その際、誤植訂正や不鮮明箇所の解読は、家永三郎『古代史研究から教科書裁判まで』(名著刊行会、1995年刊)によった。
*4 佐々木敏二「民友社の社会主義・社会問題論 ─ 『国民之友』を中心に」(同志社大学人文科学研究所編『民友社の研究』(雄山閣、1977年刊)所収)。
*5 家永三郎「『国民之友』研究の思い出」(《民友社思想文学叢書》第1巻『徳富蘇峰・民友社関係資料集』1986年12月、三一書房刊に付された『月報 7』所収)
*6 嘉治隆一『明治時代の社会問題』(国史研究会編輯『岩波講座日本歴史 第9 (最近世 [2]』、岩波書店、1934年刊)、p.40。
*7 家永三郎『古代史研究から教科書裁判まで』(名著刊行会、1995年刊)pp.356-357。
*8 西田毅『竹越与三郎 ─ 世界的見地より経綸を案出す ─ 』(ミネルヴァ書房、2015年刊)の「はしがき」およびp.64に紹介されている、元民友社員・春風道人の回想「昔の民友社」(『文章世界』1巻5号)。
*9 山路愛山「竹越与三郎論・常に第一流を以て自ら居る竹越君」(『中央公論』第25巻第11号、明治43年11月1日)。ここでは『山路愛山集(二)』(三一書房、1985年刊)に依った。
*10 竹越与三郎著・西田毅校注『新日本史』(下)(岩波文庫、2005年刊)p.145。
*11 『竹越三叉集』《民友社思想文学叢書》第4巻(三一書房、1985年刊)、p.285。
*12 慶應義塾福澤研究センター 近代日本研究資料2 『人民読本 (竹越與三郎著)』(慶應義塾福澤研究センター、1988年刊)p.80。
*13 竹越与三郎著・西田毅校注『新日本史』(下)(岩波文庫、2005年刊)p.82-118。
*14 労働組合の一種と推測されるおそれのある「工談会」ですが、実際は工手学校などを出た「技手」=現場技術者を「正員」とする全国組織です。大学出の上級技術者も「役員」「名誉員」などとして名を連ねていました。《国立国会図書館デジタルコレクション》の中に『工談会々員名簿』(明治25年11月調、工談雑誌社)があります。URLはhttp://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/779599/1
*15 竹越三叉の作品で、現在も比較的読みやすいのは、文庫や新書に収められている、次の3点であろう。①『新日本史』上下(岩波書店、2005年刊)、《岩波文庫》、西田毅氏による校注・解説が加えられ、原著の上巻は上として、中巻は下として刊行されている。 ②『二千五百年史』(講談社、1990年刊行)、竹越三叉の甥にあたる中村哲元法政大学総長の「解説 ─ 回想の竹越三叉」を加え、《講談社学術文庫》として上下2冊に翻刻されている。③『旋風裡の日本』、高坂盛彦「孤高の戦闘者竹越与三郎」と題する小伝と略年譜が付されて《中公クラシックス》の新書版として復刻されている。(中央公論新社、2014年刊)。
このほか、④『人民読本』が、明治版と大正版が1冊にまとめられ、慶應義塾福澤研究センターから1988年に復刻されている。また、『六合雑誌』『国民之友』『国民新聞』などに掲載された論文のかなりの部分は、『竹越三叉集』〔《民友社思想文学叢書》第4巻〕(三一書房、1985年刊)に収録されている。これには西田毅氏による「解説」、「解題」のほか「年譜・参考文献」が付されている。
なお、『日本経済史』をはじめ、竹越与三郎が執筆した冊子体の書物は、《国立国会図書館デジタルコレクション》で読むことが出来る。
*16 服部之総「史家としての蘇峰・三叉・愛山」(《服部之総著作集 6》『明治の思想』理論社、1955年)p.213。
*17 慶應義塾福澤研究センター 近代日本研究資料2 『人民読本 (竹越與三郎著)』(慶應義塾福澤研究センター、1988年刊)p.219。
*18 竹越与三郎『旋風裡の日本』(中央公論新社、2014年刊)p.96。
【追 記】
本論文は、2018年4月7日に、「再論・〈労働者の声の筆者は誰か?〉 ─ 大谷英昭氏に答える ─ 」というタイトルで掲載しました。しかしその後大田英昭氏が、同氏のブログに「二村一夫氏の反論に答えるーー「労働者の声」(『国民之友』95号、1890年9月23日)の筆者をめぐって」を掲載され、ネット上での論争となりました。そこで、この論文のタイトルも「大田英昭氏に答える ─ 〈労働者の声〉の筆者は誰か・再論」と改めました。
【2018年5月15日 記】
|