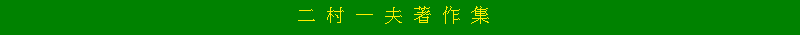 |
『足尾暴動の史的分析──鉱山労働者の社会史』 |
第2章 飯場制度の史的分析 ─ 〈出稼型〉論に対する一批判 ─ (1)はじめに日本の労働運動に関する歴史研究は量的に少ないとはいえない。しかし,残念ながら,質的にすぐれたものは多くはない。その理由の一部は,この分野が本格的な研究の対象となったのがようやく第二次大戦後のことであるという,学問自体の若さによるものである。しかし,戦後もすでに十数年を過ぎた今では(1),〈学問の若さ〉だけにその責任を負わせるわけにはいかない。では,現在,労働運動史研究の発展にとって何がもっとも要求されているのか? 最大の課題はその研究方法の確立であろう。 従来の日本労働運動史は,一般に実践家の回顧録あるいは事実羅列の年代記的色彩が濃く,それぞれすぐれた内容をもつものではあっても,そこから直ちに〈方法的〉に学ぶところは多くない。そうした中で,大河内一男氏のいわゆる〈出稼型〉論は,何よりも日本の労働運動の特質を問題にし,その特質を生んだ根拠の究明を意識的に試みられた点で,重要な意義をもっている。これによって,従来の無方法的な労働運動史研究は科学的に基礎づけられたと言ってもよい。この〈出稼型〉論は今なお労働問題研究の上に大きな位置を占めており,今後の研究にあたってその成果を無視することは許されないであろう。 Ⅰ 〈出稼型〉論とその問題点〈出稼型〉論 では,〈出稼型〉論とはどのような理論か。すでに周知のところではあるが,簡単にそれを見ておこう(2)。
(c) このような前提にたって,つぎに労働力の日本型が規定される。すなわち,日本資本主義はその創出期において,イギリスにおいて典型的に遂行されたような徹底的な農民層の分解,独立自営農民の一掃をなし得なかったため,その後も一貫して小農経営を維持しつつ,その中から労働力の供給を得てきている。ここから必然的に,日本の労働者はなんらかの形で前近代的な農家経済との結びつきを保つものとなり,言葉の広い意味における〈出稼型〉が成立する。この〈出稼型〉こそ正に労働力の日本型であり,日本資本主義の生成期から今日にいたる迄の一切の日本の労働問題を規定しているという。たとえば,低賃金,劣悪な労働条件,横断的労働市場の欠如,身分制的労働関係,労働組合の組織形態(企業別組合),労働者意識の前近代性,労働運動の不安定性などの根底にはこの〈出稼型〉賃労働がある,というのである。 〈出稼型〉論に対する批判論ところで,すでに述べたとうり,この大河内氏の理論は,日本の労働問題研究に大きな影響力をもっているのであるが,これが広く一般に承認されているかといえば必ずしもそうではない。むしろ多くの人々はこの理論に対し批判的であり,さまざまな反論や修正の企てがおこなわれてきた。しかし,その大部分は〈出稼型〉論の論理の枠内での批判に止るか,さもなければ,これをごく一般的な公式によって批判するに終わっている。労働運動史の分野では,それさえ十分に行なわれていない。そこで,先ずはじめに,従来の批判を参考にしながら〈出稼型〉論それ自体の問題点を,やや詳細に検討しておく必要があろう。 これまで批判者が〈出稼型〉論の問題点として一様に指摘してきたのは,その宿命論的性格である。たとえば大友福夫氏は〈出稼型〉論の重要な一部をなす企業別組合論を批判して,次のように述べている。 「何よりもこの考え方の弱いところは,それでは〈企業別組合〉から脱却するにはどうすればよいのかという行動の指針なり手がかりが全くみいだせないことにあらわれている。賃金労働の日本型といわれるものが,日本資本主義の構造そのものに由来していると説明されるだけであって………構造が変わらない限り,宿命的なものとして日本型労働が存続することになって,この構造を変革する指導勢力たるべき労働者階級について,すこぶる悲観的な見通ししかもてぬこととなる」(5)。 この批判は正当であろう。しかし,ここで〈出稼型〉論を宿命論であり現状解釈論であると指摘するに止まって,何が〈出稼型〉論を宿命論にしているのかを明らかにしなければ,問題は前進しない。
では〈出稼型〉論の問題点はどこにあるのか? 結論的にいえば,それは大河内氏の〈型〉把握の一面性にあり,その方法の非弁証法的性格にある。以下それを具体的にみよう。 以上で,大河内理論の大前提である「一国の労働運動,労働問題はその国の労働力の特質によって規定される」という命題をそのまま承認し難いことは明らかとなった。これは当然「一国の労働力の特質は労働運動,労働問題を制約する重要な,しかし一つの要因である」と変えられなければならないであろう。では,このような限定を加えれば〈出稼型〉論は存続を認められるものであろうか? この問いに答えるには,その前に日本の労働力の特質を〈出稼型〉と規定することの当否が検討されねばなるまい。
(c) 大河内氏によれば,日本の賃労働の「一般的な特質」は資本主義の生成期から1950年代の今日に至るまで,一貫して広義の〈出稼型〉であるという。氏はその例証として次の4類型をあげている(7)。
2)の季節的出稼について,これを〈出稼型〉と見ることには異論がない。1)と4)の紡績女工や通勤工の場合,これを常に〈出稼型〉と規定しうるか否か疑問がないわけでではないが,いちおう理解しうる。しかし,3)の〈流動的過剰人口〉工場,鉱山,交通における男子労働者の主力を占めるを〈出稼型〉とすることについては,並木正吉氏による有力な批判がある。すなわち並木氏は,国勢調査の農村人口(5000人未満の町村人口)の動態を克明に分析されて,次のような事実を明らかにしているのである(8)。 (d) 仮に前項で指摘した問題がなかったとしても,日本の労働者の特質を〈出稼型〉とすることには疑問がある。というのは,〈出稼型〉は主として労働力を,その労働市場における性格によって特徴づけたに過ぎないからである。もちろん労働力の特質がその労働市場での在り方によって制約されることは確かである。だが,それは労働力の性格が,その労働市場における在り方だけで決まることを意味しない。むしろ労働力がまさに労働力たることを実証するのは,ほかならぬ生産過程においてである。労働力は資本の支配する生産過程において,その生産機構の特質に応じて特有の性格を刻印される。例えば,比較的高い知識を必要とする植字工と暗黒の坑内で重労働に従事する炭坑夫とでは,その意識や生活様式に大きな違いがある。また,同じ造船労働者といっても,精密かつ高度の技能を要求される造機部門の労働者と,屋外での激しい筋肉労働に携わる船体部門の労働者とでは,異なった性格をもつことが知られている。さらにまったく同一の生産部門においても,新たな技術の導入や新たな生産方法の採用によって,労働力の性格が変化することはしばしばである。ごく一般的にいえば,近代産業の生産手段体系は,労働市場において如何に前近代的な性格を持っていた労働力であろうと,その生産過程に必要な技術的,社会的訓練をほどこし,これを近代的労働者に鍛え上げていくものである。〈出稼型〉論が抜け道のない宿命論に陥ったもう一つの理由は,この事実を無視したところにある。 課 題以上で〈出稼型〉論の問題点はいちおう明らかになった。しかし,これで 〈出稼型〉論批判が完了したわけではない。留意すべきは〈出稼型〉論が多くの,それ自体正当な批判にもかかわらず,いまだに労働問題研究に大きな影響力を有している事実である。それは何よりも〈出稼型〉論が日本の現実を問題にし,一面的ではあってもその分析に成功しているのに対し,批判者の多くは,単にそれを方法的に批判・修正するに止っているためであろう。こうした事態を克服するには,批判者がその批判を現実の分析,把握の上に生かし,それが〈出稼型〉論より現実をより正確に把握しうる,より優れた方法であることを示すほかないであろう。小論はそのための一つの試みである。 ここで検討の対象として取り上げるのは,1907年の足尾暴動である。まず問題の手がかりを得るために,大河内氏が足尾暴動をはじめとする1907年の金属鉱山における労働争議をどのように評価しているか見ておこう。 〔足尾暴動の〕「特徴は苛烈な原生的労働関係と奴隷制的飯場制度の強度な支配とは,労働組合の力をもってしてはコントロ−ルできない暴動を惹きおこすという点」にある。〔また明治〕「四十年代における各地の炭坑,鉱山,造船所,軍工廠等における大規摸な争議の頻発は,何れも足尾銅山の暴動と同じ社会的基盤にもとずくものであった」。
以上から,大河内氏は1907年の鉱山業における労働争議の性格をつぎのように見ていると考えてよいであろう。
以上の性格づけ全体に,疑問点は少なくない(10)が,本章で問題にしたいのは(1)の〈苛烈な原生的労働関係と奴隷制的飯場制度の強度な支配〉という規定の後半部分〈奴隷制的飯場制度の強度な支配〉についてである。前半の〈原生的労働関係〉という言葉は,人によってさまざまに使われているだけでなく,大河内氏自身もきわめて多義的に用いており,正確にその意味を把握することは難しい。しかし,ここでは〈過度労働と低賃金〉の意味で使われているとみられる(11)。とすれば,大河内氏の主張はつぎのような内容であると考えてよいであろう。 この主張が鉱山における争議の原因の一面をとらえていることは確かである。飯場制度は,親分・子分関係といった前近代的な人的関係によって労働者に極度の労働強化を強い,資本の搾取に飯場頭による中間搾取が加わって,労働者の不満を増大させる側面をもっている。しかし,ここで注意すべきは,飯場制度が,本来,労働者を統轄・支配することを主たる機能の一つとする組織であった点である。もし,飯場制度が,大河内氏のいうほど強度な支配力を保持していたのであれば,労働者がどれほど経済的に窮乏したとしても,反抗に立ち上がるのは困難ではなかったか? 少なくとも,欝積した不満は別のかたちで解決され,暴動といった公然たる反抗形態をとることなく終わったのではないか? このように見るならば,1907年に,鉱山で暴動やストが頻発したのは,この時点で「飯場制度が強度の支配力」を保っていたからではなく,むしろ逆に「飯場制度の弱化」が生じていたためではないか? 足尾暴動の経緯は,この推論の正しさを裏書しているように思われる。
第1章で詳しく見たように,暴動の主体となったのは坑夫を中心とした坑内夫で,反抗の対象となったのは鉱業所長から下級職制にいたる職員であり,飯場頭ではなかった。だが,注目すべきは暴動に先立って,賃上げ運動の主導権をめぐり,また飯場頭による中間搾取の制限をめぐって坑夫と飯場頭との間で公然たる対立抗争があったことである。しかもこの抗争で,友子同盟に組織された坑夫等は,飯場頭を窮地に追い詰めていたのである。暴動は,まさにこの段階で飯場頭によって企てられ,挑発された疑いが濃い。いずれにせよ,坑夫等が飯場頭と真っ向から利害の対立する闘争に立ち上がり,一時的にせよ勝利したことは,飯場頭の坑夫支配力が,この時点で弱化していたことを明らかに示している。 【注】
[初版は東京大学出版会から1988年5月10日に刊行]
【最終更新:
|
Edited by Andrew Gordoon, translated by Terry Boardman and A. Gordon The Ashio Riot of 1907:A Social History of Mining in Japan Duke University Press, Dec. 1997 本書 詳細目次 本書 内容紹介 本書 書評 |
|
|
|
|
||
Wallpaper Design © あらたさんちのWWW素材集 先頭へ |
||