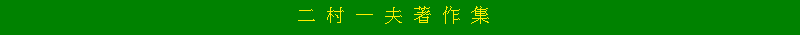第1章 足尾暴動の主体的条件
──原子化された労働者」説批判──
はじめに
第一次世界大戦の前後まで,日本の労働者,とりわけ鉱山労働者はしばしば〈暴動〉を起こしている。こうした形態の運動について,われわれはまだ学問的に充分な検討を加えていないのではないか。その結果,ともすれば〈暴動〉を「無知な民衆,あるいは意識の遅れた労働者による無秩序な騒乱」と見なす傾向が強いように思われる。だが,果して実態はどうであったのか? どのような労働者が,いかなる原因で,どのようにして〈暴動〉をおこし,あるいはこれに参加したのか? また,参加しなかった労働者はどのような人びとであり,その理由はどこにあったのか ? これらの点を1907(明治40)年の足尾暴動を対象に調べてみたい。
そこで,先ずはじめに,従来の研究が〈足尾暴動〉の担い手の性格をどのように把握しているかについて見ておこう。とはいっても,このテーマを中心に取り組んだ研究があるわけではない。多くは通史的叙述のなかで簡単にふれているにすぎない。それらに共通するのは「組織をもたず,経済的に窮乏した労働者による自然発生的反抗(1)」という理解である。
原子化された労働者説
そうしたなかで注目されるのは,丸山真男氏が「近代化のさまざまな局面の変化を個人の態度のレヴェルで図式化しよう」と企て,その図式の例証として1900年代における鉱山労働者をとりあげ,次のように分析していることである(2)。
「1900年代において原子化の傾向を集中的に表現すると考えられるのは,石炭・銅・銀などの鉱業における労働者であり,造船・鉄鋼業などに働く労働者がこれについだ。これらの産業は軍事的要請からして他の産業と不均衡に,生産力が飛躍的に膨張したため,ほとんど不断の追加労働力の調達を迫られた。紡績女工の募集が郷土の縁故関係に依存していたのに対し,鉱山や重工業の男子労働者は会社から全国に派遣された〈募集人〉が農村の大量の遊休労働力のなかから〈手あたり次第に〉引き抜いてきたものか,さもなければ自然に流れ込んで来る浮浪人口の中から採用されたものかであった。日本の産業革命初期の労働関係を大正中期以後から区別する一つの特徴は,経営者がほとんど無限に調達できる労働力に依存して安定した持続的な労働関係を維持しようとする配慮を全く欠いていたことであり,それに対応して労働者の一つの工場から他への移動が激しいことであった。ただ,これは近代社会における社会的流動性の現われとして理解できるものではなく,労働者はまだ一つの社会的〈階級〉にまでまとまらず,渡り職工や流れ者の大群として存在するにとどまっていた。しかも炭鉱労働者の〈納屋〉制度に典型的に表現されるように,こうした産業の労働条件は信じられないほど悲惨であった。
しかもなお悪いことに,日露戦争後の急激な生産規模の膨張は,下級労働者との家長的ではあるがパースナルな接触を保っていた〈親分〉の減少をもたらし,会社の下級職員──しばしば官僚気質最悪の側面を体現しているような──があらゆる保護を欠いた労働者の群れを直接に監督するようになった。日露戦後,大鉱山・巨大軍事工場に頻発したストライキや騒擾はこうした背景で理解されねばならない。大阪砲兵工廠や呉海軍工廠の騒擾(いずれも1906年),さらに有名な足尾銅山や別子銅山の大暴動(いずれも1907年)は,欝積した労働者の不満がひきおこした連鎖反応的な爆発であった。放火,建物の破壊,監督者の官舎襲撃といった彼らの巨大な破壊力は政府や会社当局を震撼させて,軍隊の出動をみちびき,同時代の社会主義者やアナーキストは相次ぐ蜂起に少なからず励まされたけれども,それはもともと絶望的に原子化された労働者のけいれん的な発作であって,いかなる意味でも組織された労働運動を構成するものではなかった。こうした諸事件がいずれもきわめて急速に鎮静し,継続性をもってさらに発展したり他に飛び火したりする傾向をほとんど欠いていたのは怪しむに足りない」。〔強調は引用者による〕
この丸山氏の分析の前提となっている世紀転換期の日本における鉱工業大経営の歴史的変化に関する事実認識には,不正確な点が少なくない(3)。しかし,何より問題にすべきは,ここに描かれている労働者像そのものである。その特徴は〈原子化〉の一語につきている。そこでまず,この〈原子化〉という言葉の意味するところについて丸山氏の説明を聞こう。
一般に近代化の過程では,〈伝統的〉社会に生活していた個人が,「それまで彼をしばり,一定の伝統的な行動を規定してきた共同体の紐帯から〈解放〉される」。この普遍的な現象を,丸山氏は〈個人析出〉individuation と呼び,「こうした個人析出のプロセスに,近代化のさまざまな局面におかれた個人の態度の面からして,四つのパターン──〈自立化〉individualization・〈民主化〉democratization・〈私化〉privatization・〈原子化〉atomization──をわかつことができよう。このパターンが,析出してゆく個人が社会との関係についていだく意識をも規定するのである」という。
氏は,この4つのパターンの相互関係と移動を次のように図式化されている。
「この図で水平軸は,個人が政治的権威の中心に対していだく距離の意識の度合を示し,ある人間が左によれば,それだけ遠心性 centrifugality が増す,つまりそれだけ政策決定中枢と一体化する傾向が減じる。こうして自立化と私化とは,政治的権威に対する求心的態度 centripetalを示す民主化および原子化とは逆に,軸の左方におくことができよう。これに対し,垂直軸によって個々人がお互いの間に自発的にすすめる結社形成の度合を示すことができよう。この図では垂直軸に従って上の方に来るのは,結社形成的な associative 個人,政治的目的にかぎらず多様な目的を達成するために隣人と結びつく素質の備わった人である。これの下の方に来るのは非結社形成的な dissociative 個人であり,仲間との連帯意識はより弱くなる」。
また〈原子化〉した個人の特徴はつぎのように規定されている.
「求心的・非結社形成的で他者志向的である。このタイプの人間は社会的な根無し草状態の現実もしくはその幻影に悩まされ,行動の規範の喪失(アノミー)に苦しんでおり,生活環境の急激な変化が惹き起こした孤独・不安・恐怖・挫折の感情がその心理を特徴づける。原子化した個人は,ふつう公共の問題に対して無関心であるが,往々ほかならぬこの無関心が突如としてファナティックな政治参加に転化することがある。孤独と不安を逃れようと焦るまさにそのゆえに,このタイプは権威主義的リーダーシップに全面的に帰依し,また国民共同体・人種文化の永遠・不滅性といった観念に表現される神秘的〈全体〉のうちに没入する傾向をもつのである。このような型の個人析出の噴出は,一般的には,ヒトラー直前のドイツが典型的にそうであるように,近代化の高度の段階の現象であるが,例えば多くの発展途上地域の場合のような近代化初期の局面でも,都市化した個人の間にはみとめられる(4)」。
疑 問 点
こうした図式の,分析用具としての有効性を問うことはひとまず措いて,ここでは1900年代の日本の鉱山労働者を「原子化の傾向を集中的に表現する」ものと特徴づけることの当否を検討してみたい。
まず前提となる基本的事実を確認しておこう。鉱山労働者の多くは農村出身者であった。ある者は完全に村を離れ,あるものは一時的に鉱山に生活する出稼ぎであるなど,彼らが生まれ育った村との紐帯を完全に断ち切っていたか否かは,職種によっても異なり,地域によっても異なった。しかし彼らが,村落共同体との結びつきを,程度の差はあれ弱めており,また鉱山の生活において文字通りの合理化,機械化,官僚性化といった近代化のインパクトに絶えずさらされ,丸山氏の言う〈個人析出〉の状況に置かれていたことは事実であった。
だが,ここから先は氏の結論にすぐ従うわけにはいかない。果して1900年代の鉱山労働者は〈原子化〉の傾向を集中的に表現しているであろうか? 丸山氏は1907年における鉱山労働者のたび重なる暴動の事実こそ彼らの〈原子化〉を立証している,と考えておられるようである。
「有名な足尾銅山や別子銅山の大暴動は欝積した労働者の不満がひきおこした連鎖反応であった。放火,建物の爆破,監督者の官舎の襲撃といった彼等の巨大な破壊力……それはもともと絶望的に原子化された労働者のけいれん的な発作であって,いかなる意味でも組織された労働運動を構成するものではなかった」という断言は,丸山氏が,〈暴動〉こそ労働者の「求心的・非結社形成的で他者志向的」な性格を示す指標と理解していることを示している。そこに描かれた労働者像は,旧来の通史的研究と同様に全く主体性を欠いている。むしろ丸山氏の労働者は主体性のなさでより徹底している。意思をもつ人間であるより,〈原子〉という言葉通り,外力によって動かされる無機物的存在に見える。
だが,はたして暴動とは,そのような特徴づけを許すものであろうか。何より疑問であるのは,ストライキはもちろん暴動といえども,それ自体は集団的な行動であって,「絶望的に原子化された労働者」の行動形態とは思えないことである。暴動の事実は,彼らが〈結社形成的〉であったことを示しはしても,〈非結社形成的〉であった証拠にはならないのではないか?
この疑問に答えるには,暴動にいたるまでの,また暴動における,労働者の行動を具体的に追跡して見るほかはないであろう。
【 注 】
(1) こうした規定は,従来の日本労働運動史,日本近代史,資本主義発達史に多く見られる。次章でとりあげる大河内一男氏はその典型的な例であるが,その他にも同様の見解の方は少なくない.たとえば小山弘健『日本労働運動史』(社会新報,1968年)はつぎのように述べている。
「しばしば闘争が暴動のかたちになっていったことは,組合がなく,労働者によって指導も組織も,また正しい交渉の方法もとれなかったからである。しかし,奴隷的な労働条件,当然の民主的権利の抑圧,半封建的な身分的圧制などのもとで,労働者が不満のはけ口を求めて,爆発的なエネルギーをもって起ちあがるのは当然であった」(同書18ページ)。
(2) 丸山真男稿,松沢弘陽訳「個人析出のさまざまなパターン──近代日本をケースとして──」(マリウス B. ジャンセン編,細谷千博編訳『日本における近代化の問題』 岩波書店,1968年 所収)。
なお,労働史研究者ではない丸山真男氏を批判の対象にしたのは何故かという疑問は,ご本人をはじめ何人かの方から提起された。私としては,日本の社会科学者のなかで経済主義とはもっとも縁遠いところにいる丸山真男氏においてさえ,本稿に引用したようなきわめて素朴な労働者認識,労働運動理解がいささかの疑問もなく展開されていることを重視し,これを批判することに積極的な意味を見いだしたのであった。「本書の内容紹介、注1」参照
(3) たとえば,鉱山や重工業の労働者は縁故によらずに,募集人が「農村の大量の遊休労働力の中から〈手あたり次第に〉引き抜いてきたものか,さもなければ自然に流れ込んで来る浮浪人口の中から採用されたもの」とされるのは,事実に反する。男子労働者の場合でも,地縁,血縁が大きな役割を果たしたことは明かである。これについての詳細は本書第2章補論(1)「飯場頭の出自と労働者募集圏」を参照いただきたい。また1900年代において,経営者が「ほとんど無限に調達できる労働力に依存して安定した持続的な労働関係を維持しようとする配慮を全く欠いていた」とするのも正確ではない。大経営では,長期勤続者に対する賞与や相互救済制度,強制的な積立金制度などはごく一般的に見られた。現に足尾でも勤続賞与や相互救済などは比較的早くから存在した。
(4) 丸山真男,前掲稿,372〜374ページ。
[初版は東京大学出版会から1988年5月10日に刊行]
[本著作集掲載 2003年10月8日,同10月9日,表現の一部を加筆訂正。論旨に変更はない]
【最終更新:
|