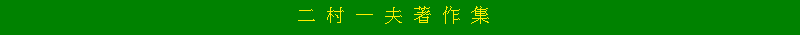第3章 足尾銅山における労働条件の史的分析(続き)
Ⅲ 製煉部門における技術進歩(続き)
4)生鉱吹の導入
生鉱吹実験開始
ベセマ法の成功にともない,熔鉱炉はもっぱら鉱石を熔解して,鈹の生産にあたるだけになった。しかし,それによって熔鉱炉の構造そのものには変化は生じなかった。ただ,1890年代から1900年代にかけ,しだいに炉の大型化が進み,炉の数は減少した。吹床全廃直後の1891年には,本山製錬所に8座,小滝製錬所に5座の計13座があり,これが洋式炉の炉数のピークであった。1893年,ベセマ転炉の導入と同時に本山製錬所の熔鉱炉4座がとりこわされ,かわって従来よりひとまわり大きい熔鉱炉2座が建設された。後にはさらに大型の炉がつくられたので,ここでは中型と呼んでおこう。中型炉も小型炉と同じ一部水套式長方形熔鉱炉で,その大きさは羽口レベルの内法で2.24メートル×84センチ,羽口数は18個(後では14個)であった。小型炉より長辺で74センチ増,短辺では4センチの増に過ぎなかったが,1昼夜の鉱石熔解量は小型炉の2倍から3倍近い6,000貫から8,000貫に達した(39)。
ついで1897(明治30)年8月,小滝製錬所が廃止され,当時4座あった小型熔鉱炉のうち1座が本山に移築され,あとは取り壊された。これは,同年6月の鉱毒予防命令により,両製錬所に亜硫酸ガス除去装置を取り付けることが要求されたことによるものであった。指定された短い工事期間に,小滝と本山の2箇所に脱硫塔を建設することは困難であり,その負担を軽減するため,小滝製錬所の廃止を決定したものであった。ベセマ転炉の操業が軌道に乗り,熔鉱能力に余裕が生まれていたことが,こうした決定を可能にしたのである。この,小滝製錬所の小型熔鉱炉移築と同時に,中型炉1座が新設された。これは,小滝製錬所の廃止とは無関係で,新たな実験にとりくむため設けられたものであった。鉱石を焙焼せずに熔鉱する生鉱吹が,その実験テーマである。生鉱吹は,いわばベセマ錬銅法の熔鉱版で,外部燃料を大量に使うことなく,鉱石自体にふくまれている硫黄や鉄の酸化熱によって鉱石を熔解する方法で,自熔製煉と呼ばれるのはそのためである。生鉱吹に成功すれば,製煉コストに大きな比重を占める熔鉱炉の燃料費を大幅に節減し,さらに製錬所の構内で広い空間を占拠し日数もかかるストール焙焼や,人手と燃料を要する反射炉焙焼を全廃することも可能であった。この銅の自熔製煉法は,1878年に,イギリスのジョン・ホルウェーによって発明されていたが,その実用化に成功したのは1890年代にはいってからである(40)。日本では,1900年に小坂鉱山で成功し,小坂銀山を銅山として再生させたことで知られている。足尾でも,小坂とほぼ同時,1897(明治30)年末か,98年1月に実験を開始したのである(41)。
1900年まで,実験は装入物の種類や構成を変え,また送風圧や風量,さらには送風を予熱し230度から300度Cの熱風とするなどして,断続的におこなわれたが,見るべき成果はあがらなかった。装入物は生塊鉱,石灰石,コークス,それに転炉鍰や熔鉱鍰を主とし,これに生粒鉱,生粉鉱,煙灰,生鈹などが加えられた。難問はやはり粉鉱で,生鉱吹では,粉鉱の比率が増すと熔解不良が生じ,故障が続出した。とくに羽口がふさがって,送風が炉内にとどかず,操業中止に追い込まれることがしばしばであった。送風を熱風に代えればこの事故はあるていど減らせたが,予熱に大量の燃料を要した上に,熱風機の故障が頻発し,成績はあがらなかった。そこで,粉鉱や粒鉱を加えず,塊鉱だけを装入して実験がおこなわれた。この場合は,コークスを対鉱石比(重量)で23%前後加えれば,熔解は比較的スムースに進行した。しかし焼鉱を熔解する場合のコークスの所要量は17.5%から20%であったから(42),これでは生鉱吹本来の目的である燃料消費の節減にはならなかった。しかも,製出された鈹の品位が28〜29%と,焼鉱の場合の55%前後に比べ著しく低かった。このように粉鉱の処理ができず,濃縮率も2倍に達せず,しかも燃料消費が増大するのでは,とても実用にはならなかった。このため,足尾のように鉄分や硫黄分の少ない鉱石では生鉱吹は困難であるとして,実験は一時中断された。
しかし,1902(明治35)年,鉱石焙焼用のストールの大修理が必要となり,焼鉱の不足を生じたため,余儀なく生鉱吹実験が再開された(43)。はじめは満足すべき結果は得られなかったが,同年12月4日からの第3回実験では,コークス比率16.3%,鈹の品位36%とやや成績が向上した。これは,従来の口径3インチの羽口を4インチに拡大して風量の増加をはかるとともに,凝結を防ぐために羽口から石炭を装入した結果であった。この羽口々径の拡大,羽口からの石炭の装入は,いずれも小坂鉱山で開発された技術で,これによって足尾における生鉱吹実験は大きな壁を越えたのであった。
一方,この間にベセマ錬銅の操業技術が進歩し,処理可能な鈹の品位が,当初の60%から39%程度にまで低下したこともあって,足尾における生鉱吹はようやく実用化の段階に近づいた。さらに1903(明治36)年5月,生鉱吹専用の大型炉が建設された。この炉は,羽口レベルの内法が506.5センチ×100センチと,従来の小型炉の4.2倍,中型炉の2.7倍もの面積を有し,1昼夜の熔鉱量も1万貫から1万2000貫に達した(44)。羽口の口径は6インチ,その数も24個と多く,送風量の増大をはかっていた。生鉱吹では,小型炉より大型炉の方が好成績であることも,小坂での経験から学んだものであった。これ以後,足尾でも急速に生鉱吹が熔鉱の主流になり,3年後の1906(明治39)年7月には,焼鉱吹は完全に廃止され,すべて生鉱吹に切り替わったのである。この年,コークス比率も17%台にさがり,1909年上期には10.8%にまで低下した。
【注】
(39) K.Denawa " Report on the Metallurgical Works of Ashio Copper Mine" 1904, p.92,東京大学工学部金属工学研究科図書室所蔵。
(40) 真継義一郎『銅冶金術』(大阪化学商議所,1904年)116〜130ページ。
(41) 古河鉱業株式会社『創業100年史』148〜151ページ,および同書が依拠したと思われる「足尾銅山製煉所沿革」(『栃木県史』史料編・近現代九所収)は,足尾銅山における生鉱吹実験の会誌を1900(明治33)年頃のこととしている。しかし,1897年に足尾銅山で実習をおこなった崎川茂太郎は,同年,生鉱吹のための熔鉱炉が新設されたことを報告している(M.Sakigawa " Report onCopper Metallurgical Work at Ashio Copper Mine",1898年,pp.90〜91)。
実際に生鉱吹実験が開始された時期については,1897年末と1898年1月の2つの異なった記録がある。1897年末説は出縄維則の実習報告(K.Denawa " Reporton the Metallurgical Works of Ashio Copper Mine" 1904, p.127)と『明治工業史・鉱業篇』(日本工学会,1930年,486ページ)である。一方1898年1月説は,久永正治の実習報告( S.Hisanaga " Ashio Copper-smelting Works" 1903年,p.182)および大河原三郎の実習報告,『足尾銅山冶金報告』1907年)である。とくに,久永は,実験の開始日を「明治31年1月27日」と明記している。いずれにせよ,足尾銅山で生鉱吹実験の準備が始められたのは1897年中であることは確実である。
(42) コークス所要量の対鉱石比率は,焼鉱については前掲崎川茂太郎実習報告書78,85ページによる。生鉱については出縄維則実習報告書128ページによる。なお,この数字は通常操業における装入物の構成比であって,そのまま熔解鉱量に対する燃料消費比率を示すものではない。炉の修理後の〈吹き入れ〉,あるいは何等かの故障で操業を一時中止したあと再開する時などには,大量の木炭やコークスを消費するから,実際の燃料消費比率はこれより高くなる。1896年においては,中型炉の燃料消費は,対鉱石重量比で約30%,小型炉では48.3%に達している(崎川茂太郎実習報告書70ページ)。この他にも,鉱石の焙焼や蒸気機関の運転にも薪や石炭を使い,頻繁に修理を要する前炉や転炉の乾燥にも木炭が使われた。
(43) 大河原三郎『足尾銅山冶金報告』119〜124ページ。なお,前掲出縄報告書,久永正治報告書,『明治工業史・鉱業篇』も参考にした。
(44) 前掲,出縄維則実習報告書91〜92ページ。
[初版は東京大学出版会から1988年5月10日刊行]
[本著作集掲載 2006年3月16日]
【最終更新:
|