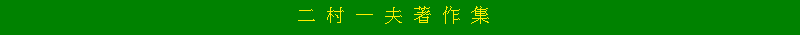第3章 足尾銅山における労働条件の史的分析(続き)
Ⅳ 製煉部門の技術的変化と労働力構成(続き)
2)熔鉱労働の量的変化
これまで,主として熔鉱労働の質的変化を見てきた。次は,その量的側面について検討を加えたい。
人力送風による吹床の段階──1877〜1884
1877(明治10)年,古河が足尾の操業を引き継いだ時の製煉労働者の数は明かでない。しかし,吹床は2座であったとされており(31),吹床の所要人員には一定の標準があったから,推計は可能である。箱鞴使用の吹床では,吹大工1人,前大工1人,それに鞴人夫が1挺につき2人ついた。鉱石から鈹をとる寸吹床では鞴は2挺,鈹から粗銅を製出する真吹床では鞴1挺を用いた。したがって,古河の足尾操業当初の製煉労働者の数は,吹大工が2人,前大工が2人,鞴人夫は6人から8人であったと推定される。翌78年,吹床1座が増設され,79年から1882(明治15)年までにさらに5座が新設された。したがって1879年のはじめでは本大工3,前大工3,鞴人夫10〜12の計16〜18人であり,82年末では吹大工8人,前大工8人,鞴人夫28人前後となる。ただし,82年ではまだ箱鞴を使用し,吹床の数は寸吹床6座,真吹床2座と仮定しての数字である。月日は不明だが,82年に送風は箱鞴から革鞴に代わっている。この改良によって,鞴人夫は吹床1座につき3人となり,寸吹床,真吹床の区別はなくなった。したがって鞴人夫の所要人員は24人となる。
以上はいずれも吹床数から算出した人員である。吹大工は「吹床の主監者」としての性格からみて吹床数と一致したであろうが,前大工は将来の拡張のための要員を,鞴人夫は欠勤者が出た際の予備人員を必要としたであろうから,実数はこの推計値を上回ったに違いない。
1883年については,すでにしばしば利用した「明治十六年分砿業景況取調書」に,「製煉夫 貳百貳名」との記録がある。しかし,この年の吹床数は14座であり,これから推計される吹大工は本大工14人,前大工14人の計28人,鞴人夫42人で,その合計は70人である。「砿業景況取調書」のいう〈製煉夫〉のなかには焼鉱夫や選鉱夫まで含まれているとしか考えられない。事実,この年の初冬の概況として『鉱業雑誌』が伝えるところでは「吹大工十一名,焼鉱炉掛六名」となっている(32)。
推計でなく,製煉労働者の実数を記録しているのは,1884(明治17)年8月下旬に足尾を調査した大原順之助の報告書である(33)。それによれば,広い意味での製煉関係労働者の職種別人員は,焼鉱夫70人,土竃夫54人,熔鉱夫60人,吹夫90人の計274人である。「砿業景況取調書」の数値と比較するため,これに〈撰鉱夫〉の100人を加えると,合計は374人となる。焼鉱夫と土竈夫はともに鉱石や鈹の焙焼作業に従事している労働者である。焼鉱夫は洋式の反射炉で働くもの,土竈夫は旧来の土竃で焼鉱や焼鈹に従事するものとみてよい。熔鉱夫60人は,本大工30人,前大工30人の合計であろう。吹夫は鞴人夫である。この時点で,吹床の数は30座,すべて革鞴で送風するものである。さきに見たとおり,洋式の革鞴の操作に必要な人員は1座3人,吹床は1座につき本大工1人,前大工1人であるから,30人,30人,90人という数は,吹床数とちょうど合致する。しかし,これらがいずれも端数を欠くのはいささか不自然で,おそらく在籍労働者の実数でなく,吹床など設備面から算出した標準的な所要人員であろう。
動力送風による吹床の段階──1884〜1890
大原順之助が足尾を視察した直後の1884(明治17)年11月,水車を動力とするルーツ式ブロアー2基が32座の吹床に送風を開始した。ただし,86年までは〈直利橋製錬所〉内に16座,本山地区に17座の革鞴使用の吹床も同時に稼働していた。また,1887年からはピルツ炉の,88年からは一部水套式長方形熔鉱炉の実験操業が始まり,90(明治23)年末には吹床は全廃された。したがって,この動力送風による吹床の操業期間は約6年と短く,しかも常に他の形式の炉と併用されている。文字通り,過渡的な存在である。ところで,この時期の熔鉱労働者については4種のデータが残っている。
その1つは「明治十七年砿業景況取調書」で,製煉夫は539人と記録されている。この数字は前年の「明治十六年砿業景況取調書」の202人と比較が可能で,この間に製煉関係労働者が2.7倍と,急激に増加したことがわかる。ただ,再三述べたように,この〈製煉夫〉の中には選鉱夫や焼鉱夫などが含まれている。年次は異なるが,より詳細な職種別の内訳がわかるのは,1885(明治18)年8月現在の原田慎治の視察報告である。原田は「製鉱〔製煉〕ニ関スル使役夫」としてつぎのような20職種をあげている。熔鉱夫88,仝手伝84,焼鉱夫86,鍛冶2,機関方2,普通人夫65,鉱物運搬夫25,焼鉱冷却夫4,焼鈹運搬夫25,粘土運搬夫14,銅貫監4,焙焼鉱送夫13,衣艸拾夫1,水道番1,馬丁23,牛夫33,馬夫23,車夫64,車大工4,運送夫30,合計604。この記録は,直接吹床の前に立って製煉作業に従事する吹大工などの背後に,実に多種多様な労働者がいたことを示している。目を惹くのは運搬労働者が多いことで,20職種中9職種を占め,小計263人と全体の43.5%に達している。ただ,彼等は職種区分からすると製煉夫というより雑役夫に区分されるべきであろう。熔鉱夫,焼鉱夫につぐ多数を占める普通人夫は熔鉱夫や熔鉱夫手伝の補助労働者であると思われる。鍛冶は吹床で使う鉄道具の修理にあたる者,機関方は水車およびルーツ式送風機の運転・保守係とみてよい。動力に蒸気機関が使われるようになるのは,この年11月からであるから。銅貫監は製出された粗銅の計量係,水道番は水車用の水路の監視人である。わからないのは衣艸拾夫である。あるいは焼鉱の際,鉱石の上を覆う草や藁を集める仕事をしていたのでないかと想像されるが,確かではない。1886年については8月現在の「栃木県足尾銅山点検報告(34)」と会社所蔵の「事務的調査書類(35)」の2つの記録がある。以上をまとめたのが,つぎの第23表である。
第23表 吹床時代の製煉関係労働者職種別人員推移
| | 1877年 | 1878年 | 1882年 | 1883年 | 1884年8月 | 1884年 | 1885年8月 | 1886年8月 | 1886年 |
|---|
| 本大工 | (2) | (3) | (8) | (14) | 30 | | 44 | 287 | 113 |
|---|
| 吹大工 | (2) | (3) | (8) | (14) | 30 | | 44 | 72 |
|---|
| 鞴人夫 | (6) | (10) | (28) | (42) | 90 | | 84 | 0 |
|---|
| 焼鉱夫 | 0 | 0 | 0 | ? | 70 | | 86 | 87 | 90 |
|---|
| 土竃夫 | ? | ? | ? | ? | 54 | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| その他 | ? | ? | ? | ? | ? | | 346 | ? | ? |
|---|
| 合 計 | | | | 202 | | 539 | 604 | | |
|---|
【備考】
1) ( )内は推定数。
2) 1883年及び1884年の合計数には選鉱夫を含むと見られる。なお、1884年8月現在の選鉱夫数は100人である。
3) 1886年8月の熔鉱夫287人の中には、雑役夫なども含まれていると見られる。
洋式熔鉱炉導入後
洋式熔鉱炉が吹床を完全に追放したのは1890(明治23)年である。直利橋製錬所の吹床48座とピルツ炉3座が,小滝製錬所でも吹床32座が廃止され,いずれも一部水套式長方形熔鉱炉8座と5座が新設された。残念ながら1890年代前半の熔鉱労働者の人数がわかる記録はない。ただ,すでに見たように,1898年現在の小型炉の所要人員は1シフトあたり炉前夫2人,装入夫2人,鍰運搬夫1人,雑役夫1人であった。この所要人数が1890年でも同じであったとすれば,小型炉13座,1日2交代の総所要人員は炉前夫52人,装入夫52人,鍰運搬夫26人,雑役夫26人,合計156人である。製煉夫と呼ばれたのは炉前夫と装入夫であるから,その数は104人。ただし,これは最低所要人員であるから,若干の予備人員を考慮すると110人程度であろう。洋式熔鉱炉導入直前の製煉夫の正確な人員はわからないが,吹床72座に必要な吹大工は144人,ピルツ炉3座が仮に小型長方形炉と同じであったとすれば,炉前夫12人,装入夫も12人,総計で168人である。単純に比較しても製煉夫64人が余ることになる。実際には,吹大工の熟練は洋式熔鉱炉ではほとんど役に立たなかったから,職を失ったものの数はこれを大きく上回ったであろう。
1895年以降になると製煉夫数の記録はかなり残っている。それをまとめたのが次の第24表である。参考までに製煉夫1人あたりの熔解精鉱量と産銅高を附した。この作表に用いた資料の性格は多様だが,この時期になると,製煉夫と呼ばれたのは熔鉱炉・熔鈹炉の炉前夫と装入夫,それに転炉の炉前夫に限られていた(36)から,十分相互に比較可能な数字である。
第24表 洋式熔鉱炉製煉夫数,能率推移
| 年次 | 製錬夫(A) | 熔解精鉱量(B) | 産銅量 | B/A | C/A |
|---|
| 1895(明28)年 | 121人 | 6,076 | 4,898 | 50.2 | 40.5 |
|---|
| 1896(明29)年 | 144 | 7,564 | 5,861 | 52.5 | 40.7 |
|---|
| 1900(明33)年 | 105 | 10,963 | 6,077 | 104.4 | 57.9 |
|---|
| 1901(明34)年 | 111 | 11,462 | 6,320 | 103.3 | 56.9 |
|---|
| 1902(明35)年 | 117 | 11,855 | 6,695 | 101.3 | 57.2 |
|---|
| 1906(明39)年 | 103 | 13,644 | 6,735 | 132.5 | 65.4 |
|---|
【備考】
1) 各項目の単位は、製錬夫は「人」、熔解精鉱量は「千貫」、産銅量は「トン」、B/Aは「千貫」、C/Aは「トン」。
2) 1895年の製錬夫数は『栃木県史』史料編・近現代九、491ページ。1896年は高岩安太郎『足尾銅山景況一斑』、
1900年は『上山達三実習報告書』、1902年は蓮沼叢雲『足尾銅山』、1906年は『大河原三郎実習報告書』による。
3) 熔解精鉱量は1895年、96年は『崎川茂太郎実習報告書』、他は「足尾銅山製煉所沿革」『栃木県史』史料編・近現代九、124〜125ページによる。
4) 産銅量は古河鉱業会社『創業100年史』82ページによる。
この表で注目されるのは,1896年と1900年との間にある大きな変化である。その1つは,製煉夫数の大幅減少であり,第2には製煉夫1人あたりの熔解精鉱量の倍増である。製煉夫の減員は,絶対数では40人足らずでしかないが,比率にすると27%強である。この減少の理由の1つは,1897年8月の小滝製煉所の廃止であろう。廃止の直接の原因は同年6月の第3回鉱毒予防命令の第30項にあった。
「本山及小滝に於ける製錬所の各烟突は烟道を以て之を連絡し,烟室を設けて亜砒酸及烟煤を凝結降沈せしめ,且硫酸製造又は其他脱硫の方法を以て亜硫酸瓦斯を除却したる後,製錬所背後の山腹より更に大烟道に依り山頂指定の地に至り,本山に於ては高さ八十尺,小滝に於ては仝五十尺以上の烟突を設け噴煙せしむへし(37)」。
この,いわゆる〈脱硫塔〉建設は,予防工事の中でももっとも難工事が予想された。この負担を軽くするため,小滝製煉所を廃止し,本山だけの工事にとどめたのであった。それが可能であったのは,ベセマ転炉の操業技術の向上によって,熔鉱炉は製鈹に集中し得るようになり,また炉容の大型化によって熔鉱能力に余裕が生まれていたからである。
製煉夫が減少したもう1つの理由は,古河がこの鉱毒予防工事命令を機に,経営組織を再編し,同時に従業員の危機感を利用してコストの削減をはかったことである。具体的には,従来100斤あたり17円92銭8厘であった産銅コストを全体で17円まで切り下げることを目標に,製煉コストは従来の100斤あたり5円9銭1厘を4円83銭1厘とすることを指示したのである。20項目におよぶ経費節減策の中には「各工場ヲ通シテ職工ノ員数ヲ制定シ,制限外ノ職工ヲ一切使用セサル事」,「職工ハ総テ厳重ノ秩序ヲ以テ使役シ,苟モ怠惰又ハ風紀ヲ乱サヽル様督励ノ事」が含まれていた(38)。こうした,経営政策の転換も,製煉夫減員の背景にあったことは確かである。
製煉夫1人あたりの熔解精鉱量が倍増したことは,製煉夫の大幅減員にもかかわらず,産銅量が増加したことに1つの理由がある。それと同時にベセマ転炉の導入により,熔鉱炉はもっぱら鉱石の熔解に集中するようになり,かつてのように,鉱石と鈹とを同時に熔解することがなくなったことも,この数字に反映していよう。
第24表でもう1つ注目されるのは,1906年の製煉夫1人あたりの能率の向上である。1902年と比べ,熔解精鉱量で30%余,産銅量で15%近い増加を示している。これは,おそらく生鉱吹の成功によるものであろう。
【注】
(31) 「足尾銅山製煉所沿革」には,「古河市兵衛氏ノ所有ニ帰シタルノ当時ハ,本山ノ鷹ノ巣沢ト本口沢,出合沢近傍ニ於テ,旧式吹床二座(凡ソ三百貫吹キ)及焼鉱土竈(凡ソ三百貫焼)十五枚,現存セルノミナリシガ」(『栃木県史』史料編・近現代九,109ページ)と記されている。この記述は何に依拠したものか明かでないが,いささか疑問がある。それは,1877年3月15日に,古河が前借区人・副田欣一から引き継いだ建物等の目録には,本山出沢に鎔鉱所1棟(鞴4挺附属),宿に鎔鉱所3棟(製吹,荒吹,丁銅吹用),簀子橋に鎔鉱所1棟(鞴2挺等附属)の計5棟の鎔鉱所が含まれていたことである(古河鉱業株式会社『操業100年史』54〜55ページ)。ただ,建物は引き継いでも実際に使用したのは本山の1棟だけであったとも考えられるのと,産銅量からみると2座か3座の能力で充分なので,ここでは「足尾銅山製煉所沿革」の記述にしたがっておく。
(32) 《日本鉱業史料集》第1期明治篇④『足尾銅山概況等』3ページ。
(33) 『工学会誌』第34巻(1884年10月25日)。
(34) 『栃木県史』史料編・近現代九,14ページ。
(35) 『日本労務管理年誌』第一編(上),209ページ。
(36) この時期には〈古河足尾銅山鉱夫使役規則〉が制定され,職種毎の「鉱夫等級賃金表」によって賃金が支払われていた。〈鉱夫使役規則〉によれば,熔鉱夫とは「鉱物熔解錬銅ノ業ニ使役ス」るものであった(『足尾銅山図会』31ページ)。
(37) 足尾銅山古河鉱業所『足尾銅山予防工事一班』(1898年,7ページ)。
(38) 『日本労務管理年誌』第一編(上),附録重要参考史料,87ページ。
[初版は東京大学出版会から1988年5月10日刊行]
[本著作集掲載 2006年4月3日]
【最終更新:
|