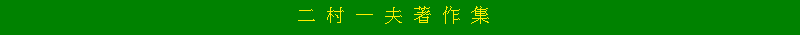第3章 足尾銅山における労働条件の史的分析(続き)
Ⅵ 坑夫の賃金水準の推移(続き)
3)開坑・採鉱労働の質的・量的変化
最後に足尾坑夫の賃金水準の変化をより長期的に検討しておこう。さきに問題点の第3としてあげたことである。すなわち,1880年代の前半にはどの産業,どの職種と比べても群を抜く高水準にあった足尾坑夫の賃金が,1890年代から1900年代半ばまで,名目では横ばいか僅かな上昇にとどまり,実質で低下したのは何故かということである。
この問題に答えるには,次の3点について検討する必要があろう。第1は足尾坑夫の賃金水準が1880年代前半で群を抜いた高さにあったのは何故かということ,第2に,1890年代から1900年代にかけて実質賃金が低下傾向をたどったのは何故かということ,第3に,とはいえ同じ足尾の製煉夫賃金が名目においてさえ低下したのに,坑夫の場合は名目賃金は僅かにせよ上昇,あるいは横ばいであったのは何故かということである。
開坑・採鉱労働の質的変化
第1点についてはすでに検討した。第2点についてもすでに答えは出ている。
そこで,問題は坑夫賃金の水準の変化が,製煉夫など足尾の他職種の賃金水準とは違った動き方をしたのは何故かということになる。この疑問を解くには,開坑・採鉱労働の変化を,質量の両面で検討しなければならない。
採鉱・開坑作業でまず問題となるのは火薬使用の有無である。これまで,ともすれば,開坑・採鉱作業は鑿岩機の導入までは手工的段階にとどまっていたから,そこでは徳川時代と比べほとんど技術的進歩がなかったかの如き見解が主張されているが,これは妥当ではない。開坑作業での火薬の使用こそ,日本の鉱山業が徳川時代の停滞を脱却して,再生し得た決定的な要因であった。そして,この火薬の使用は坑夫の労働の質を変化させずにはおかなかったのである。その具体的様相はあとで見ることにして,まず足尾での火薬使用の状況を確認しておこう。
1877(明治10)年,古河が足尾の操業を開始した時,開坑・採鉱作業に火薬を使用したか否か,はっきりした記録はない。しかし,同年,同じ古河が経営する草倉銅山で火薬が使用されていたことは確実である。すなわち東京大学理学部採鉱冶金学科を卒業した理学士,原田慎治は,1885(明治18)年に草倉を視察し,その報告を『日本鉱業会誌』に発表しているが,そこには次のような記述がある(25)。
「採掘法ハ明治十年以来専ラ官行鉱山ノ法ニ做ヒ,姑息ノ竹管導火ヲ廃シ西洋導火ヲ用ヒ,又和鉄ノ鑿鎚ヲ廃メ西洋ノ鋼鉄ヲ用ユル等,漸次用法ヲ改良ス。明治十四年ニ至リダイナマイトヲ使用セシニ大イニ当山ノ石質ニ適シ,其効験火薬ニ三倍シ,現今ダイナマイト及火薬ヲ併用スト雖トモ寧ロダイナマイト其多キニ居レリ。其比較左ノ如シ。旧坑道ニシテ火薬及竹管ノ導火ヲ用ヒシトキ,堅石採掘量一日一人一トスルトキハ坑道ヲ切拡ゲ専ラ改良シ,火薬ヲ用ヒシトキ其一倍半トナル,又ダイナマイトヲ用ヒシトキ尚ホ前上ノ一倍半ニ当レリ」。
同じ古河経営の鉱山であり,技術者や坑夫も草倉から移動しているから,当然,足尾でも古河経営の当初から,火薬はもちろん洋式の導火線やダイナマイトも使用されたに違いない。足尾銅山における火薬使用が一次史料で確認できるのは1882(明治15)年のことで,市兵衛が木村長兵衛宛書簡で,ダイナマイトをもっと多用するよう勧めている(26)。採鉱現場での実際を伝えているのはすでにしばしば引用した大原順之助の「足尾銅山現況」で,1885年当時の状況をつぎのように述べている(27)。
「鉱石ヲ採掘スルニ,先ズ下磐 (粘土 (粘土 )ヲ掘鑿シ,便宜ノ距離ニテ支道(合背五,三)ヲ止磐 )ヲ掘鑿シ,便宜ノ距離ニテ支道(合背五,三)ヲ止磐 ニ通シ,鉱脈ニ逢フニ至リ左右ニ掘進ムナリ。其法ハ略ホ掘上リニテ,岩石破壊ニハ径六分ノ鋼銕製八角鑚ト手鎚トヲ以テ穴ヲ穿チ,焔硝ヲ用テ破裂ヲ行フヲ常慣トス。然トモ岩面割條ニ乏シク,非常ニ硬堅ナルカ若クハ湧水多キトキハ,焔硝ニ代ルニダイナマイトヲ以テス」。 ニ通シ,鉱脈ニ逢フニ至リ左右ニ掘進ムナリ。其法ハ略ホ掘上リニテ,岩石破壊ニハ径六分ノ鋼銕製八角鑚ト手鎚トヲ以テ穴ヲ穿チ,焔硝ヲ用テ破裂ヲ行フヲ常慣トス。然トモ岩面割條ニ乏シク,非常ニ硬堅ナルカ若クハ湧水多キトキハ,焔硝ニ代ルニダイナマイトヲ以テス」。
もちろん,これは1885年に初めて火薬が使用されるようになったことを意味しない。それ以前から火薬が使われていたことは明瞭で,田代苗臣の「栃木県下足尾銅山点検報告」が,「〔明治〕十八年以降改良法ニ依リ便益ヲ起シタルコト(28)」として,同年ダイナマイトの点火に電気導火を用い始めたことを述べ,1884年以前にダイナマイトが使われていたことを示唆している。
火薬使用以前の採鉱・開坑作業は,岩石を掘り割り,〈はつり取る〉のが基本であった。坑道開鑿の場合は,採掘面をその掘鑿の難易によっていくつかの区画に分け,石目に応じて〈掛地法〉か〈仏壇法〉によって掘鑿した。〈掛地法〉は鉱脈のように縦に石目が発達している場合にとられる採掘法で,まず上部の区画を掘鑿し,そこから下部を割り取るものである。〈仏壇法〉は,岩磐が均質で石目に乏しいものに用いられる方法で,まず中央部を掘り取り(仕掛け,または心抜き)ここから左右,ついで下部,最後に上部と掘鑿していった。各区画は通常坑夫1方の作業量で,掘鑿面が石目に乏しく堅ければ分割数は数十にもなり,石目が発達して破砕が容易な場合は少なくてすむのである(29)。
これが火薬の使用とともに,開坑・採鉱とも火薬を装入するための孔くりが主となった。火薬装入用の孔は,岩石の硬軟,亀裂の多少などその性質,開口面の広狭などによっても異なったが,通常直径が30ミリ前後,深さは30センチから 60センチ程度である。
発破の順序は,坑道開鑿であれば,まず中央部に数本の孔をくり爆破させた。このあと上下左右に鑿孔して同様に火薬を詰め発破をかけた。点火には,最初は竹筒に黒色火薬をつめたものを使っていたが,すでに紹介した「草倉銅山記事」にあるように,すぐ洋式の導火線に変わっている。足尾では1885年から,ダイナマイトの点火には電気導火を用い,一時に数十発を爆破させるようになり,火薬の点火にも電気導火を使えるように改良を加えている。
掘鑿に使用する道具もとうぜん変化し,和鉄で出来た〈はつり〉作業用の鎚,鑚から,鑿孔用の鋼鉄製のタガネ,セットーと呼ばれる鋼鉄製の鎚へと変わった(30)。タガネは通常,刃先が一文字で三味線の撥状,柄の部分は八角形をしているものが用いられた。左手でタガネを保持し,右手で重さ1.5キロ程度のセットーをふるってタガネを打った。一打ごとにタガネを回転させ,刃の位置を変えることでくり孔を円形にした。ときどき孔に水を注いでは岩石の小片,細粉を除き,さらにキューレンと称する鉄製の大型の耳掻き状の道具で孔内の石屑を掻き出した。掘りすすむと,刃先がひとまわり小さく柄の長いタガネに代えて同様の作業をつづけた。作業現場が広い場合には,手子にタガネをもたせ,坑夫は両手を使って重さ4~5キロの玄翁を使う2人掘りがおこなわれた。〈2人掘り〉の方が作業効率はよく,また道具の損耗も少なかった。この鑿孔作業は,重筋肉労働であるだけでなく,かなりの経験・熟練を必要とした。さまざまな岩石の性質を知らねばならず,石目や石木目を見分け,どの部位にどのような角度で,どれほどの大きさ,深さに孔をくればよいかを判断しなければならなかった。
孔をくり終ると,火薬を木製の〈込棒〉を使って孔底に充填し,さらに導火線を差入れ,つぎに乾いた粘土などでこれをふさぎ,導火線に点火して爆発させた。火薬の分量の多少,詰め方の巧拙,爆発の順序なども発破効果に影響した。また岩石の性質を見分けて火薬を使うか,ダイナマイトがよいかの選択も必要であった。ダイナマイトは爆発力が強く,硬い岩でも破砕し,また湧水部でも使用できる利点はあったが,黒色火薬に比べ高価であった。どちらを選ぶかで所要経費に大きな差がでた。また火薬の詰め方や導火線のつなぎ方,点火が下手だと不発箇所を生じ,作業効率に響くだけでなく,生命の危険をまねいた。
いずれにせよ,開坑・採鉱に火薬を使用するだけでは,暗黒の坑内で,鎚と〈たがね〉を使っての重筋肉労働という坑夫の労働の基本的な性質は変わらなかった。岩石の性質や石の亀裂,石の節理を見分け,狭い場所で〈たがね〉を効率的に打つといった坑夫としての知識・熟練も火薬導入前と同じように役だった。しかし,かつては岩石をはつり取るため,さまざまな道具の使い分け,はつりの手順などさまざまな作業に習熟する要があったが,主たる作業が鑿孔になったことは,作業内容をいくらか単純化した。また支柱作業などはかつては坑夫の労働の一部であったが,経営規模の拡大にともない,専門職種としての支柱夫が分化し,それだけ坑夫の習熟すべき作業は減った。しかしその反面で,危険な火薬やダイナマイトなどの取り扱いに習熟し,効率的な発破箇所の選定,発破方法の選択なども学ばなければならず,その点では坑夫は新たな知識・経験・技能を要求されることになった。このように,金属鉱山坑夫の労働の性質は,火薬使用によって,1870~80年代に大きな変化を蒙ったのである。だがその後しばらくは,製煉労働のような急激な変化は生じなかった。もちろん,まったく採鉱技術に進歩がなかったわけではない。1890年代の後半に進展した〈抜き掘法〉から〈階段掘り法〉への転換は,採鉱現場である切羽の状況を変えた。これについては第2章でふれているので,再論は避ける。だが,〈階段掘り法〉の採用は,採鉱労働の性質そのものにはほとんど影響をおよぼすことはなかった。
鑿岩機導入の影響
しかし,採鉱とならんで坑夫の重要な職務であった坑道開鑿の場合,事情は違った。鑿岩機の導入によって,まったく別の職種が生まれ,それが少なくとも主要坑道の開坑については,手掘り坑夫の職務を奪っていったのである。足尾では,1885(明治18)年に官営払い下げによって入手したばかりの阿仁鉱山からシュラム式鑿岩機を運び,有木坑の開鑿に使用したのである(31)。鑿岩機の利用は当然のことながら開坑労働の性質を変えた。鑿岩機を使用するには,
まず坑外に圧気機(エアー・コンプレッサー)を据え,ここから作業現場まで鉄管をひく必要があった。現場では鑿岩機の据え付け台を設置し,これに機械をとりつけた。当時の鑿岩機は人力で保持するにはあまりに重かったのである。鑿岩機そのものの操作は1人でおこなったが,スタンドへの装着やタガネの交換,鑿岩機の移動は単独ではなしえなかった。またタガネ先を冷却し,掘鑿を容易にするために,鑿孔にたえず水を注入する必要があった。もちろん動力機や圧気機の運転,鑿岩機の整備・補修にも人手を要した。このため鑿岩機による鑿孔作業には思いのほか多数の人員を必要とした。足尾での要員数は不明であるが,同じシュラム鑿岩機を使った阿仁銅山の実績では,1チーム13人で作業をおこなっている。その職種別内訳は,坑夫頭1,器械方1,坑夫6,手子1,鍛冶2,車夫2である。1チームの作業時間は12時間であったが,各人の労働時間ははるかに短かった。というのは,この12時間は,機械の据え付けなど準備作業に1時間,鑿孔作業に5時間,発破に2時間,捨石運搬に4時間となっていたからである。車夫の実働時間は4時間,〈坑夫〉の労働時間は6時間から8時間ということになる。12時間の掘進量は高さ7尺,幅6尺の加背で50センチメートル,手掘り掘進の2倍強であった。
いままでは阿仁での用語にしたがって〈坑夫〉と呼んだが,鑿岩機を操作する労働者の労働内容は手掘りの坑夫=開坑・採鉱夫のそれとはまったく異質のものであった。手掘り坑夫の場合はすでに見たとうりタガネと鎚とを使っての孔くり作業が主で,その作業能率は本人の労働意欲と,岩石の性質を見分け,適切な部位に,適切な角度や大きさ・深さで鑿孔すること,火薬の装入の巧拙など,各人の能力や意欲にかかっていた。これに対し,鑿岩機を使用する〈坑夫〉,足尾銅山での呼び名で言えば〈進鑿夫〉の主な作業内容は,重い鑿岩機を数人の協同作業でスタンドに装着し,これを操作して孔をくり,孔の深さに応じてタガネを交換し,孔をくり終えれば鑿岩機を移動させ,といったことであった。もちろん鑿岩機の操作には熟練を要した。たとえば,岩の性質に応じ深さに応じて太さ,長さのちがうタガネに交換するというだけでも,一定の知識・経験が不可欠であった。適切な時期に交換しないとタガネが回転し難くなり,掘進できないばかりか,タガネが抜けなくなるといった事故をまねいた。しかし,作業能率は個人の意欲や能力だけでは決まらず,同じチームの労働者の力量によって,さらには鑿岩機,動力機,圧気機など機械類の好・不調によっても左右された。進鑿夫の賃金を手掘り坑夫のような出来高給にはしえず,基本的には固定給としたのもこのためであった。
だが製煉部門と違い,開坑・採鉱部門では,進鑿夫が坑夫の職場を奪うといった事態はすぐには生じなかった。1902(明治35)年10月現在でさえ,進鑿夫はわずかに24人,坑夫(徒弟を含む)2,737人の1%にも達していない(32)。開坑・採鉱作業で機械掘りが手掘りを上回るのは,これよりさらに22年後の1924(大正13)年のことである(33)。何故このように開坑・採鉱作業の機械化が遅れたかといえば,機械設備一式が高価であるうえに,経常費だけ比べても,人力掘鑿より割高だったからである(34)。また,技術的な制約から鑿岩機が大型で,しかも重かったから,その移動に人手を要しただけでなく,開口部の大きい主要坑道の掘鑿にしか使用し得なかったからである(35)。そうしたマイナス面にもかかわらず鑿岩機が使用されたのは,なによりその掘進速度にあった。鑿岩機が導入されたばかりの1880年代前半で手掘りの2倍から3倍,さらに1890年代になると機械の操作に習熟し,さらに能率は向上した。また,手掘りでは歯がたたないような堅い岩でも,鑿岩機は鑿孔できること,さらに,鑿岩機の動力には圧搾空気を用いたから,通気不良箇所でも作業が可能であるという利点があった。通風困難,排水・運搬問題など,さしせまった障害を解決するための坑道掘鑿では,なにより短期間で完成させ得ることが,長期的にみれば,コスト面でも有利だったからである。
開坑・採鉱労働の量的変化
つぎは,開坑・採鉱労働の推移を,量の面でみてみよう。ここでも,賃金の場合と同様に,坑夫数に関する資料が残っているのは1880年代と1900年代に限られている。ただ,熔解精鉱量が全年次について明かであるのと,採鉱量についても一部の年を除きわかっているので,坑夫数を推定することは不可能ではない。つぎの第36表がその結果である。
第36表 足尾銅山坑夫数推移
| 年次 | 坑夫数 | 推定
坑夫数 | 採鉱量 | 熔解
精鉱量 | 坑夫1人
当精鉱量 |
|---|
一番
粗鉱 | 二番
粗鉱 | 計 |
|---|
| 1877(明10) | 120 | | | | | | |
| 1878(明11) | | | | | | | |
| 1879(明12) | | | | | | 10.7 | |
| 1880(明13) | | | 12.5 | - | 12.5 | 11.1 | |
| 1881(明14) | | | 26.0 | - | 26.0 | 26.7 | |
| 1882(明15) | 136 | | 33.0 | | 33.0 | 34.6 | 2,544 |
| 1883(明16) | 330 | | 99.8 | - | 99.8 | 81.8 | 2,479 |
| 1884(明17) | 750 | | 339.0 | - | 339.0 | 267.9 | 3,572 |
| 1885(明18) | 933 | | 375.0 | - | 375.0 | 457.8 | 4,907 |
| 1886(明19) | 1,231 | | 406.0 | - | 406.0 | 392.4 | 3,188 |
| 1887(明20) | | 1,288 | 453.0 | - | 453.0 | 399.3 | |
| 1888(明21) | | 1,815 | | | | 562.8 | |
| 1889(明22) | | 1,989 | | | | 616.7 | |
| 1890(明23) | | 2,258 | | | | 648.3 | |
| 1891(明24) | | 2,166 | | | | 723.1 | |
| 1892(明25) | | 2,118 | | | | 656.5 | |
| 1893(明26) | | 1,873 | | 950 .0 | | 580.7 | |
| 1894(明27) | 1,876 | | 1,330.0 | 2,130.0 | 2,250.0 | 615.9 | 3,283 |
| 1895(明28) | | 1,960 | 1,190.0 | 2,100.0 | 3,320.0 | 607.6 | |
| 1896(明29) | 2,854 | | 1,480.0 | | 3,580.0 | 756.4 | 2,650 |
| 1897(明30) | | 2,928 | | | | 731.9 | |
| 1898(明31) | | 2,753 | | | | 1,128.8 | |
| 1899(明32) | | 2,655 | | | 3,082.0 | 1,088.5 | |
| 1900(明33) | 2,405 | | | 3,001.0 | 3,301.0 | 1,096.3 | 4,558 |
| 1901(明34) | 3,053 | | 1,165.0 | 2,757.0 | 4,266.0 | 1,146.2 | 3,754 |
| 1902(明35) | 2,737 | | 1,159.0 | 2,574.0 | 3,951.0 | 1,185.0 | 4,331 |
| 1903(明36) | | 3,070 | 1,298.0 | 3,233.0 | 3,906.0 | 1,258.7 | |
| 1904(明37) | | 2,926 | 1,184.0 | 4,240.0 | 4,451.0 | 1,199.8 | |
| 1905(明38) | 3,360 | | 1,094.0 | 4,787.0 | 5,372.0 | 1,269.1 | 3,777 |
| 1906(明39) | 3,358 | | 1,111.0 | | 5,945.0 | 1,364.4 | 4,063 |
【備考】
1) 坑夫数は以下の史料による。
① 1877年は古河鉱業株式会社『創業100年史』58ページ。
② 1882年は『古河市兵衛翁伝』手柬篇20ページ。
③ 1883年、85年、94年は『栃木県史』史料編・近現代九、8ページ、25ページ、491ページ。
④ 1884年は『工学会誌』34巻
⑤ 1886年は『日本労務管理年誌』(上)209ページ。
⑥ 1896年は『足尾銅山景況一班』
⑦ 1900年は上山達三実習報告書18ページ。
⑧ 1901年は『足尾銅山図会』
⑨ 1901年は蓮沼叢雲『足尾銅山』
⑩ 1905年は『栃木県史』通史編八621ページ。
⑰ 1906年は『坑夫待遇事例』。なお、坑夫数に関するデータはこの他にもあるが、手子・掘子等を含んだものはとらなかった。
2) 採鉱量は以下の史料による。
① 1880年、85年、86年は『木村長兵衛伝』51ページ、89ページ。
② 1881年、87年は『栃木県史』史料編・近現代九147ページ、150ページ。
③ 1882~84年は『古河潤吉君伝』34ページ、40ページ。
④ 1894~96年は木部一枝実習報告書8ページ。
⑤ 1899年、1900年は細谷源四郎実習報告書265ページ。
⑥ 1901~1905年は大河原三郎実習報告書。
⑦1907年は古市六三実習報告書12ページ。
3) 熔解精鉱量は以下の史料による。①1896年以前は崎川茂太郎実習報告書、②1897年以降は『栃木県史』史料編・近現代九124~125ページ。
最左欄の坑夫数は,何等かの資料的根拠をもっており,いちおう信頼し得る数値である。その右隣が推定坑夫数であり,この推定方法について,やや詳しく述べておこう。
推定の基準として熔解精鉱量を使ったのは,これが全年次について得られるほぼ一貫した数値だからである。本来であれば,採鉱量を用いるべきであろうが,1888~93年,97,98年の8年分について記録が得られなかったのである。
ところで坑夫数の推計に熔解精鉱量を利用すると,いくつか難点が生ずる。その1つは,製煉能力を上回る出鉱があった場合に,精鉱が翌年に繰り越されることである。この場合,そのまま熔解精鉱量を使うと,当該年度の推定坑夫数は過小となり,翌年度の推定坑夫数は過大となるおそれがある。ただ,そうした年は,比較的よく知られている。すなわち,1884,87,97年がそれである。1884年は出鉱の激増により,1887年は直利橋製煉所の火災により,1897年が鉱毒予防命令による工事のため,出鉱の一部を翌年に繰り越している。それ以外で出鉱の一部を翌年に繰り越した可能性があるのは1890年である。この年は例の古河産銅一括販売契約の最終年であり,かなりの増産があったはずである。ところが,契約終了後の91年が,その前後の年との比較で,とび抜けた高さの熔解精鉱量になっている。これは,おそらく1890年に採鉱量は増大したが,製煉能力がこれに追い付けなかったものと考えられる。翌91年は,製煉が全面的に一部水套式熔鉱炉にきりかわってからの初年度で,この繰り越し鉱を処理したものであろう。こうした点は推定に当たって考慮することで,推計値の誤差を減らすようにするしかない。
熔解精鉱量を坑夫数推計のために使用する際,もう1つ問題となるのは,年によって採掘対象となる鉱体の品位が違い,また鉱脈の硬軟など採掘の難易が変化し,これが一人当りの精鉱量に影響することである。また,開坑作業と採鉱作業への坑夫の配分比が,年によって違うことも問題である。しかしこうした点は,精鉱量でなく採鉱量を使用してもおこることで,前後に比べて飛び抜けた違いのある年について配慮するほかない。
この他,選鉱能力が向上すると,採鉱量は同じでも熔解鉱量は増大するし,熔鉱炉の性能向上にともない,製煉可能な鉱石品位は低下したから,傾向的には坑夫1人当りの精鉱量は増したものと思われる。しかし,一方では選鉱・熔鉱能力が低い段階では,採鉱は〈抜き掘り法〉によったから,採掘量に比し精鉱量は多くなるのに対し,〈階段掘法〉採用後は採掘量の割には精鉱量は少なくなる。いずれにせよ,こうした問題は,つぎに検討する坑夫1人当りの精鉱量を決める時に配慮することにしよう。
1880年代において坑夫数の判明している5年間について,坑夫1人当りの年間精鉱量の平均をとると3,338貫である。もし,横間歩 の〈大直利〉での採鉱が本格化していた1884年以降の3年間だけをとれば3,889貫となる。85年が飛び抜けて多いのは,すでに述べたとうり84年に出鉱が激増して製煉能力を越え,92万4,142貫が85年に繰り越されたためであった。この2年間の平均は4,240貫である。 の〈大直利〉での採鉱が本格化していた1884年以降の3年間だけをとれば3,889貫となる。85年が飛び抜けて多いのは,すでに述べたとうり84年に出鉱が激増して製煉能力を越え,92万4,142貫が85年に繰り越されたためであった。この2年間の平均は4,240貫である。
つぎに1900年代で坑夫数の明らかな5年間について,同様に坑夫1人当りの年間精鉱量の平均をとると4,097貫である。1880年代の5年間との比較では22.7%の増であるが,84年以降の3年間の平均とくらべると僅かに5.3%の伸びでしかない。この間における選鉱部門や製煉部門の生産性の急上昇とは対照的である。
何故このような相違が生じたのかは,明らかである。選鉱部門では動力化・機械化がすすみ,製煉部門でも洋式熔鉱炉の導入成功により,大量処理の連続操業が実現したのに対し,採鉱部門では技術的進歩は主として運搬・排水・通風といったいわば間接面に集中し,直接鉱石を採取する作業については1890年代以降ほとんど進歩がみられなかったからである。
ただし,ここには足尾銅山独自の事情があることも考慮しなければならない。その1つは,1884年,85年に採掘の対象となった鉱脈が,採掘の容易な粘土脈で,しかも鉑幅は広く,品位の高い異例の優良鉱脈であったことである。だが,その盛況は比較的短期間で終っていた。1885年に足尾を視察した原田慎治は「横間歩 ハ最良ナルモノニシテ盛況ヲ呈セシトキハ厚サ八尺,鉑線三尺ニ及ヒシモ,現時ハ平均三尺,鉑線ハ七,八寸ナルベシ(36)」と述べている。すでに85年の後半には最盛期は過ぎていた。これを裏付けているのは坑夫1人当りの採鉱量で,1884年が4,520貫であったのに,85年には4,019貫,86年には3,298貫と減少している。さらに1896年になると,坑夫1人当りの精鉱量は2,650貫にすぎない。しかし1896年の減少は,坑夫の採鉱能力の低下によるものではない。なぜなら,坑夫1人当りの1番粗鉱の採鉱量は5,186貫で,1884年の4,520貫,85年の4,019貫を上回っているのである。 やはり1884,85年の坑夫1人当りの採鉱量,精鉱量は異例の富鉱脈に助けられて,かなりの高水準に達していたものと見るべきであろう。 ハ最良ナルモノニシテ盛況ヲ呈セシトキハ厚サ八尺,鉑線三尺ニ及ヒシモ,現時ハ平均三尺,鉑線ハ七,八寸ナルベシ(36)」と述べている。すでに85年の後半には最盛期は過ぎていた。これを裏付けているのは坑夫1人当りの採鉱量で,1884年が4,520貫であったのに,85年には4,019貫,86年には3,298貫と減少している。さらに1896年になると,坑夫1人当りの精鉱量は2,650貫にすぎない。しかし1896年の減少は,坑夫の採鉱能力の低下によるものではない。なぜなら,坑夫1人当りの1番粗鉱の採鉱量は5,186貫で,1884年の4,520貫,85年の4,019貫を上回っているのである。 やはり1884,85年の坑夫1人当りの採鉱量,精鉱量は異例の富鉱脈に助けられて,かなりの高水準に達していたものと見るべきであろう。
坑夫1人当りの精鉱量が1880年代と1900年代との間で,ごく小幅の上昇でしかなかったもう1つの理由は,1890年代の後半からすすんだ階段掘法導入の影響である。鉱脈の富鉱部だけを採取する抜き掘法にくらべ,階段掘法では一定の幅で掘り進むため,採掘量に比し精鉱量は減少せざるを得ない。これについては,いま見た1896年の数字が,明瞭に示している。1894年,1901年,1902年についても,坑夫1人当りの採鉱量は1880年代を上回っている。
そこで,問題の坑夫数推定の根拠となる坑夫1人当りの精鉱量について考えてみよう。まず1880年代後半から1890年代前半であるが,1884,85年は異例であるから除き,ここで参考にし得るのは1886年と1894年,96年である。この3年間を平均した坑夫1人当りの精鉱量は3,040貫である。そこで,1887年から95年については,坑夫1人当りの精鉱量を3,100貫と仮定して大過ないであろう。ただし,さきに指摘したように1890年の採鉱の一部分が翌年に繰り越された可能性が高いと見られるので,同年の精鉱量を700万貫,翌91年を671万4,000貫とした。つぎに1897年であるが,5月に第3回鉱毒予防命令が出て,小滝製煉所は廃止,本山製煉所も脱硫塔の建設工事と併行して製煉作業がおこなわれていた。また,竣工期日を限られた工事のため,坑夫等も坑外作業に駆り出されていた。そこでこの年は坑夫1人当り精鉱量を2,500貫と仮定した。1898年以降の坑夫数推定の根拠には,坑夫数が判明している1900年以後の5年間の平均が4,097貫であるので,4,100貫と仮定した。
もとより,この推定坑夫数はあくまで参考でしかない。しかし,その誤差の範囲は比較的小さいと思われる。もともと,この当時の足尾銅山の労働者数は季節的な変動がいちじるしく,ある時点での坑夫数がその年の平均値を示すとは限らないのである。たとえば1901年の坑夫数は最多の12月で3,373人であるのに対し,最少の6月は2,719人である(37)。仮にこの年の坑夫数を精鉱量から算出してみると,3,092人となる。他の年次についても,推定坑夫数はその年度中の変動幅の中におさまっていると見てよいのではないか。
【注】
(25) 「草倉銅山記事」(『日本鉱業会誌』第15号,1886年5月,《日本鉱業史料集》第1期 明治篇④『足尾銅山概況等』56ページ)。
(26) 茂野吉之助『木村長兵衛伝』55ページ。
(27) 労働運動史料委員会編『日本労働運動史料』第1巻,79ページ。ただし,火薬使用が〈常慣〉ではあっても,採掘の対象となった部位が粘土質の場合は火薬は使われていない。草倉の視察報告を書いた原田慎治は,同じ頃足尾にも行き,つぎのように報じている。「鉱脈ハ堅硬ナラザルヲ以テ単ニ尖鑚ト手鎚ヲ以テ採獲スルモ,岩石ハ弾薬ヲ以テ之ヲ破砕ス。又非常ニ堅実ナルカ或ハ湧水ノ為メ火薬ヲ使用スルコト能ハザルトキハ〈ダイナマイト〉ヲ以テス」(『栃木県史』史料編・近現代九,22ページ)。
(28) 「栃木県下足尾銅山点検報告」(『栃木県史』史料編・近現代九,20ページ)。
(29) 採鉱法の歴史的変化の詳細については,村上安正氏の一連の論考を参照されたい。『鉱業論集〔Ⅱ〕』(自費出版,1986年),「近代前期に至る手掘採鉱についての考察」(『日本鉱業史研究』第10号,1982年3月),「足尾銅山の採鉱過程をめぐって」(『技術と文明』3巻2号)。
(30) 村上安正氏にならい,はつり作業用の鑚には漢字を使い,鑿孔作業用のタガネは片仮名で表記する。「近世の鑚,近代のタガネは日本語では同一名称であるが,機能的には大きな違いがある。すなわち鑚は,Iron wedge(鉄楔)であるのに対し,近代のタガネ(採鉱用の発破タガネ)は,Drill steelである」(村上安正「足尾銅山の採鉱過程をめぐって」『技術と文明』3巻2号の注(7))。
(31) 日本で最初に実用に供されたこの鑿岩機については,三田守一「阿仁鉱山隧道ノ話」(『工学会誌』第47巻,1885年11月)に詳しい。
(32) 蓮沼叢雲『足尾銅山』(公道書院,1903年)80ページ。
(33) 市原博「第1次大戦後の産銅業労資関係の展開」(『歴史学研究』第522号,1983年11月)8ページ。
(34) 1879年に阿仁銅山が購入したシュラム式鑿岩機の価格は2台1組で800円,圧気機は赤羽工作分局が製造したもので2,460円であった。阿仁では圧気機の動力として水車を用いたがm足尾では150馬力の蒸気タービンを使用した。また経常費を阿仁の場合で見ると,鑿岩機使用の場合は掘鑿1メートルにつき22円50銭にたいし,手掘りでは15円であった(三田守一「阿仁隧道ノ話」(『工学会誌』第47巻,1885年11月参照)。
(35) その後の足尾銅山における鑿岩機の導入経過については,村上安正『鉱業論集』〔Ⅰ〕〔Ⅱ〕(自費出版,1986年)参照。
(36) 原田慎治「足尾銅山記事」(《日本鉱業史料集》第1期 明治篇④『足尾銅山概況等』25ページ)。
(37) 『栃木県史』通史編8・近現代三,622ページ。
[初版は東京大学出版会から1988年5月10日刊行]
[本著作集掲載 2006年6月11日]
【最終更新:
|