《編集雑記》4 (2001年4月〜2001年12月)
1ヵ月あまり更新を怠ってしまいました。やはり引っ越しはたいへんでした。今回はとくに海外への移動でしたから。といっても別に海外へ移住したわけではなく、約1年間の予定でアメリカへ来ているだけですが。今回は、出発前から住宅が決まっていたり、前任者から車を譲り受けることができたりと、好条件に恵まれていたのですが、それでもなんとか落ち着くには時間がかかりました。
実のところ、まだ軌道にのったとは言えない状態ですが、それでも「雑記」を書き始めたのは、古巣の法政大学大原社会問題研究所のサイトがこの1ヵ月余の間に大発展したことを、読者の皆さまに知っていただきたいと思ったからです。
なかでもご注目いただきたいのは、本日、つまり4月20日、月刊の機関誌『大原社会問題研究所雑誌』のオンライン化という快挙をなしとげたことです。今回は、最新号の2001年4月号と、2000年度分、つまり2000年4月号から2001年3月号まで全12号のバックナンバーの公開だけですが、今後は雑誌の刊行からあまり時間をおかずに最新号を掲載すると同時に、バックナンバーについても順次追加されてゆくことが予告されています。 詳細は、直接オンライン版『大原社会問題研究所雑誌』でご覧ください。PDFファイルですからアクロバットリーダーが必要ですが、無料ソフトですからどなたでもご利用いただけます。
そのほか、目立ちませんが、研究所が所蔵する戦前期の原資料のほぼ全容を把握できる「戦前期原資料インデックス」が先月下旬に公開されました。これまでは、直接、研究所にいらしていただき、カードで検索するほかなかったものが、ご自宅からでも利用可能になったわけです。研究所の所蔵資料についてお詳しくない場合は、まずリストアップ版をご覧ください。そこで概要を把握された上で、ご自分の関心のある分野についてはさらにデータベース版で詳しく検索なさると良いのではないかと思われます。
また『日本労働年鑑』別巻として刊行された、『太平洋戦争下の労働者状態』および『太平洋戦争下の労働運動』の2冊と、戦後労働組合運動の再出発の時期を記録した『日本労働年鑑』の第22集から25集もこの間に研究所のサイトで読んでいただけるようになりました。戦中、戦後という日本の労働運動の歴史でも波乱万丈の時代についての記録が、オンラインで読み、全文検索できるようになったことは、はやり大きな意味をもっていると思います。
もうひとつは、長い間絶版になっていた『大原社会問題研究所五十年史』の全文が公開され、これはオンデマンド出版として活字版でも入手しうる形をとったことです。
最後に、これまで大方のご好評を得てきている「社会・労働関係リンク集」に収録されている日本のすべての労働サイトを横断的に全文検索するシステムが本格的に発足しました。まだ、正式名称ではないのですが、労働サイト全文検索という仮称で稼働しはじめました〔2001年5月《労働サイト横断検索》と正式名称を決定〕。同様のシステムにJILの「労働情報ナビゲートシステム 」があるのですが、あちらは大学や官庁、労働組合全国組織など、労働とはかならずしも関連しない大組織を中心に採録しているのに対し、こちらは「社会・労働関係リンク集」に収録されている労働関連サイトを網羅しています。つまり、労働関係であれば、個人のサイトや労働組合でも単組や分会レベルまで検索できる点が違います。
なお、これはすでに歴史があるのですが、OISR.ORG内の検索も、個別のコンテンツを選んで検索することが可能になっています。つまり、この二村一夫著作集だけを対象に全文検索をかけることも出来るのです。
ぜひいちど
OISR.ORG(法政大学大原社研)をお訪ねくださって、その内容の急速な充実ぶりを直接お確かめください。
〔2001年4月20日記、23日補訂〕
1997年7月、岩波文庫の1冊として高野房太郎著、大島清・二村一夫編訳『明治日本労働通信──労働組合の誕生』を刊行しました。同書は、高野房太郎が35年余の生涯の間に書き残した文献を、筆名、匿名をふくめ網羅することを目指して編集したものでした。しかし、同書を買ってくださった読者には申し訳のないことですが、その後房太郎が「O.F.T.」の名で『読売新聞』に執筆した論稿を5本、〈在米桑港 一商生〉の名で発表した論稿を1本発見しました。
また、解説にかえて執筆した「高野房太郎小伝」に、訂正すべきところがあることもわかりました。
しかし、まだ初版が売り切れずに残っている活字版を訂正することは出来ませんので、とりあえず本サイトで、同書の補訂をおこなうことにしました。こういう小回りのきく処置が簡単にできるのは、インターネットの利点というべきでしょう。いずれは、サミュエル・ゴンパーズの手紙も掲載し、往復書簡として読めるようにしようかなどと考え始めています。
なお今回の処置は、出版社とは無関係に、同書の編集・翻訳・解説を担当した二村一夫個人の責任においておこなうものです。とくに問題になることはないだろうと思いますが、念のためひとこと。
また、「米国桑港通信」など追補分のテキストファイル作成は、リブロ電子工房にお願いしました。旧字、変体仮名など読みにくい原稿を正確にテキストにしてくださった是枝洋さんに厚くお礼申し上げます。
〔2001年5月20日記〕
「火星の井戸掘り」というサイトがあるのをご存じでしょうか。『ルネッサンスパプリッシャー宣言』や「投げ銭システム」の提唱などで知られた、ひつじ書房社主の松本功さんがプロデューサー兼スポンサーで、開設されているものです。
4人の評者が、人文・社会科学系の学術関連ホームページのうち紹介に値すると考えたサイトだけを批評し、点までつけてしまおうという「サイト評サイト」です。データベース化されていて、さまざまな件名で引き出すことが出来る仕組みになっており、2001年5月現在675サイトが採録されています。担当者は各サイトの内容を実際によく見た上で、かなり率直にコメントしています。なかには、どうかなと思う意見もないではありませんが、仲間ぼめの相互リンクや、トップページだけを見てコメントを書いているリンク集が多いなかで、有意義な企てだと思います。まだご覧になったことがない方は、ぜひいちどお出かけになってはいかがでしょうか。文字通りのお勧めサイトです。
この3月末、松本さんと、このサイトで直接批評を担当している2人の方からインタビューを受けました。その記録が、このサイトのオンライン・ジャーナルである『火星の井戸掘り新聞』の第2号
に掲載されています。中味は直接ご覧いただくことにして、とりあえずご報告まで。
〔2001年5月21日記〕
日本を出る前に、季刊『本とコンピュータ』の座談会に参加しました。その記録は、「徹底討論 資料のデータベース化も〈知的生産〉である」として、20001年4月10日に発行された第16号に収録されています。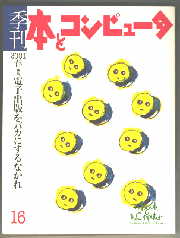 実は、この雑誌は、はじめに4年間だけ出すことを決めて創刊されたので、これが最終号でした。もっとも9月には、第2期創刊号が出ていますが。ほかの参加者は、早稲田大学図書館の金子昌嗣氏、横浜美術館の相澤勝氏、ノンフィクション作家の中野不二雄氏、いずれも情報関連の専門家で、いろいろ教えられました。 実は、この雑誌は、はじめに4年間だけ出すことを決めて創刊されたので、これが最終号でした。もっとも9月には、第2期創刊号が出ていますが。ほかの参加者は、早稲田大学図書館の金子昌嗣氏、横浜美術館の相澤勝氏、ノンフィクション作家の中野不二雄氏、いずれも情報関連の専門家で、いろいろ教えられました。
私は、主として法政大学大原社会問題研究所のデータベース制作の経緯について報告しました。もっとも、いちばん強く主張したのは、やや本題から逸れた発言でしたが、現在の著作権制度がインターネット時代にはそぐわない事実でした。どうも、いまの著作権は、実際に知的生産に携わっている人の権利を守っているというより、知的財産をもとにしたビジネスに従事している企業の利益保護に重点が置かれすぎているのではないかということでした。いまネット上では、世界中で、著作権の切れた文献を中心に、ボランティアの手で、つぎつぎとE-TEXT化がすすんでいます。これがどれほど知識の共有に大きな力を発揮しはじめているか、その可能性の大きさははかりしれません。ところがその際、ネックになっているのが、著者の死後50年という長期間の著作権の存在です。しかも、国際的な傾向としては、この期間はさらに70年に延長される可能性があるようです。
もともと、ものを書く人びとは、他の人たちに読んで貰いたいから書いてきた、また書いているわけです。死後70年となると、自分の書いたものの権利者が誰になっているかさえ分かりません。作家などが、若い貧乏時代をともに過ごした配偶者の生活を考えて著作権を残すとすれば、その配偶者の生存期間で十分ではないかと思うのです。あるいはせめて可愛い孫のためというなら、それも分からなくはありません。しかし現状は、そうした物書きの気持ちとは無関係なところで、ビジネス上の権利が一人歩きしているように思えてなりません。
〔2001.10.22〕
インターネット時代の著作権(2)
すっかりご無沙汰いたしてしまいました。あれこれと忙しい日々が続き、更新を怠っている間に、本サイト開設4周年の9月25日はとっくに過ぎ去っていました。これまで毎年9月25日には大改訂をしてきたのですが、今回はなにも出来ませんでした。それどころか、アメリカでも連載を続けると宣言していた『高野房太郎とその時代』は、出発前の1月に「スクールボーイ」を書いたのを最後に、まったく書き進めずにいます。その後は、文字どおりの時間稼ぎに、高野房太郎の未発表資料「米国桑港通信」や、その昔まとめた座談会 政経ビル時代の思い出──戦後初期の大原社研を掲載してお茶をにごしてきました。しかし、それも8月はじめのことでしたから、この2ヵ月あまりは、背景の模様替えをしたりリンク先を追加したほかは、ほとんどなにも更新せずに来てしまいました。《編集雑記》にいたっては、5月末に書いてから4ヵ月あまり音なしでした。自分で編集する著作集は催促してくれる編集者がいませんので、いったん中断してしまうと再開するのが容易ではありません。
おいおいご説明するような事情でしばらくサイトの更新に時間をさく余裕はありませんので、とりあえずはいくつか「近況報告」をさせていただくことで、ごカンベンいただきたいと思います。なお『高野房太郎とその時代』については、アメリカにいる間にもう少し調べておきたいこともあるので、勝手ながらしばらく休載させていただきます。
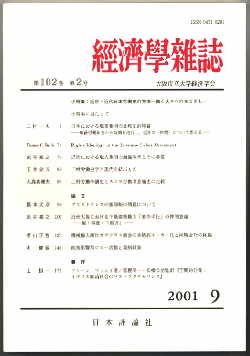 実はサイトの更新がすすまなかったひとつの理由は、この5ヵ月ほど日本近世史とヨーロッパのギルドやクラフト・ユニオンのことを勉強して、小さな論文を書いていたからでした。その論稿が、このたび大阪市立大学の『経済学雑誌』(日本評論社発売)の第102巻第2号(2001年9月号)に発表されました。「日本における職業集団の比較史的特質──戦後労働組合から時間を逆行し,近世の〈仲間〉について考える──」と題する小論です。なんと《小特集:近世・近代日本労働史の方法──働く人々へのまなざし》の巻頭論文で、武谷嘉之、玉井金五、大島真理夫のお三方が私へのコメントを書いてくださっています。「追悼号みたいだ」と言う人がいるほど過分の扱いです。小特集には、わが敬愛する友人トム・スミス(Thomas C. Smith) の英語論文 "Right Ideology in the Japanese Labor Movement" が収められているのも嬉しい限りです。小論は、いずれ本サイトにも掲載するつもりでおりますので、ご一読いただければ幸いです〔2000年11月20日に、この論文は第1巻第5章として、増補のかたちで掲載しました〕。今回の論稿は、これまでの私の研究をいくらか整理し、論点を近世にまで広げたものです。
実はサイトの更新がすすまなかったひとつの理由は、この5ヵ月ほど日本近世史とヨーロッパのギルドやクラフト・ユニオンのことを勉強して、小さな論文を書いていたからでした。その論稿が、このたび大阪市立大学の『経済学雑誌』(日本評論社発売)の第102巻第2号(2001年9月号)に発表されました。「日本における職業集団の比較史的特質──戦後労働組合から時間を逆行し,近世の〈仲間〉について考える──」と題する小論です。なんと《小特集:近世・近代日本労働史の方法──働く人々へのまなざし》の巻頭論文で、武谷嘉之、玉井金五、大島真理夫のお三方が私へのコメントを書いてくださっています。「追悼号みたいだ」と言う人がいるほど過分の扱いです。小特集には、わが敬愛する友人トム・スミス(Thomas C. Smith) の英語論文 "Right Ideology in the Japanese Labor Movement" が収められているのも嬉しい限りです。小論は、いずれ本サイトにも掲載するつもりでおりますので、ご一読いただければ幸いです〔2000年11月20日に、この論文は第1巻第5章として、増補のかたちで掲載しました〕。今回の論稿は、これまでの私の研究をいくらか整理し、論点を近世にまで広げたものです。
アメリカにいながら何で日本近世史だと思われるかもしれませんが、ここハーバード大学のエンチェン(燕京)図書館は、中国、日本、韓国・朝鮮など東アジア語の図書を中心に約100万冊を所蔵しているのです。もちろん一番充実しているのは中国語文献で蔵書の半分以上の56万冊ですが、日本語図書も26万冊を所蔵しています。そのほとんどは日本に関する文献ですから、日本研究用の図書に限れば、日本の多くの大学図書館より充実しているかもしれません。〔2001.10.22〕
このところ、著作集の更新がすすまなかったひとつの理由は、アンドルー・ゴードンといっしょに比較労働史のゼミを担当しているからです。いやこの言い方はちょっと不正確で、就労を禁止しているJ1ヴィザの条件違反を疑われかねません。正確にはアンドルー・ゴードンに頼まれ、彼が担当しているゼミの〈助っ人〉をしているわけです。ご承知のように、アメリカの大学のゼミは、リーディングリストに基づいて学生に本を山のように読ませるところに特徴があります。日本の大学のゼミはどちらかというと熟読玩味型が多いと思いますが、こちらは、1回に数冊の本をとりあげることはざらです。
ページ数が多いといっても、学生達の多くにとっては自国語の本ですから、1週間で数百ページ程度を読むことは、それほど大変ではないでしょう。しかし、私のように英語を自国語としない者にとっては、これはかなりの負担です。また学生として参加するわけではないので、割り当てた章だけ読めばすむというわけにもゆきません。おまけに、なかにはE.P.Thompsonの The Making of the English Working Class. のような難物があります。900ページ余の長さもさることながら、さまざまな公文書、文学作品、評論、詩や俗謡、手紙や日記などがふんだんに引用されています。そこで使われている古いスペリング、発音そのままを表記した当て字などには、当方の理解をこえるものが少なくありません。さらにトムソンは、さまざまな人物、地域、事件をつぎつぎと引き合いに出して論じているのですが、それを門外漢に分かるように説明してくれてはいません。知っているのが当然という態度なのです。名文であるだろうことは察しがつきます。しかし、私のようにイギリス史、イギリス文化についての基礎的な素養を欠いている者にとっては、かなり歯ごたえがある本で、辞書や辞典のお世話にならずに読み進むことは不可能です。その昔、ずいぶん時間をかけて読んだことのある本ではありますが、それも四半世紀以上前のことです。ただ、その時との大きな違いは、パソコンに入れてある電子辞書が使えること、またこれに出て来ない単語や事項についてOEDやBritanicaをオンラインで利用して調べることができるのようになったことでしょう。ハーバード大学の図書館経由だと無料で使えるので、これは助かります。
私が出席することで学生たちにどの程度プラスになっているのかは、はなはだ心もとないところですが、私にとっては大いに勉強になります。なにしろ、短期間にこれだけの数の本を読むことはあまりないことですから。ゼミでどんな本を取り上げているかは、コースのサイトhttp://www.courses.fas.harvard.edu/~hist1955/がありますので、ここをお訪ねくださればお分かりいただけます。なお、なおこのサイトのリンク集のメンテナンスも私が担当しています。シラバスにあわせて関連サイトを探しだしてリンクしています。こちらもお試しください。
〔2001.10.22〕
昨年暮に書いた《編集雑記》で、小著 The Ashio Riot of 1907:A Social History of Mining in Japan(Duke University Press, 1997)に対する書評について調べ、オンラインで読めるものを中心に「英文小著への書評」として紹介しました。その後、もう1点、アーウィン・シャイナー(Irwin SCHEINER)が書評してくれているのを発見しました。なんと「灯台もと暗し」で、東京大学社会科学研究所の英文機関誌 Social Science Japan Journal Volume 3, Issue 2.(October 2000)に掲載されていたのです。 これで、小著への書評・紹介は13点になりました。Social Science Japan Journal は、出版元の Oxford University Pressのサイトからオンラインでも読むことができます。ただし有料です。
実は評者のシャイナーとは旧知の間柄です。カリフォルニア大学バークレー校の歴史学教授ですが、彼が同校日本研究所の所長時代に私をバークレーに呼んでくれたおかげで、研究に専念する自由な時間に恵まれ、この英文小著のもとになった『足尾暴動の史的分析──鉱山労働者の社会史』(東京大学出版会、1988年)をまとめることができたのでした。1984年から85年にかけてでしたから、もう17年も昔になります。マグノリアの花が美しく咲いたキャンパス内の宿舎からベルタワー(Sather Tower)の傍らにある研究室に通った日々のこと、そのベルタワーから朝昼夕と毎日定時に演奏されたカリヨン(carillon)の響きを懐かしく思いだしました。
〔2001年11月2日記〕
The Ashio Riot of 1907:A Social History of Mining in Japanの書評がもうひとつ出ていることを、10年後になって知った。明治学院大学国際学部教授のThomas Paramor Gill氏が、1999年にAsian Affairsでとりあげてくださったらしい。同氏のサイト「トム・ギル研究室」で発見した。ただ残念ながら、書評の内容はまだ読んでいませんが。
〔2009年1月23日追記〕
英文小著への書評(1)
大学出版部協会の広報誌『大学出版』がオンラインでも読めることを知りました。『Web 大学出版』と題して1998年の第37号から公開されおり、最新号は第50号です。1986年の創刊ですからすでに15年の歴史をもつ季刊誌ですが、正直のところ活字版についてはあまり忠実な読者とは言えません。印象にのこっているのは『銀座百点』タイプの横長の雑誌であることくらいなのです。それも、長い間《日本社会運動史料》復刻の相棒だった法政大学出版局の平川俊彦さんから『大学出版部協会30年の歩み』などをいただいたことがあるから記憶に残っている程度の、いささか頼りない読者です。
〔訂正=雑誌が横長というのは私の勘違いで、普通のA5判でした。『銀座百点』型は25周年、30周年などに出された記念誌だけだとのことです。本文で紹介した東アジア三国合同セミナーで「組版におけるコンピュータ導入と出版界の対応」について報告されたり、『大学出版』の「製作の現場から」欄の筆者でもある法政大学出版局の秋田公士さんから教えられ、創刊号の写真をみてあらためて確認しました。どうもたいへん失礼いたしました>関係者の皆さま。「頼りない読者」どころか「読者」を名乗る資格もないことを暴露したようです。〕
じつは『Web 大学出版』の存在自体、たまたま逆リンク検索をしていて発見した次第です。「学術情報の発信」をテーマとする特集に "ACADEMIC RESOURCE GUIDE" の岡本真さんが「これからの学術情報流通におけるインターネットの役割」を寄稿され、その中で私のサイトを紹介されていたのでした。なんと「これからの学術情報流通における学術出版の可能性を示唆していると思われる2つのサイト」として『森岡正博全集』とともに例にあげてくださっています。この岡本さんの論稿で知ったのですが、現在、文科系の研究者だけでも2000人をこえる方がウェッブサイトを開設されているのだそうです。それも「業績紹介にとどまるものやゼミ生による教員紹介といったものは除いた、実際に研究者が自身で作成し、管理しているものの数」がこれだけの数に達しているとのことです。私自身、大原デジタルライブラリーで《研究論文E-TEXTリンク集》を制作していますから、多くの研究者がインターネットを通じて発信されていることは知っているつもりでしたが、2000人を超える数とまでは予想していませんでした。そうした数多くのサイトのなかから例として選ばれたわけで、嬉しいと同時に身の縮む思いがしています。
当然のことながら『Web 大学出版』でもインターネットやオンデマンド出版に関する論稿が増えています。今年9月に上海で開かれた中国・日本・韓国大学出版部協会合同セミナーのテーマも、コンピュータやインターネット出版が中心だったようです。詳しい内容は《ウェブ大学出版部ニュース》をご参照ください。また、「いま世界の大学出版部では、何が起こっているのか?」を問う第50号の特集も読み応えがあります。なかでも、アイオワ州立大学出版会売却問題を中心にアメリカの大学出版部の現況を伝えた聖学院大学出版会の山本俊明さんの報告には教えられました。ここアメリカにいると出版物の電子化への動きが急速であることを実感させられます。たとえば、ゼミで使われるテキストのうちかなりの部分が活字本ではなく、"eReserves" と称する電子情報を図書館のサイトからダウンロードしたりプリントアウトして利用するようになっています。その一例は、すでにこの《編集雑記》でご紹介した「比較労働史ゼミ」のサイトで、シラバスをご覧ください。アステリスクを1つだけつけたものが "eReserves" 指定です。
さらにインターネットである大学出版部が出している本を買おうとして、ハードカバー、ペーパーバックと並行して e-book と称するPDFなどによる電子出版物が市販されていることを、つい先日知ったばかりでした。日本でも、 辞書や百科事典のCD-ROM は前からありますが、学術専門書で活字版と同時にオンライン電子本が売られている例はまだ聞いたことがありません。e-book は海外の読者にとっては送料がかかりませんし、すぐ読める利点もあります。ただ値段はペーパーバックに比べ、ほんの少々安いだけなのです。活字本と同時に制作され、紙代も製本代もかかっていない割には高く感じます。この価格差で、実体のある活字本に慣れた一般の読者が、はたしてどれだけ購入するでしょうか。私のようにかなりのインターネット中毒でも、自分で本を買うとなれば、きちんと印刷製本したものが欲しいと思いますから。しかし、玄関にまで本を山積みにせざるを得ないような日本の住宅事情を考えると、これからは e-book も案外伸びるのかもしれません。すでにこちらでは、テキスト用に何冊もの図書を買わざるをえない大学図書館には、書庫スペースをとらないので歓迎されているようです。もちろん1冊分買えば良いというわけではなく、普通の本と同様に誰かが読んでいる時は、他の人は使えない仕組みだそうです。
いずれにせよ、こうした新たな事態に対応するにはそれなりの人的・物的投資も必要だろうし、大学出版部はどこの国でも厳しい状況を迎えているに違いないと感じたことでした。もちろんインターネット販売により、店頭に並べなくても本の内容がある程度わかり、直接、読者の手にとどきやすくなっている点は少部数出版には有利でしょう。さらに、e-book やオンデマンドなど、さまざまな出版手段を利用すれば、少部数の学術出版をてがける大学出版部にも、それなりのチャンスがあるのではないかとも思いますが、果たしてどうでしょうか。これまで公私ともに、いろいろお世話になってきた大学出版部のいっそうの発展をねがって『Web 大学出版』をご紹介するしだいです。
〔2001.11.16記、11.24訂正〕
Academic Resource Guide が、最近号(第117号、2001.12.9)の「編集日誌」で、本雑記の「インターネット時代の著作権」を紹介してくださいました。同時に、『Hotwired』の記事「著作権至上主義は文化の衰退をもたらす」も紹介されています。この「著作権至上主義は文化の衰退をもたらす」は、スタンフォード大学のロースクールで、憲法・サイバースペース法を研究されているローレンス・レッシグ (Lawrence Lessig)教授の講演を記事にしたものですが、まさにわが意を得たりの内容で、ご一読をお勧めいたします。一方、「インターネット時代の著作権」(1)は、最後のところが駆け足になってしまい、意をつくさなかった点があので、この機会にもう少し書き加えておきたいと思います。
いつも限られたサイトしか見ていない者の個人的な印象にすぎませんが、インターネット上での著作権をめぐる論議というと、ともすれば「著作権を守りなさい」という忠告か、あるいは「こうした事例は著作権法に触れるか触れないか」といった質疑応答が多く、しかもそれだけに終わっているように感じます。もちろん、一部のサイトではあっても、他人がつくった画像を盗用したり、かってに人の曲をBGMに使ったり、リンク集を無断で流用したりする事例があとをたたない点からみれば、こうした発言が多いのは当然だと思います。
しかし、より大きな問題は、世界の著作権法制が、知的生産に従事する創作者の利益を守るためというより、作者の意思や希望とは無関係なところで、レコード会社、映画会社、大出版社などの主導のもとに変えられている点ではないでしょうか。具体的には、著者の利益よりも企業や著作権管理団体の利益を優先するかたちで、著作権保護期間が異常なまでに長期化の方向をたどっている事実です。私が懸念しているのは、このような法制度のもとでは、多くの作品が読者の手に届かなくなるおそれがあることです。もちろんどんな作品でも、なんらかの形で経費がまかなえなければ出版することはできません。また、さまざまな作品を創作することによって生計をたてている人びとの利益をまもる必要があるのも当然で、その点からみれば、現在の印税や原稿料はむしろ低すぎるのではないかとさえ思います。その意味で、著作権が保護されなければならないのは当たり前のことです。ただ著者の死後50年、あるいは70年というような長期間にすることに、どれほどの合理性があるのか、それを疑っているのです。多くの著作者は、死後の、しかもこんな長期の権利保護よりも、自分の作品がより広く読まれることを望んでいるのではないでしょうか。
一方、このように長期間にわたって著作権が存続することのマイナス面は明らかです。現に出版されている書物のなかで、初版刊行後20年、30年たっても、利益があがる本がどれだけあるでしょうか。利益とまでは行かなくても、せめて出版諸経費をまかなえるだけの売れ行きが見込める作品がどれだけあるでしょうか? 〈書物復権〉など、出版社の側でも、品切れをなくすためのさまざまな試みをされていますし、その努力は貴重だと思います。しかし現実には、少なからぬ数の書物が絶版、あるいは長期品切れのまま放置されているのではないでしょうか。じっさい著者の没後50年、あるいは70年といった長期間、出版社がその書物を刊行する責任を負うことなど出来ようはずもありません。いささか不穏当な発言であることを承知で言わせていただければ、50年後に果たしてどれだけの出版社が生き残っているかさえ定かでない時代なのです。もちろん「出版権」は著作権に比べれば期間はかなり限定的ですし、出版社は「慣行に従い継続して出版する義務」を負うだけです。この「慣行」が具体的にはどのような内容であるのか私には分かりませんが、著者が争わないかぎり、「出版権」はかなり長い間存続しているのが現実ではないでしょうか。いずれにせよ、著作者側だけでなく、出版社にとっても、現行の(あるいはさらなる長期化が予想される)著作権法は、どこか間違っているとしか考えられません。
インターネットを利用すれば、そうした品切れ本、絶版本を読者の手許に届けることは比較的容易なのです。その実例は、著作権の切れた文学作品を中心に数多くのボランティアの手で電子出版をすすめている青空文庫に見ることができます。また、著者による学術書の電子復刻プロジェクトとしてはリブラリア・プロジェクトがあります。しかし、現行の著作権法の存在は明らかにこうした電子出版の推進を妨げています。レッシング教授は「著作権を回避する新しい技術――たとえば、ピアツーピア通信プログラムなど――を使用する闘いが進行中だ」と指摘しているそうです。しかし私は、そうした技術に対しても「敵」はかならずまた手をうってくるでしょうから、やはり著作権法制そのものを再検討する議論や運動がもっと活発化する必要があるのではないかと考えています。もちろん、著作権法はいまや日本一国だけでは解決できない性質の問題であるるだけに、こうした運動の前途が多難であることは間違いないところでしょうけれど。
あるいは現行の著作権法のもとでも、著者が自主的に死後の著作権を放棄したり、あるいはその存続期間を短縮する意思をもっている場合には、これを公的機関(たとえば国会図書館など)に登録し、一般的に確認できるシステムをつくりさえすれば、ある程度はこうした企業利益優先のシステムに対抗できるのではないかなどとも考えているのですが、はたしてどうでしょうか。著作権問題の専門家をはじめ、作者や出版関係者、さらには読者の皆さまなど、それぞれのお立場からのご意見を、ぜひうかがいたいと思っています。
なお、「著作権至上主義は文化の衰退をもたらす」の Karlin Lillingtonn による記事の英語原文は、つぎで読むことが出来ます。Why Copyright Laws Hurt Culture
〔2001.12.10〕
日本ですとこの季節のご挨拶のカードには「メリー・クリスマス」と書くのが普通だと思います。しかし最近アメリカでは、多様な宗教を信ずる人びとが共存していることに配慮し "Merry Christmas" は使わず "Happy Holidays" を使う人が増えているのだそうです。私自身の体験というより聞いた話ですから、それが全米どこでもそうなのか、ハーバードやMITをはじめ多数の大学があり世界中からさまざまな人の集まるボストン周辺だからそうなのかは、よく分かりません。しかし、9.11の犠牲者追悼式がキリスト教各派だけでなく、ユダヤ教、イスラム教、さらにはシーク教徒も参加し、それぞれの流儀で祈りを捧げているのをみると、おそらく全米的な傾向だろうと思います。
ただ、21世紀最初のこの1年は、残念ながらとても "Happy" とは言えない年でした。世界的な景気低迷に加え、9月11日のテロ事件とアフガン攻撃、さらにはその影響を受けたイスラエル、パレスチナなど世界各地で、多くの人びとの命が失われたのですから。とくに9.11は、多数の乗客がのった4機もの民間航空機をミサイル代わりにして、世界80ヵ国におよぶ数千人の民間人を殺戮するという悲惨な出来事でした。自らの信念にもとづき、19人もの若者が、自らの命を犠牲にすることもいとわず、憎しみの対象とは無関係な人びとを無差別に死の道連れにしたのです。とても人間が考えうること、なしうることとは思えません。しかし現実には、こうした殺戮は人類史においてしばしば繰り返されてきた出来事のひとつです。犠牲者の数も、広島・長崎などと比べれば少ないともいえます。おそるべき非人間的な企てではありますが、人間以外にはこのような計画をたて、それを実行しうる動物がいないことも、また確かです。
9.11から早くも3ヵ月あまり経ちましたが、事件直後は、一国の国民の意識が、ひとつの出来事を境にいっきに変化しうること、このような時をこそ「歴史的瞬間」と呼ぶのであろうことなどを再認識すると同時に、アメリカ国民の反応にいささかのそら恐ろしさも感じました。なにしろ、過半数に達しない得票でようやく当選したばかりの大統領の支持率がいっきに史上最高の90%台に達し、町を走る車に星条旗がたなびき、いたるところで「ゴッド・ブレス・アメリカ」「アメリカ・ザ・ビューティフル」といった愛国歌が聞こえてきたのですから。テレビキャスター連も口を揃えて、こうした危機に際して、アメリカは一致団結して反撃する伝統のあることを論じていました。マスメディア、とりわけテレビの影響力をあらためて実感させられました。
もっともABCニュースのアンカーマン=ピーター・ジェニングスだけは、愛国心と団結を示すリボンやピンもつけず、落ち着いた報道振りが印象的でした。それだけに彼に対する批判攻撃も激烈だったようです。ちなみにピーター・ジェニングスはアメリカ人ではなく、カナダ人だそうですが。ブッシュ大統領支持派によるジェニングス攻撃の激烈な論調を直接ご覧いただけるサイトのURLをつぎに記しておきましょう。http://www.rushonline.com/peterjennings.htm
〔追記〕 愛国心を示すリボンやピンとは一体どのようなものかとお問い合わせを受けました。さしあたり次のサイトをご覧くださればお分かりいただけると思います。http://www.shopfms.com/mall/flag_pins.asp
背広の襟につけるものを"Lapel Pin"と呼ぶようですが、これだけでなく、9.11以降、星条旗をアレンジした商品が大人気だそうです。つぎのサイトをご覧になれば、星条旗をデザインしたさまざまな商品を見ることが出来ます。愛国心も旺盛ですが、商魂もたくましい人びとが少なくありません。http://www.americastore.com/starstripcol.html
〔2001.12.26〕
戦争反対を主張した高校生が孤立し退学に追い込まれた事実も伝えられましたし、ボストン市内で反戦集会もありました。ハーバードのキャンパスには「〈目には目を〉を続ければ、世界中が盲目になってしまう」といったビラも貼られていましたから、アメリカのなかにも戦争反対の声がなかったわけではありません。しかし、ごく少数派であることは明らかです。
第二次世界大戦で戦争の惨禍を身近に体験し、戦争放棄をうたった「平和憲法」のもとで育ってきたわれわれの感覚は、どうしてもアメリカ人とは違っています。サイレンを聞けば空襲を思いだし、原爆が落ちた夢で夜中にとびおきたことのある身としては、空からミサイルや新型爆弾が大量に投下されているのを知ると、いかに「テロリスト支援国」の軍事目標だけが狙われていると聞かされても、その爆弾を浴びている人びとのことを思わずにはいられません。それに、両者の軍事力があまりに違いすぎ、攻撃する側は、戦闘による死者より友軍の誤爆など事故による犠牲者の方が多いほど、安全な状況下での一方的な戦争であることも、割り切れなさを感ずる一因です。「小よく大を制する」柔道でさえ体重別制でないとアンフェアだと主張する人びとは、こうした事態をどう考えているのかと問いたくなります。
しかしアメリカ人の多くは、この軍事行動はテロ行為を企てた者たちに正義の裁きをうけさせ、テロの再発を防ぐためもので、正当な措置であると考えているようです。アメリカ国民のなかには「やられたらやりかえすのが当然」と思っている人が少なくないことは確かですが、公的な立場は「報復戦争」ではなく「テロ撲滅のための戦争」です。この点で、日本をよく知る人びとは、日本のメディアがフガン戦争を「武力報復」と呼んでいることに疑問を呈しています。報復ではない、テロ支援国を叩き、テロ集団を壊滅させるための戦争であると考えているのです。その点では、戦争反対声明の多くが「報復戦争反対」をうたっているのも、呼びかける相手に対する説得力という面でも、再検討の余地があるように感じます。
このような軍事行動はかえってアメリカに対して恨みをいだく人びとを増やし、結果的にテロ再発の危険を高めるのではないかと聞くと、アメリカが戦後の日本にしたように、アフガニスタンの民主的再建を助けることで、そうした懸念はある程度は解決すると言います。アフガニスタンを支配していたタリバーン政権が、文化財を破壊したり、女性に対して極度の忍従を強いるなど、圧制的な性格をもっていたことを知る一方で、日本が戦争に負けて占領下に諸改革をすすめたことが、どれほどその後の日本の繁栄につながったかを思い、また「鬼畜米英」を口にしたことのある私が今アメリカにいることを考えると、こうした主張にも一理あることを認めざるをえません。
ただ、アメリカへの反感は、なにもアフガニスタン人の間だけに広がり、強まっているわけではありません。アフガン攻撃は、イスラームの国々をはじめ世界のあちこちで、ビンラディンを英雄視しアメリカを敵視する人びとを増やしているのではないでしょうか。軍事作戦だけでテロ根絶が不可能なことは明らかです。ではどうしたらよいと問われると、どう考えても即効的な解決策はありそうになく、答えに窮します。パレスチナ問題の根本的解決がひとつの鍵となろうとまでは言えても、ではそれにはどうすれば良いかという、さらなる難問が生まれてしまいます。
今回の事件でアメリカ人が大きなショックを受けた背景には、長い間アメリカ本土が直接敵から攻撃されたことがなく、強大な軍事力に守られ、自国の安全に自信をもっていた事実があると思います。なにしろアメリカ本土が戦場となり犠牲者を出したのは、明治維新より前の南北戦争が最後なのです。今から136年も昔のことで、しかもこれは内戦でした。敵に襲われた経験としては60年前の日本軍による真珠湾攻撃がありますが、ハワイは本土から遠く離れた島で、当時はまだ領土ではあっても連邦を形成する州でもありませんでした。それに攻撃されたのは主として軍事施設で、まったく予想外の出来事というわけでもありませんでした。
それが今回は、ニューヨークとワシントンという、まさにアメリカの心臓部が狙われ、自分たちの目の前で多数の死傷者が出たのです。起きてしまえばこんな方法もあったのかとは思うものの、現実にこのようなテロ攻撃が行われるとは誰も予想していなかっただけに、その驚愕にははかりしれないものがありました。大陸間弾道ミサイルによる攻撃を想定し、莫大な資金を必要とするスターウォー計画まで練っていたのに、その防衛システムの盲点が暴露されてしまったのです。世界最強の「超大国」としての自負心が傷つけられた上に、航空、ホテル業をはじめ経済界への打撃も大きく、多くの解雇者がでているだけに、テロへの怒りは広がりをもち、持続的な性格をもっています。戦争反対の声に耳を傾ける精神的余裕はなく"America's New War" への支持は根強いのではないかと推測されます。
それと、テレビのキー局が集まるニューヨークで、市のランドマークのツインタワーが報道関係者の目前で崩壊し、犠牲者のなかに親族や友人知人が少なからずいたことも、その衝撃を強め、各局がいっせいに愛国心鼓吹に走った原因だったと説く人もいます。身近なことは大きく見え、遠くの出来事は小さく感ずるというのは人の性で、報道のプロたちにしても例外ではないようです。いまでも犠牲者の家族・友人たちの死者を悼む声や、かろうじて助かった人びとの涙の映像が、さまざまな機会に報道され、その度に無差別攻撃の非道さが強く印象づけられます。これも現場がニューヨークであったことと無関係ではないでしょう。
2週間ほど前が、ちょうど日米開戦の60周年にあたっていたこともあり、多くの人が今回の事件と真珠湾攻撃との比較を論じていました。そうした話のなかで、60年前のアメリカ社会も、一夜にして国民の意識が変わった点では、今回とよく似た雰囲気だったに違いないと思わせられました。
ただ今回は、大統領をはじめメディアが「この戦いはテロリズムに対する戦争であって、イスラム教やイスラム教徒を相手として戦っているのではない」と強調していたことには、いささか救われる思いがしました。こうした発言は、この60年間にアメリカ社会が人種差別をはじめ、宗教的、性別など、さまざまな差別克服の方向に動き、大きく変化をとげていることを再確認させてくれました。おそらく1960年代の公民権運動などが、こうした前進をもたらす上で力があったのであろうと思います。もちろん、もはやアメリカ社会には差別がなくなったなどと考えているわけではありません。ただ、真珠湾攻撃の直後には、西海岸の日系人全員が日本に内通するおそれがあるとして、強制的に遠く離れた収容所に入れられたのですが、今回はイスラム系とみられた人びとに対する暴行やいやがらせが散発的におきはしましたが、社会全体としてはこうした行為を一致して非難していました。この違いは大きいと思います。一方では、テロリストの周辺にいたとみなされた人びとが、はっきりした証拠もなしに移民法違反などを理由に長期間拘留されるといった事実があったことも見落とすわけにはいきませんが。
テロ行為の犠牲になった方々、アフガニスタンや中東で武力衝突の巻き添えとなった無辜の人びとのご冥福を祈るとともに、きたる2002年には、こうした事件が起きないことを切に願っています。
それでは皆さま、どうぞよいお歳をお迎えください。
〔2001.12.24記、その後補訂、最終加筆2002.1.4〕
【追記】
イスラム系社会に対する暴行は散発的とはいっても、何人もの死者がでたこともまた事実です。こうした事実については、オールタナティブ・メディアの
Flash Points で知ることができます。とくに事件直後の状況については、Your Investigative Radio Magazine が、その他の問題もふくめ多角的に報道しており、聞き応えがあります。〔2002.1.13〕
【お断り】
当初、本ファイルに収めていたつぎの小文は、《編集雑記》5に移しました。
☆ハーバード大学の内紛──Lawrence Summers vs. Cornel West
☆コーネル・ウエストの証言
☆ハーバード大学内紛事件を考える
| 