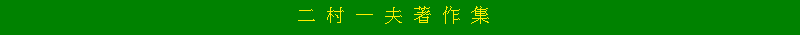 |
『足尾暴動の史的分析──鉱山労働者の社会史』
|
はじめに本書に収めた 3 編の論文と補論 2 編とは,いずれも 1907(明治40)年の足尾暴動に関連した論考である。ただし,実際に〈暴動〉そのものを対象としているのは第 1 章だけで,他の 2 編は〈暴動〉について調べる中で生まれた疑問を解くため,その歴史的背景を追究したものである。ただいずれの論文にも共通しているのは,その論争的性格と実証的方法である。どれもが,これまで,ほとんど史実によって検証されないまま,自明のこととして広く受け容れられてきた解釈を,資料にもとづいて吟味することを意図している。 執筆順序からいえば第 1 章が最も新しく,1984年秋から85年にかけて書き上げた。暴動にいたる経過,暴動そのものの展開過程とその特徴について叙述している。第 2 章以下の検討結果をふまえて書いているので,いくらかは総括的な内容をもつものとなっており,初めに読んでいただくのに相応しいのではないかと考え,冒頭にもってきた。論文の主たる意図は,従来,鉱山暴動の特徴の一つとして強調されてきた〈自然発生的抵抗〉説を検討することにある。とりわけ〈自然発生的抵抗〉説の一つである「絶望的に原子化された労働者の欝積した不満の爆発」という丸山真男氏の解釈を批判し,金属鉱山坑夫の間で徳川時代から続いて来た自主的な同職団体〈友子同盟〉が果たした積極的な役割を明らかにしたものである。 第 2 章は,1959年に「足尾暴動の基礎過程──〈出稼型〉論に対する一批判」と題して発表した論文を改稿したものである(1)。副題が示すように,そこでの主たる関心は,1950年代において日本労働問題研究に大きな影響力をもっていた大河内一男氏の〈出稼型〉論を批判することにあった。内容的には〈飯場制度〉の歴史的変化をとりあつかっている。今では〈飯場制度〉や〈納屋制度〉を,日本資本主義が生み出したもの,歴史的に変化するものとして,その生成,変質,解体において論ずるようになっているが,初稿執筆当時では,半封建的な存在として,その強固な存続を説く議論が圧倒的であった。 第 3 章は,1981年から84年にかけて執筆したもので,足尾暴動の主な担い手である坑夫(採鉱夫/開坑夫)の名目賃金が,足尾銅山の他職種の労働者と比べて高く,また他鉱山や他産業の労働者と比べても相対的に高かったことの謎を解くため,1880年代以降の足尾銅山の賃金水準の変化を探ったものである。賃金水準変動の主要因は労働力の需給関係の変化であり,それには労働力の質的・量的変化を問題にせざるを得ず,そのためには鉱業技術の展開過程の追究が不可欠であることから,内容的には鉱業技術史,とりわけ製煉技術の歴史にかなりの筆をさいている。いままで,あまり立ち入った研究の蓄積がない分野であるから,銅製煉技術史としても多少は役立つのではないかと考える。 このほか,筆者は足尾暴動研究の副産物として「原蓄期における鉱山労働者数」(2)をまとめ,また友子同盟研究の出発点であり,第 1 章の続稿でもある「全国坑夫組合の組織と活動」(3)と題する未完の論文を発表したことがある。これらも,できれば加えたいとは思ったが,紙幅の都合があり,今は改稿する時間的余裕もないので割愛した。 なお初稿発表の際は,第 3 章の一部であった「飯場頭の出自と労働者募集圏」および「足尾銅山における囚人労働」は,第 2 章の補論とした。前者は,飯場制度の中心的な機能である労働力確保の問題を扱ったもので,足尾銅山の労働市場圏を具体的に検討している。また,後者では,足尾における囚人労働を検討し,従来の研究は日本資本主義発達史における囚人労働の意義を過大評価しているのではないかとの疑問を提起している。
第 2 論文をまとめてから第 1 論文を書き上げるまで,実に25年余の歳月が経過している。いかにも〈半生をかけた作品〉とも見える年数であるが,実際は第 2 論文をまとめた後,20年余り作業を中断したために過ぎない。中断の一つの原因は必要な資料が得られなかったためである。が,それ以上に大きな理由は,筆者がこの間,法政大学大原社会問題研究所の所蔵資料の整理と,それをもとにした《覆刻シリ−ズ 日本社会運動史料》の仕事にかなりの時間をさかざるを得なかったためであった。 実は,20年余のほこりを払って足尾暴動研究再開を決意した理由はほかにもある。この中断の間,1971年に筆者は第二次大戦前の日本労働運動に関する歴史研究を総括する機会を与えられた(4)。そこで強調した論点の一つが労働争議研究の重要性であつた。本書のいわば問題関心,研究史的背景にかかわるものであるので,多少長くはなるが関連部分を引用しておきたい。 この10年来,日本労働運動史研究の主たる課題の一つは,労働組合の組織形態の変化をもたらした要因を把握することにあった。〔中略〕研究は主として企業別組合の生成要因をさぐるという観点から行なわれている。ここでも最初に問題を提起し,その後の研究の枠組みを示したのは大河内〔一男〕氏であった。ところで,この大河内氏の〈思いつき〉の背景には,次のような研究史的把握があった。 「日本の労働運動史や社会運動史の資料は,戦後たくさん刊行されているし,戦前にも若干あることはありますが,しかし,労働組合運動の歴史という観点に立ってそれらをみると,はなはだお粗末というか,低調で,どちらかというと,無産政党の歴史だとか,あるいは古くは社会主義の各分派の歴史が労働運動史という名前でよばれているのが大部分である。厳密な意味での労働組合運動の忠実な歴史的記録ということになると,はなはだ貧寒としているというのが,私どもの共通に感じたことでした。もちろん,労働組合にいくらか触れた歴史叙述が従来まったくなかったというのではありません。だがその場合でも多くは,たとえば争議とか,労使間の紛争といった普通の日刊新聞の三面を飾るようなことにつながりのある〈事件〉の歴史が中心で,労働組合の日常活動の記録はほとんど皆無にちかい。そして,そういうものに関係する限りの組合の規約とか,大会記録,その他労働組合本来のファンクションを知り得るような基礎資料はほとんど提供されていないというのが実情でした。」
この研究史的把握は,労働組合史研究のたちおくれを指摘した限りでは同意しうる。しかし,問題は労働争議を労働組合の日常活動と切り離した〈事件〉としてしか見ていないところにある。労働組合が法認されず,政府も資本家も,自主的な労働組合運動に一貫して敵意を抱いて来た戦前の日本において,労働者が労動条件を維持,改善するためにはストライキを武器としてたたかうほかはなかったのである。自主的な労働組合組織の維持とストライキは不可分のものであった。争議を抜きにして〈労働組合本来のファンクション〉はあり得なかったのである。
ここで,とくに〈特定の企業におこった争議〉を研究する必要性を強調したのには,いくつか理由がある。その第 1 は,いうまでもなく近代日本社会において〈企業〉が人々を統合する場としてとりわけ重要な位置を占めていること,なかでも労資関係という具体的な人間関係を追究するためには,どうしてもこのレベルでの検討が必要であるからである。また一方,これまで日本経済史研究などで積極的にすすめられてきた産業単位の研究では,ともすれば論理が先行し,その枠組みに適合するデータだけを拾い,不都合な資料は無視してしまうことが可能であり,従来の研究にはそうした傾向が強いと考えたからである。個別企業を対象にする場合は,前提とした論理と合わない資料があれば,論理そのものを考え直すか,資料の性格を吟味しその内容を読み直すか,あるいはその双方が要求される。既成の論理そのものの妥当性が問われている現在では,どうしてもこのような作業が必要ではないかと考えたからである。同時に,近代史研究において,資料批判がおろそかなため,既成の論理によりかかる傾向がある,あるいは既成の論理によりかかっているから,資料の読みが浅く,その読み違いに気づかずにいる例が少なくないと思えてならなかったからでもあった。 しかしながら,この二村氏の場合においてもなお,"史的分析の方法"が明確に提示されたというわけではなかった。〔中略〕二村氏にあっても,〈足尾暴動〉の分析と〈足尾暴動の基礎過程〉の分析とは,方法的に統合化される見通しをもちえていない。唯物史観の公式にいう上部構造と下部構造の相互規定性を超え出ていないのである〔中略〕〈生産技術〉の〈労働組織〉への規定性は労働者集団のあり方によって決して一様ではありえないし,またそもそも〈生産技術〉の革新自体が労働者達のあり方をも含んだ種々の条件とのかかわり合いで現実化するのである。この点を充分方法的に整理することのないまま,〈生産技術〉を起点として〈基礎過程〉を説くことは,この時期の実証研究を支配した悪しき意味での"技術主義"と自己を区別しえなくする危険をはらむものといわねばならないであろう。 この批判に対しては,足尾暴動を,その〈基礎過程〉だけでなく,〈暴動〉そのものについて分析し,両者を統合的に提示する仕事によってしか応えようがないことは明かであった。それに小論は〈基礎過程〉そのものとしても,一部を分析したにとどまり,充分とはいえないことも,当初から自覚していた。
さらに,そのしばらく後に,労働運動史研究会の例会で「日本労働運動史研究の方法」をめぐる討議が行われたが,その結論となったのは,栗田健氏の次のような趣旨の発言であった(6)。 「労資関係史研究は,善玉悪玉史観が強かった従来の労働運動史を克服する点で,研究史につけ加えたところは大きい。その成果は何よりも,日本の労資関係が日本の労働者と資本家によって作られてきたことをはっきり描いたところにある。つまり労働者はさまざまな利害対立のなかで運動を展開したのだが,資本家はそうした労働者の反対をある場合は抑圧し,ある場合は組み込みながら次の支配体制を確立して行く。ただ問題は,そうした労資関係史的方法の中心にあった争議分析の研究成果が未確定で,労働争議研究はこういうことをやったとはっきり言える所まできていないところにある」。 この指摘に対しても,争議研究の具体的な成果によってしか応えようがないことは明瞭であった。こうした友人達の批判が,足尾暴動研究を本格的に再開する決意を後押ししてくれたのである。 ところで,この争議研究の提唱は予想外の支持を得たが,当然のことながら厳しい批判も受けた(7)。その最大の批判点は,個別企業を対象とする事例研究では日本の労働運動の全体像を描くことはできない,つまり争議研究は,木を見て森を見ないものであると言うにあった。その批判に一面の正しさを認めながら,あえて個別企業の事例研究にこだわったのは,これが研究史の状況からみて必要な作業だと信じたからである。確かに,個別争議の事例研究は 1 本の木を調べるに過ぎないところがある。しかし,従来の研究が森を外から眺めるに終わっていた状況では,その森に足を踏みいれて,その森を代表する樹木を徹底的に分析することが,森の全容をより正確に把握する前提として必要だと考えたからである。もちろん 1 本の木といえども孤立して生育しているわけではないから,気候,土壌,あるいはその木に集まる虫や鳥など周囲の環境との関連を検討するのは当然である。個別企業の争議の徹底した研究を企図したのは,それがまさに日本の近代社会という森全体をより深く理解する一段階として必要であり,有効な方法であると考えたからである。全体像を見よと主張し,取り扱う対象を広くとりさえすれば,全体が把握できるわけではない。はたしてこの方法が成果をあげたか否かは,読者の判断に待つほかない。 一冊の書物にまとめるのであるから,本来ならば全体を再構成し,もっとすっきりと読みやすいものに書き改めるべきであったろう。実をいえば,何回かその計画をたて,若干の作業を始めてもみた。しかし,その都度まとめきれず,最終的にはこうした形をとることとなった。筆者の力量もあるが,もともと問題別の独立論文として執筆し,しかもいずれも論争的な形式をとったため,再構成が容易でなかったからである。そこで若干の重複や,時には相互に矛盾するところさえあるのを覚悟の上で,あえて論文集として刊行することとした。ただいくらかでも読者の理解の助けになればと思い,暴動の舞台となった足尾銅山について概観する「序章」と,全体を総括し,今後の課題についてふれる「終章」を加えた。また第 3 章の初稿は長い期間をかけて書いた上に,執筆途中で帝国大学工科大学学生の実習報告書という新たな資料を発見したため,当初予定した構成を途中で大幅に変えるなどして,甚だまとまりの悪いものとなっていたので,若干圧縮し,一部は別章の補論にまわした。第 2 章はとくに論争的なものなので,表現にかなり手を加えはしたが,基本的な論旨はもとのままである。ただし,その後訂正補充を要すると考えた箇所は補注を加えることで対処した。 このような貧しい仕事ではあっても,多くの人々のお蔭をこうむっている。なかでも石母田正先生に負うところは大きい。先生は私に歴史学への関心をよびさまして下さっただけでなく,研究者の端につらなる決意を固めさせて下さったのである。先生の無言の,絶えざる叱咤がなければ,おそらく私は本書を永久にまとめえなかったであろう。長い闘病生活ののち世を去られた先生に謹んで本書を捧げたい。先生の在世中に本書を刊行できなかったことは私の怠惰のいたすところで,悔いは残るが今となってはいたしかたない。 次に本書の中で批判の対象としてとりあげた諸先生にもこの機会に非礼をお詫びするとともに,お礼を申し述べたい。〈敵手の偉大さについて〉教えてくださったのは石母田先生であるが,大河内一男,丸山真男,山田盛太郎といった〈偉大な敵手〉をもつことができたのは研究者として幸運であった。どこにも明示していないので,念のためにつけ加えれば,第 1 章から第 3 章を通じ,つねに意識していたのは,それぞれの理論の背後に強い影響力をもって存在していた山田盛太郎『日本資本主義分析』であった。
法政大学,とくに大原社会問題研究所の諸先輩,同僚からは永年の間さまざまな形で支えられて来た。とりわけ第 1 論文をまとめた際は半年余りの自由な時間を与えていただいた。同時にこの自由な時間を過ごす上で最適の環境を提供して下さったのはカリフォニア大学バークレー校の東アジア研究所および日本研究センターであった。東アジア研究所のロバート・スカラピーノ所長,日本研究センターのアーヴィン・シャイナー所長はじめ関係者の皆様,なかでもこの貴重な機会を作って下さったトマス C. スミス教授に心からお礼を申し上げたい。スミス教授とはバークレー滞在中絶えず討議を交わす機会があり,そこで教えられたことはまことに大きい。
最後に,といっても決して付けたりではなく,この仕事を進める間に,多くの図書や資料を閲覧する便宜をはかって下さった東京大学法学部明治新聞雑誌文庫,東京大学工学部金属工学科および資源開発工学科図書室,国立国会図書館,栃木県立図書館,法政大学附属図書館の関係者の皆様に心からお礼を申し上げたい。なかでも30年近い昔,明治新聞雑誌文庫の西田長寿氏には大変お世話になった。後に資料の整理や覆刻の仕事を始め,法政大学大原社会問題研究所に労働問題専門の図書館・文書館としての機能を加えることに努めたのも,黙々と縁の下の力持ちに徹しておられた氏の後ろ姿に強い印象を受けていたからである。日本の学界が司書やアーキヴィストを大事にしないのは今や国際的にも定評がある。しかし日本近代史研究の上で明治新聞雑誌文庫と西田長寿氏が果たした大きな役割は決して忘れられてはならないであろう。この機会にあらためてお礼申し上げたい。
【注】
[初版は東京大学出版会から1988年5月10日に刊行]
【最終更新:
next 序章 暴動の舞台 足尾銅山 |
Edited by Andrew Gordoon, translated by Terry Boardman and A. Gordon The Ashio Riot of 1907:A Social History of Mining in Japan Duke University Press, Dec. 1997 本書 詳細目次 本書 内容紹介 本書 書評 |
|
|
|
|
||
Wallpaper Design © あらたさんちのWWW素材集 先頭へ |
||